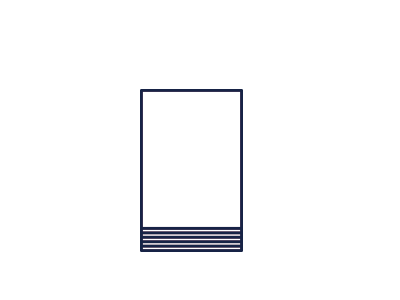古活字本と整版本
江戸初期は、活字版から整版への移行期で、同じ著作が両方の形で出版されることもあり、古活字本を覆刻した整版本もしばしば刊行されました。ここでは、両者の判別の方法について解説します。
匡郭のあるもの

史記
匡郭のあるもの
古活字本の匡郭は、上下左右の線を組み合わせて作るため、隅にしばしば隙間が生じます。匡郭のある版本では、匡郭の隅に隙間があるかどうかで、古活字本か整版本かの見当づけができます。