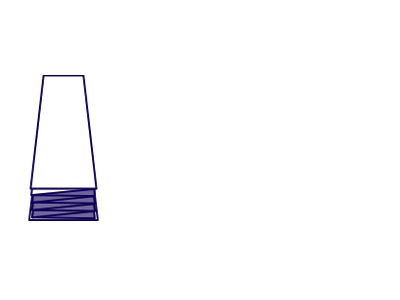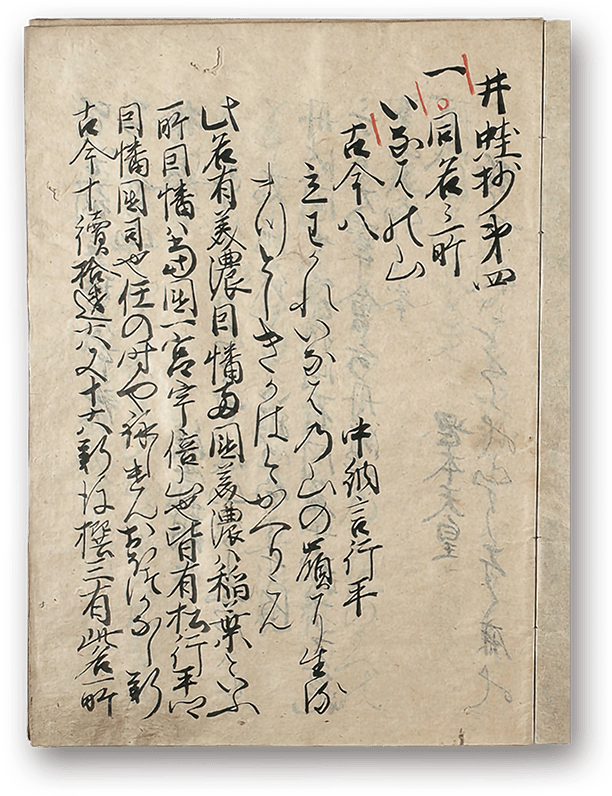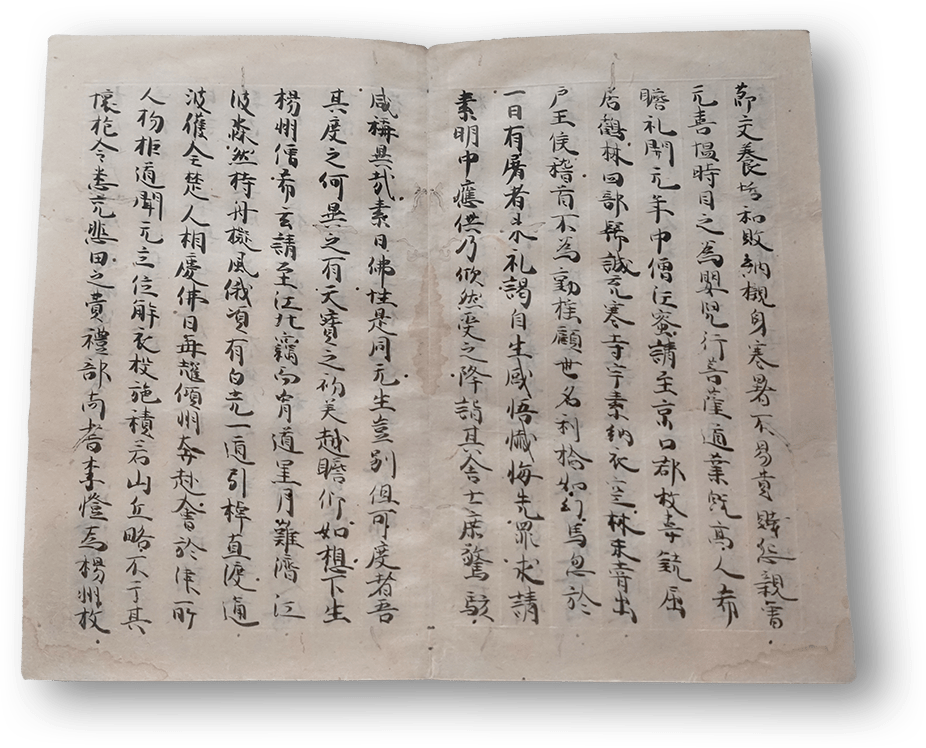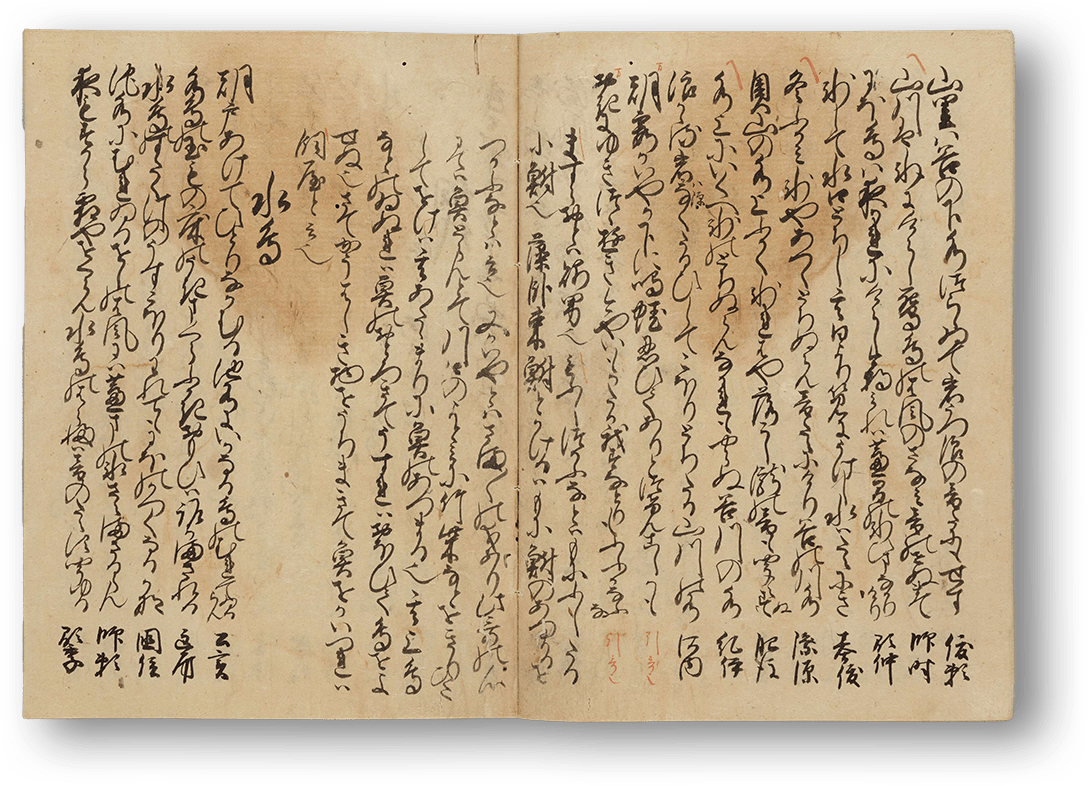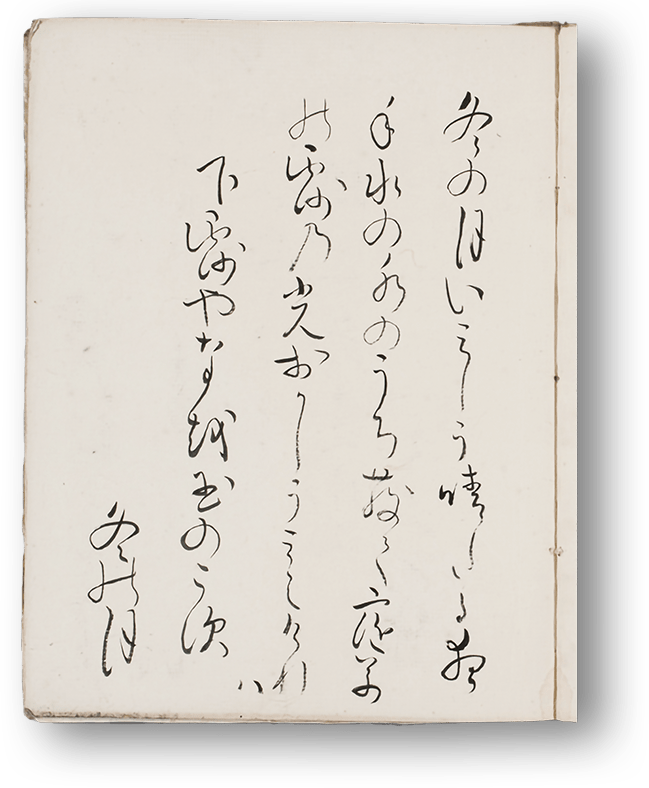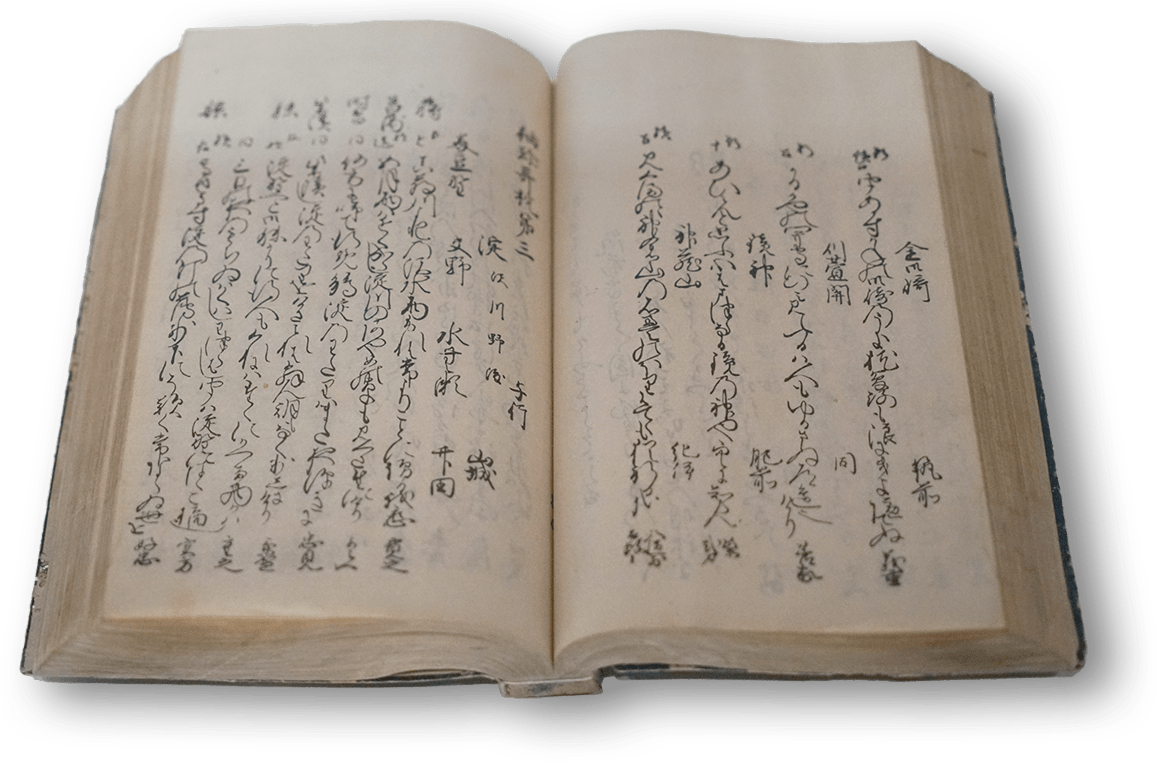料紙・附属事項
和書の本体部分は、通常は紙で作られています。ここでは和書に用いられるさまざまな紙と、料紙に附属する事項について解説します。
料紙
和書のうち、表紙以外の本体部分に使われている紙を料紙(本文料紙)と呼びます。ここでは、和書の料紙の代表的なものを例示します。
料紙

新古今和歌集
鳥の子紙(厚様斐紙)
雁皮の樹皮を材料とする斐紙のうち、厚く漉いたもの。鶏の卵のような色であることから鳥の子紙と言う。楮紙に比べて表面がなめらかである。
その他
その他

丁付
冊子本において、その丁が何丁目に当たるかを記した数字が丁付です。
その他

職原抄
界・罫
写本において、上下や行間を揃えて書くために引かれた線が界(罫)です。版本にも、界を持つものがあります。
その他

名所都鳥
匡郭
版本において、本文の周囲に引かれた枠線を匡郭と言います。線の種類により、単辺・双辺・子持ち枠などと呼びます。