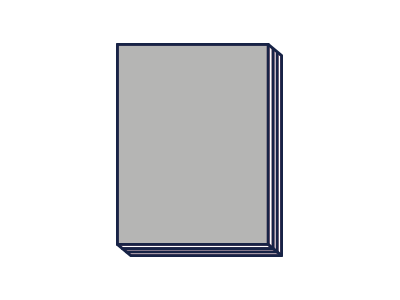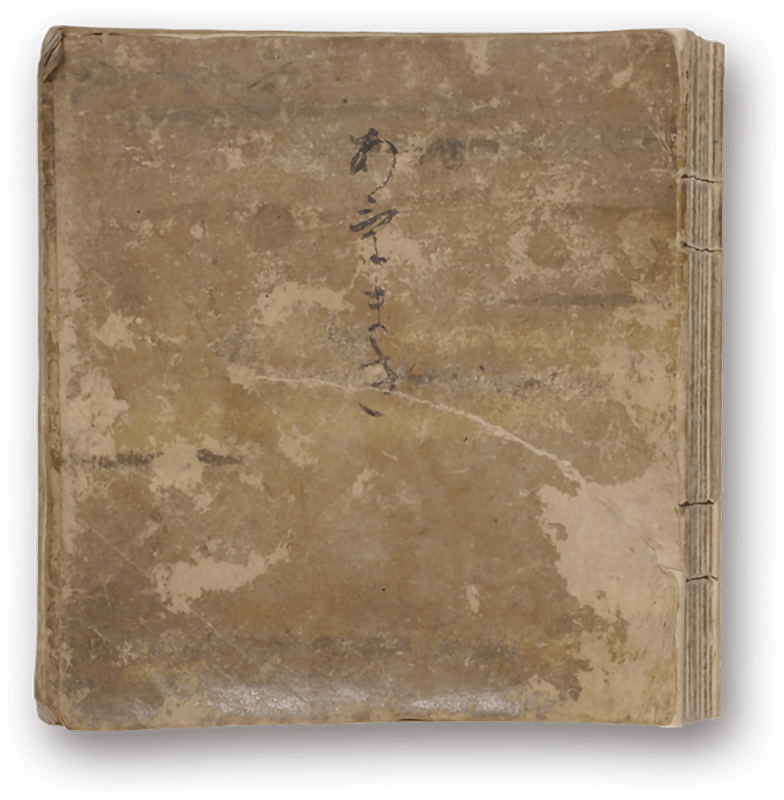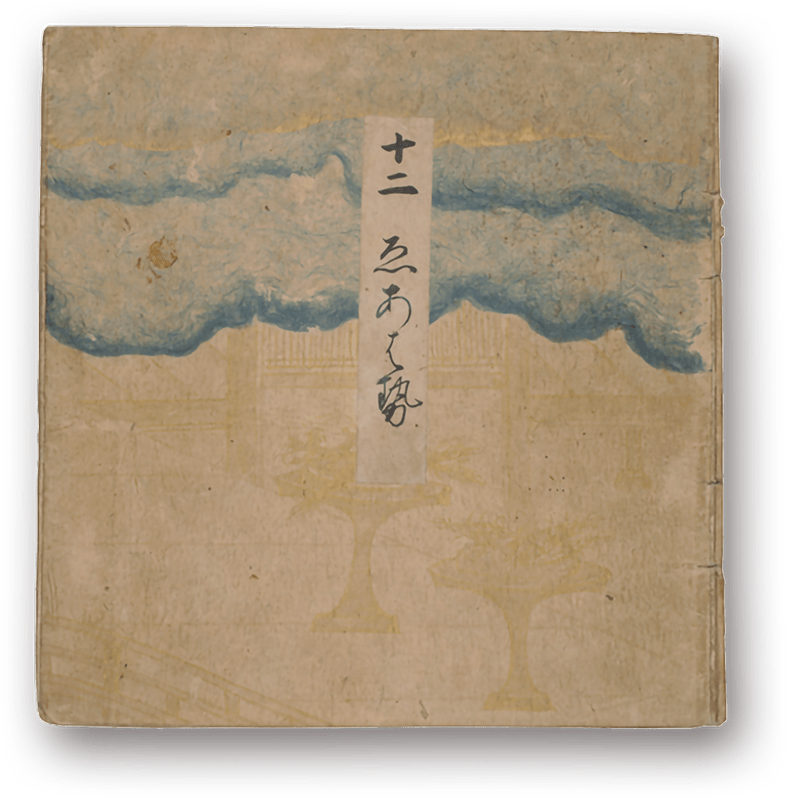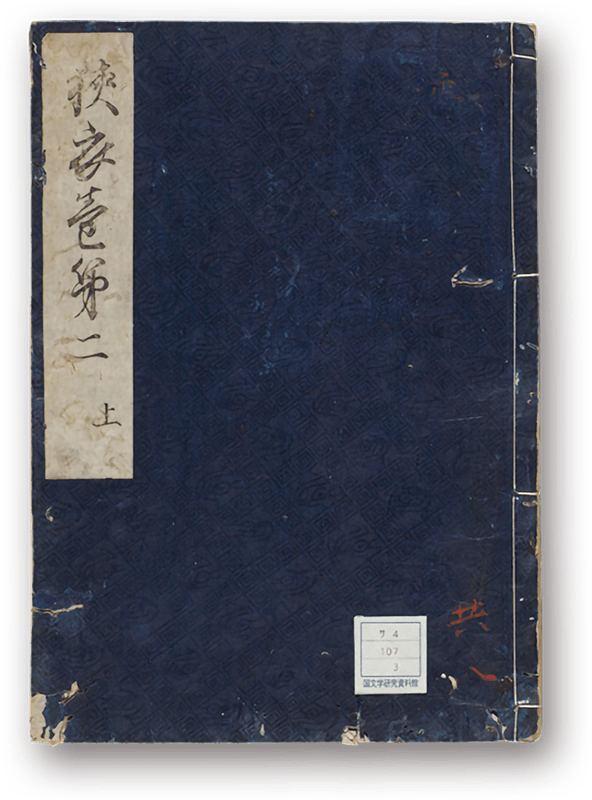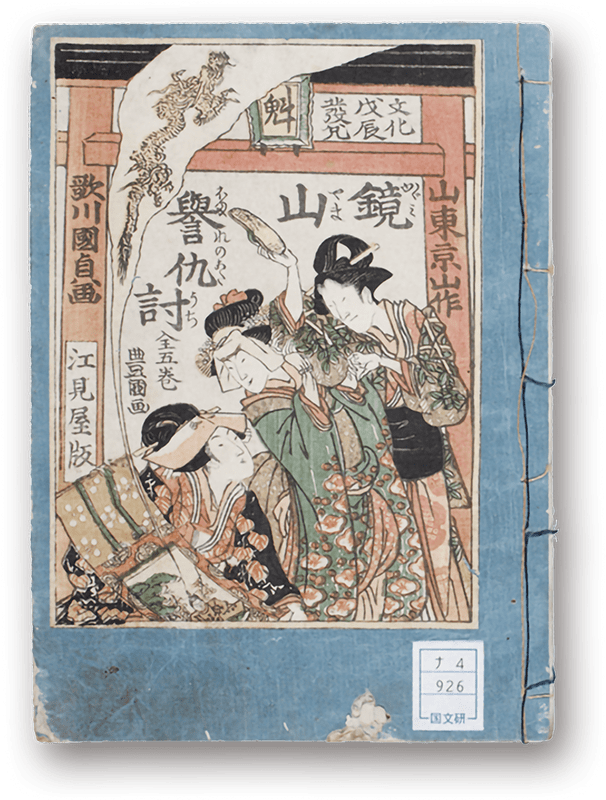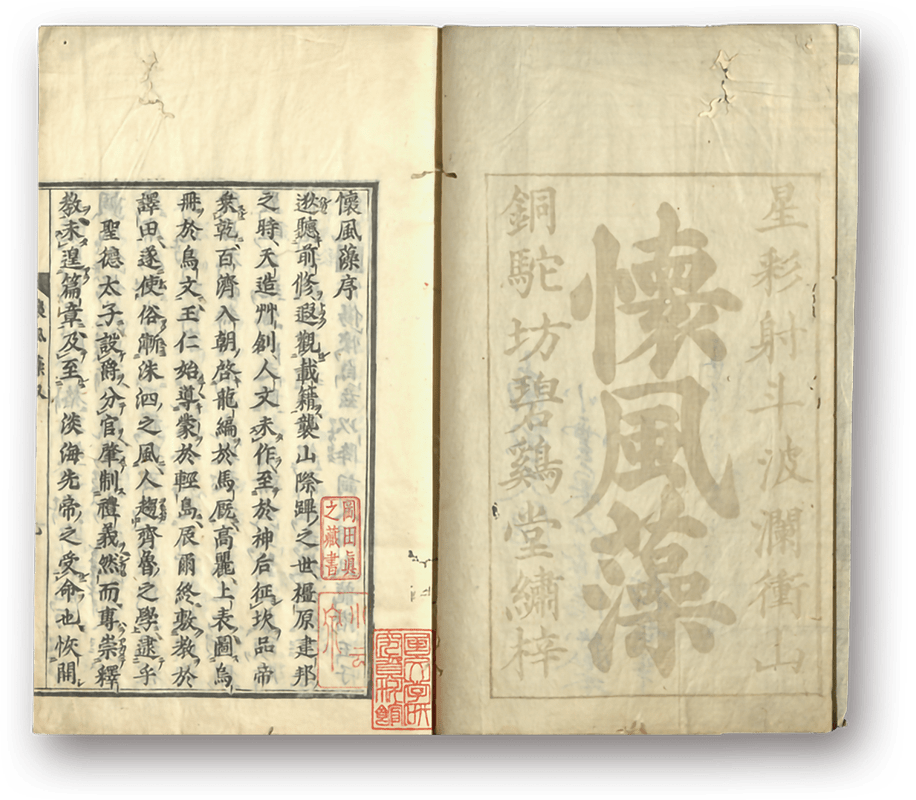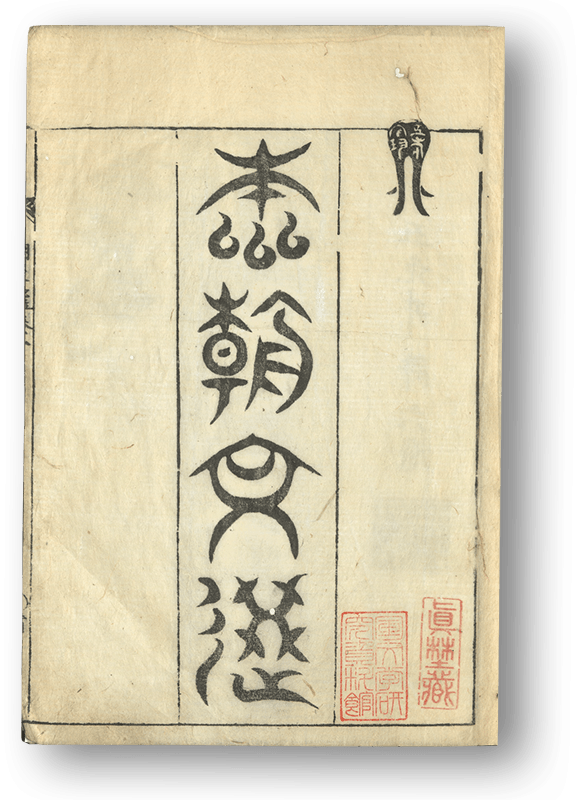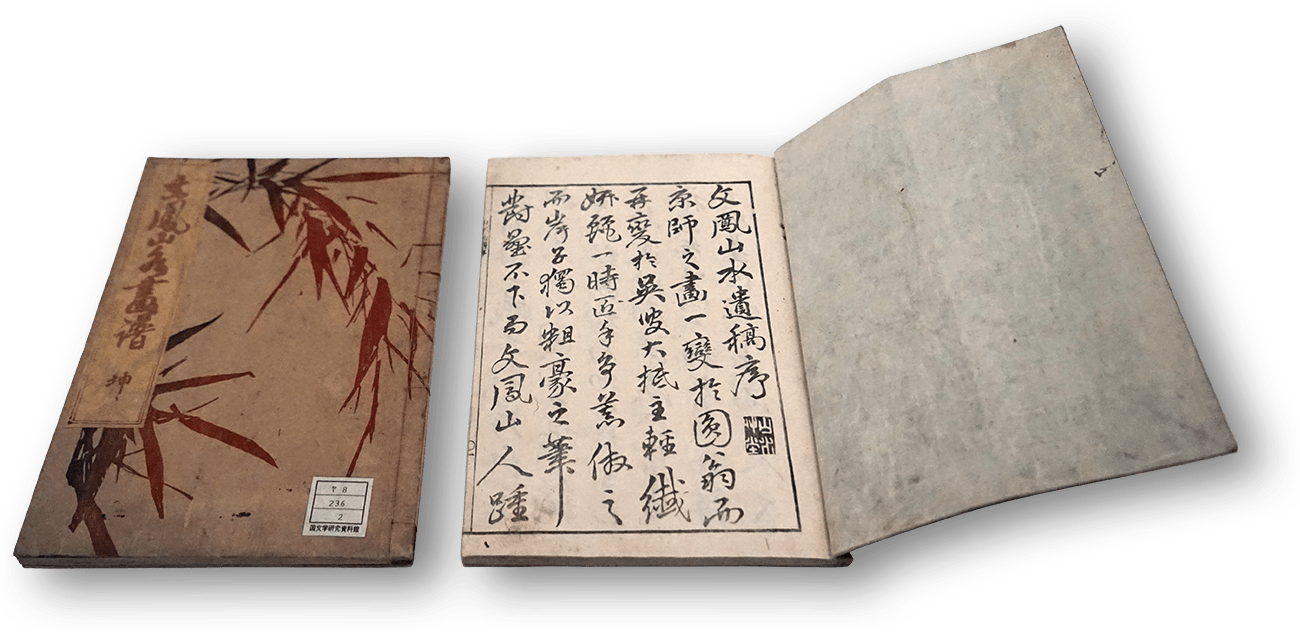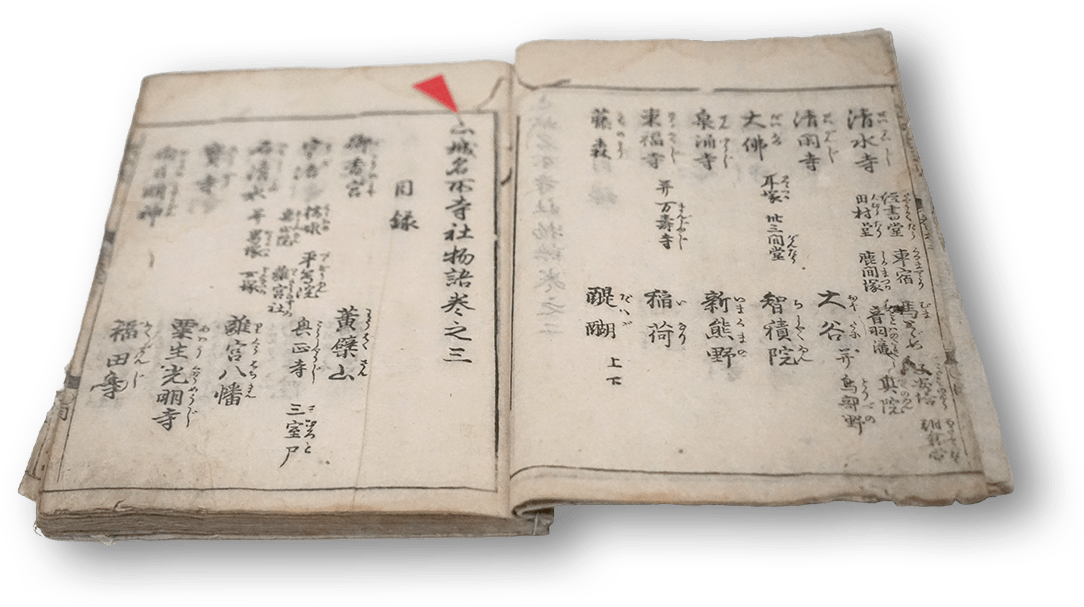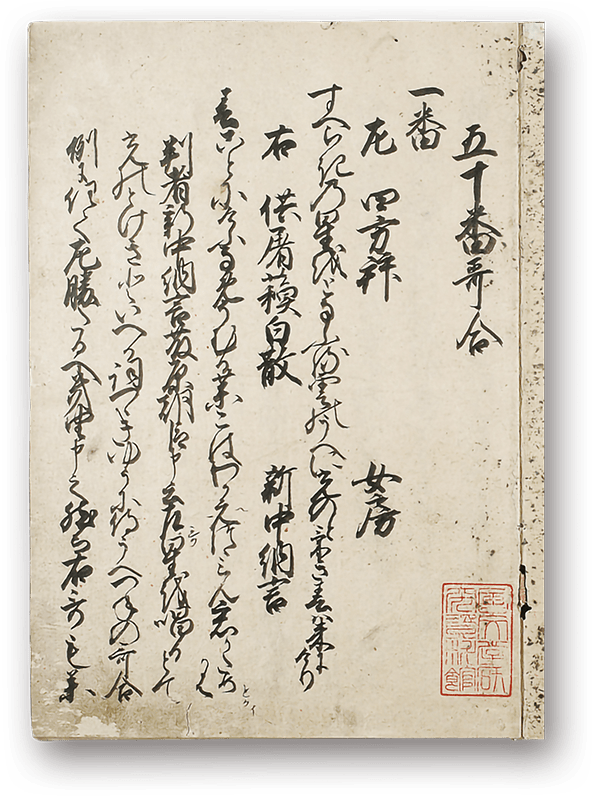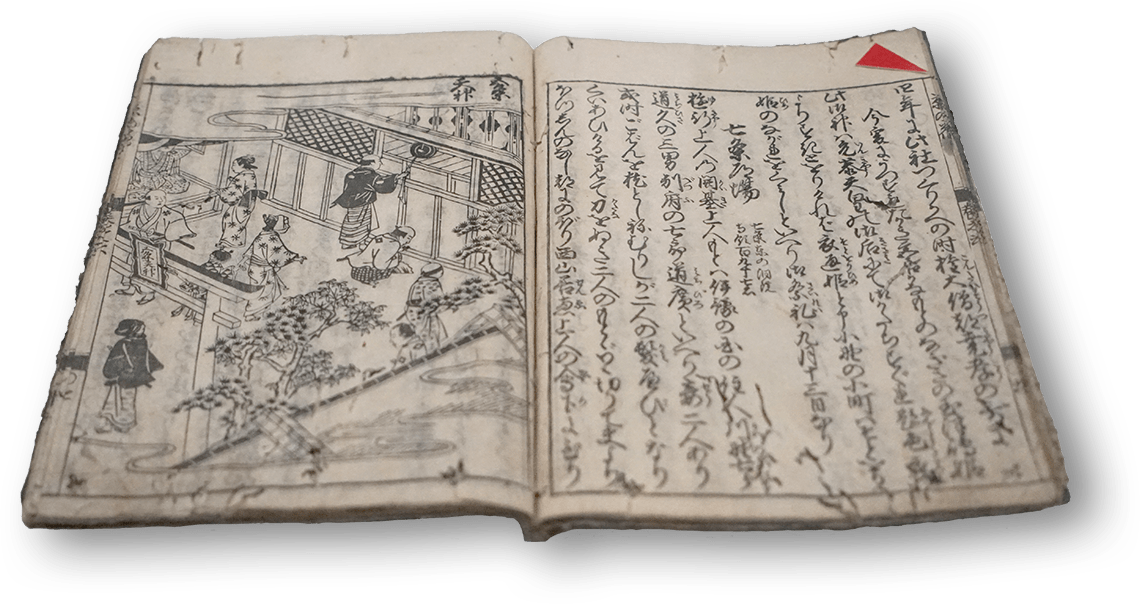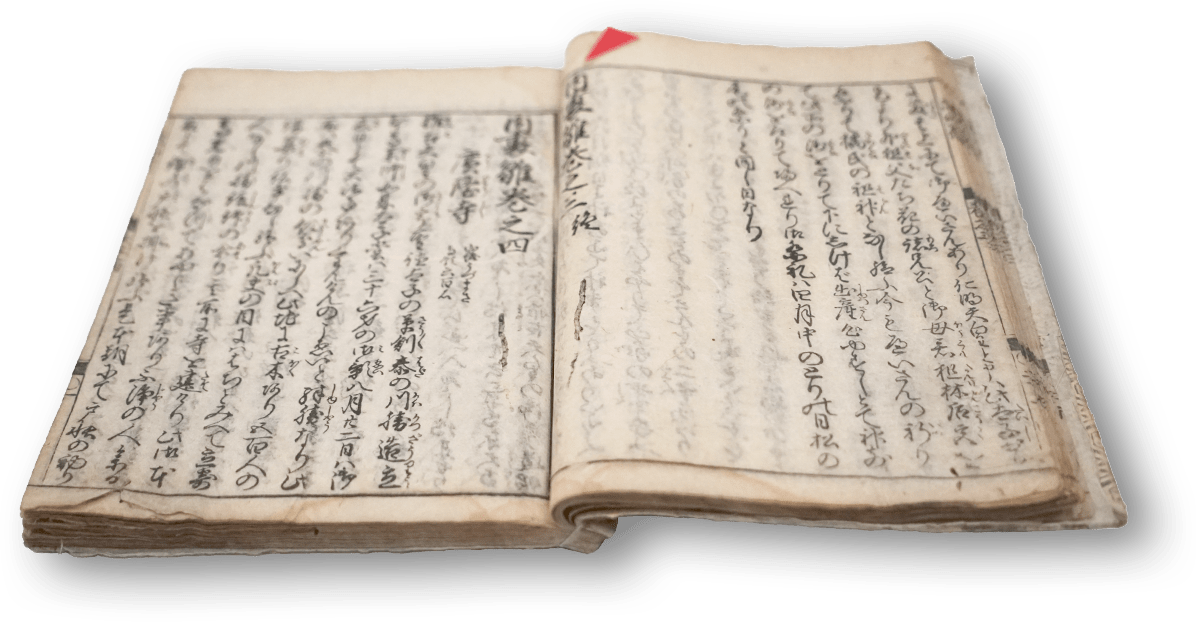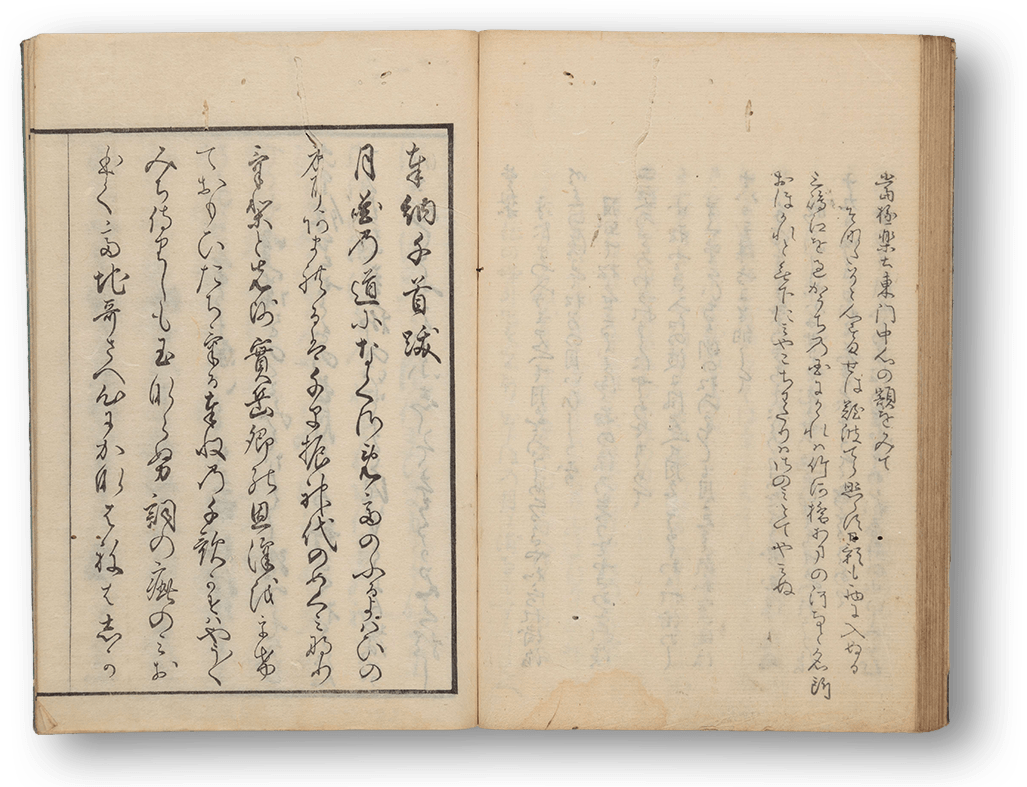書名(題記)
和書の多くには、書名(題記)が記載されています。それらは表紙にあるもの(外題)と、本の内部にあるもの(内題)に大別され、内題はその位置によってさらに区別されます。
外題
表紙にある書名を外題と言います。これに対し、本の内部にある書名が内題です。外題は、題簽を用いる場合と、表紙に直接記載する場合があります。
外題
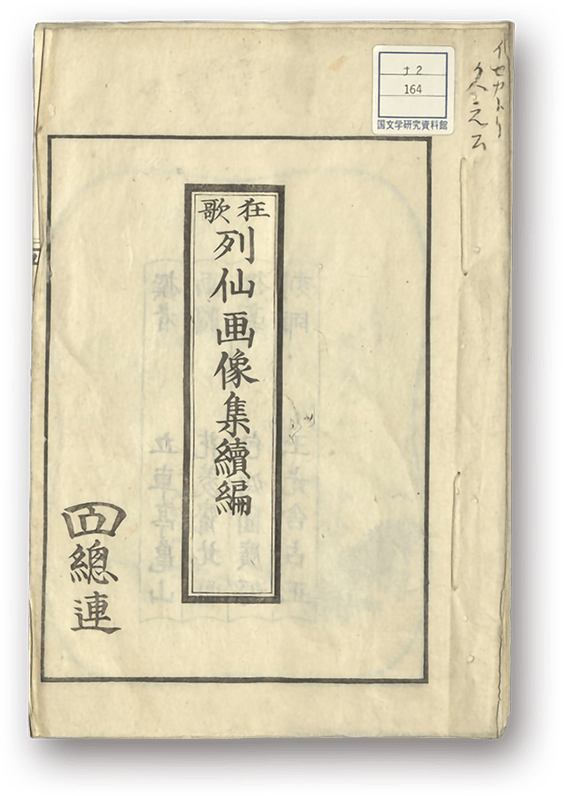
狂歌列仙画像集続編
刷り外題
表紙に直接印刷された外題を、刷り外題と言う。文字だけのものと、題簽の形に枠で囲んだものがある。丁数の少ない、簡素な本によく用いられた。