奥書と識語
写本において、末尾に書写の年月日や書写者の名などを記したものが奥書で、写本に特有のものです。識語は、所蔵者などがその本や著作について書き入れた言葉で、写本にも版本にもあります。
奥書
奥書
写本を書写した人が、年月日や名前、書写の事情などを末尾に記したものです。本奥書と書写奥書の別があります(Ⅳの「本奥書と書写奥書」を参照してください)。
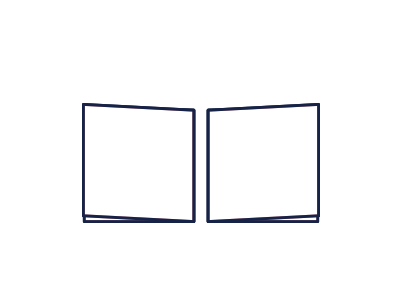 loading...
loading...写本において、末尾に書写の年月日や書写者の名などを記したものが奥書で、写本に特有のものです。識語は、所蔵者などがその本や著作について書き入れた言葉で、写本にも版本にもあります。
奥書
写本を書写した人が、年月日や名前、書写の事情などを末尾に記したものです。本奥書と書写奥書の別があります(Ⅳの「本奥書と書写奥書」を参照してください)。