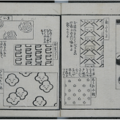『播磨屋中井家日記』
(はりまやなかいけにっき)
国文学研究資料館の歴史資料のなかには、江戸金吹町(現在の日本銀行本店付近)の両替商である播磨屋中井家の業務日記がある。手代(上級の奉公人)数人が交代で書いていたもので、安永8年(1779)から明治30年(1897)までの119年間にわたって83冊を所蔵している。この膨大な日記のなかから今回は安政5年(1858)のコレラ流行について紹介したい。

江戸では7月下旬から流行が始まっていたが、それが中井家日記に現れるのは8月8日に記された3人の死亡記事からである。そのうちの1つだけ引用すると、「室町市大夫妻しま義昨夕より俄に流行病にて苦痛これ有り、今八日酉中刻頃相果て候段届け出候」とある。この女性は7日の夕方に発症して8日の午後6時ごろに亡くなっている。発症から死亡まで約24時間という短さはコレラの特徴である。なお、死亡記事が記載されるのは、取引先や出入の商人・職人やその家族が亡くなると弔問したり香典を出したりする必要が業務上あるためである。
8月14日は彼岸入りであるため、中井家一同は菩提寺である浄見寺に参詣した。その時の様子は「このところ流行の病人が出たためお寺は人が少ない。しかし流行病のため葬式が多く混雑している。行く途中に(たくさんの)葬列に行き会った。言語に絶する」というものであった。この日にも2人の死亡が記録され、この2人については手代が葬式に参列している。ところが、8月27日に死亡が記載された3人については、「但し、いずれも此節柄の義につき御名代罷り出で申さず候」と手代が当主の代理として葬式に参列することを取りやめている。この時期の江戸は、死者数が町人地だけで1日あたり連日400人から600人とコレラが猖獗を極めていた時期である。「外出自粛」の発想があったのだろうか。
一方、8月25日には丸亀藩への融資の返済期限延長手続きを行った。同27日には庄内藩へ融資した2000両のうち1000両が利子20両とともに返済された。コレラ流行のなかでも播磨屋中井家は業務を淡々と継続していたのである。
(教授 渡辺浩一)
読売新聞多摩版2020年6月17日掲載記事より