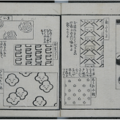『大黒舞』
(だいこくまい)
室町時代から江戸時代前期、西暦でいえば14世紀から17世紀にかけて、御伽草子(室町物語)と呼ばれる短編物語が流行し、400種を超える作品が誕生した。多くは美しい挿絵入りの絵巻や絵本に仕立てられている。とくに17世紀には、絵草紙屋で手書きの豪華な絵入り写本が量産されたが、作者や絵師はよく分かっていない。
『大黒舞』も17世紀の豪華絵巻で、濃彩の挿絵に金箔が贅沢にあしらわれている。物語は福神信仰と立身出世への憧れを背景に、正月に舞われる「大黒舞」などの芸能も取り入れて華やかに展開する。

主人公は吉野の里に住む大悦の助。貧乏な彼は清水観音から藁しべを授かり、それを梨、衣、馬、黄金と次々に交換して裕福になり、親孝行を尽くす。ここには、あの「藁しべ長者」の話が活用されている。
物語の後半ではいよいよ福の神が登場、まずは主人公の孝心を愛でた大黒が現れて宝物を授け、邪鬼祓いの豆まきを伝授する。そこへ恵比須も合流して酒宴となり、歌舞を楽しみ、ついには大悦の助を行司役に福の神が相撲の勝負。 挿絵では大黒に仕える鼠や、恵比須に仕える海のものも固唾を呑んで見守る。頭に貝を頂く姿は『百鬼夜行絵巻』などにも見え、人ならざるものの定型表現であった。
さて、折しも盗賊が来襲するが、福の神が討ち果たす。噂は朝廷にまで届き、大悦の助は福の神に見込まれた果報者として昇殿を許され、中納言の姫と結婚して栄華を極め、大黒は喜んで舞い歌ったと物語は結ばれる。
現在、『大黒舞』は10本あまりの作例が知られている。ほとんどは大型の絵巻(巻物)で、絵本(冊子)も手の込んだ装丁であるから、それなりに身分のある富裕層が正月のめでたい読み初めに用い、嫁入り道具としても注文制作したのであろう。実際、名古屋の蓬左文庫が所蔵する『大黒舞』は、尾張第6代藩主の奥方、安己君の愛蔵本であった。
御伽草子には、ほかにも『文正草子』『弥兵衛鼠』『さざれ石』『不老不死』など、立身出世や福徳の獲得、不老長寿を主題とした作品がたくさんある。人々はめでたづくしの物語を所有し、その書物を見る行為そのものに、幸福を招き寄せる力を信じたのである。
なお、『大黒舞』には、デジタル画像や展示で出会える絵巻がある(国会図書館、もりおか歴史文化館、島根県立古代出雲歴史博物館ほか)。比べてみるのも楽しい。
(教授 齋藤真麻理)
読売新聞多摩版2020年7月22日掲載記事より