対談 人文知コミュニケーター×古典インタプリタ
古典との出合いを提供するために
2022年12月22日(木) 於・国文学研究資料館
古典インタプリタとして、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)、トランスレーター・イン・レジデンス(TIR)に伴走している黄特任助教が、ワークショップの講師、参加者など様々な立場から「ないじぇる芸術共創ラボ」に関わってきた粂特任助教(人文知コミュニケーター 1)と、ないじぇるの活動で得た気づきと今後の展開について語り合いました。

―目次―
●古典インタプリタと人文知コミュニケーターとは
よろしくお願いします。

ご存知のことと思いますが、古典インタプリタというのは、クリエーターと研究者との間のいわゆる橋渡しの役として、外に向けて、また社会に向けて発信する古典知のナビゲーター、一種のコンシェルジュのような存在です。研究と社会を繋げるという点で、人文知コミュニケーターと似ているところがあると思うのですが、人文知コミュニケーターは具体的にどのようなお仕事なのか、教えていただけますか。
人文知コミュニケーターの定義というのは、私がこの仕事に携わる時は、「研究現場と一般社会を繋ぐための研究者」と教えられ、仕事を始めたのですけれども、六機関の人文知コミュニケーターは所属機関によって、それぞれの組織の任務が違います。
私の場合は、社会連携事業部に配属されて、大きな仕事としては展示室の仕事と、それに付随するギャラリートーク、一般講座のワークショップ、あとは「くずし字講座」などが主な仕事になっています。その時々で来た依頼を、広報担当職員の方と一緒にこなす、という風にしています。ですので、前に立ってしゃべる、というだけが仕事ではなく、取材対応もしますし、司会もしますし、結構なんでもやります(笑)。ただ、人文知コミュニケーターとして自分の中で、大きな成果であったと思うのが、入口先生と一緒にやってきた「和本づくり」のワークショップです。地域の図書館とか、ないじぇるのなかでも、一つのパーツとしてやったことがあります。
ワークショップで、谷原さんと一緒に絵巻をつくりましたね。
そうですね。絵巻のほかに、入口先生が考案された、裂帖装を針と糸でつくるという大人向けのワークショップも行っています。このようなワークショップを入口先生とずっと一緒に行脚してきました(笑)。
年に何回くらい開催していますか。
コロナ前は、一年に1~2回のペースで開催していましたが、コロナ以降は全て中止になり、今年の10月に、富山県で再び開催する予定があります。
参加対象は、主に大人向けで、図書館などで開催されているのですか。

依頼内容に沿って調整しています。こちらの絵巻をつくった時は、立川市の西砂図書館で、小学生から中学生までを対象としたのですが、妹さんや弟さんと一緒に参加される方もいて、実際にはもう少し小さい子も参加していました。
●イベントを通して気づいたこと
ワークショップなどのイベントで印象的なことがありましたか。
そうですね。時間をとてもオーバーしてしまった事がありました。自分では「これくらいでできるであろう」と思っていましたが、はさみやのりを使う作業は、小さいお子さんには親御さんが一緒に横でやってくださっても、思っている以上に時間がかかることなのだ、といった発見もありました。最初に講義のような少し真面目なお話をするのですが、お子さんは本当に純粋で、「飽きてる」ということを身体全体で表すので、はっきりとわかります(笑)。そのような現場の気づきを重ねて、ワークショップを組立直していきました。
もう一つの大きな成果は、日本科学未来館の科学コミュニケーターと一緒に行った、「国文学研究資料館×日本科学未来館 和書からさぐる!お江戸のサイエンスとライブラリー」2)というイベントがあります。これを計画している時はコロナ前だったので、対面で本を触りながら行う予定でしたが、コロナの影響でオンラインになりました。初期頃のオンライン講義でしたから、模索の連続で大変だった記憶があります。
イベントで古典籍に触れて、参加者からどのような感想がありましたか。
印象に残っているのは、読売新聞ジュニアプレスの子供記者さんが国文研に取材に来た時、その中の一人が、立川市の図書館で開催した和本づくりのワークショップに親子で参加したことをきっかけに国文学に興味を持ってくれて、お手紙まで送ってくれたことです。とても嬉しかったです。子供の頃にこのような体験をした子が、その後どういう風にして高校生、大学生と成長していくのか、記録をとるなりして追いかけてみたいね、という話を事務の方ともその後お話をしました。
このような記録を取ることができれば、とても大事な資料になりますね。
●クリエーターとの交流で感じたこと
粂さんはワークショップの講師として、また、イベントの参加者として、様々な立場でないじぇるに関わってくださいましたね。例えば、AIRの谷原菜摘子さんとワークショップを行いましたが、谷原さんはないじぇるに参加された最初から絵巻に大変ご興味があり、ワークショップで実際に古典籍の実物を鑑賞したり、ご自身で絵巻を巻いたりして、とても貴重な経験になったと仰いました。ワークショップで谷原さんとの交流を通して、どのように感じられましたか。
黄さんからワークショップで谷原さんとお話をしてほしいと依頼があったとき、谷原さんが、岩佐又兵衛の絵巻がお好きとうかがっていたので、自分の専門分野である語り物のお話ができることが大変嬉しかったです。同時に、いわゆる美術史の先生方が注目する名作の絵巻ではない、庶民が愛したお伽草子の絵巻もあるんですよ、ということも紹介したいと思って、関連する絵巻や奈良絵本をご案内しました。
これらの作品には、例えば、主君のために自分の身を犠牲にする、自分の子供を殺してしまう、夫以外の男性に横恋慕された女性が逃げるといった現代の小説にもあるような人間ドラマが描かれています。私がこの作品群に魅力を感じるのもそういう多様性です。これらの作品は現代社会においても、間違いなく読み応えがあるものですし、もちろん大学の教育現場やそれ以外でも、教材に十分なり得るものだと思っています。ただ教科書には全然載らないのですよね。
そういう物語に谷原さんは、とても興味を持っています。粂さんとのワークショップもそうですし、恋田先生とのワークショップでも奈良絵本・絵巻を紹介してくださいました。谷原さんはこれらの物語はもちろんのこと、奈良絵本・絵巻の構図についても大変関心がありました。自分の創作と共通するところがあると、驚かれていました。2022年12月18日に行った「ないじぇるクリエイティブ会議」(以下、クリエイティブ会議)5)で谷原さんは、奈良絵本の絵には「上質なゆるさ」が見られると仰いました。この言葉から、古典の持つおおらかさ、良い意味でのいい加減さを改めて考えさせられたと、渡部泰明館長はコメントされましたが、奈良絵本・絵巻が持つゆるさを「上質的」と見る、この捉え方はいかがですか。
とても良い言葉だと思いました。似た言葉として、すでに専門用語に近い形で、稚拙美や素朴絵いった言葉があります。奈良絵本の初期の作品群のなかには、土人形のようなコロコロした人間や、正確な遠近法とはかけ離れたゴツゴツとした建物が描かれた絵巻がありますが、私はそういうものをすごく愛しく感じます。そのような作品世界をもっとよい良い言葉で表現していただけたなと、とても嬉しく思いました。

谷原さんの作品は空間が破綻した奇妙な構図で描かれたものが多いですが、ご本人も奈良絵本や絵巻をご覧になって、古典のなかにも自分の作品と通じているものがあり、そこには日本人としてのDNAを感じたと話されたことがあります。古典とのつながりを谷原さんは「接続されている」という言葉で表現されたのですが、そういうお話をうかがって、古典は本当に生きていると思いました。
それを洋画、油絵で描かれるというのが面白いですよね。日本画で再創造するのではなくて、洋画というのが新しいところがあります。
粂さんは片渕須直監督とのワークショップにも参加されましたよね。研究者も驚くような、その映画づくりの緻密な資料収集と考証のお話をお聞きになって、いかがですか。
他の先生方がおっしゃるとおり、私も講義をうかがっているような感覚に襲われて。
まずその資料の膨大さに圧倒されますよね。

膨大な資料に圧倒されるだけではなく、資料を一つずつ拾いあげて、こうだったのではないか、と思ってこうしたのだと、その推敲、思考の過程を教えてくださいましたよね。最初はこういう風に迷ったのだけれども、色々と調べていくうちに、こうこうこういう事に気がついて、結局この絵を描いたなど、その過程を全部披露してくださることに、私は惹かれました。映画を創られる時、このように想像を束ねて絵にするのだと、完成したアニメーション作品が見たくなるお話でした。
私自身も、各地に伝わる物語や地域伝承に関する論文を書くことが多いのですが、論文を書くために現地で資料を調査したり、フィールドワークしたり、また土地の人に聞き取りをしたりと、いくつもの研究方法を組み合わせて論文を書き上げるので、アニメーション創作の現場でも、同じような方法がとらえていることに、驚きを感じました。
実は、クリエイティブ会議でも少しお話が出ましたが、AIR、TIRの方々はそれぞれテーマもジャンルも全く異なるのですが、それぞれの方がやられている事が色々なところで研究と繋がっていたり、古典籍とも思いがけないところで繋がったりして、私もとても驚きました。
●現場でこそ拾える生の声
人文知コミュニケーターのお仕事のなかでも、広く社会に向けて成果を発信することが求められていると思いますが、ないじぇるでは社会への還元として、色々なイベントを開催しています。例えば、今年は2回のないじぇるアートトーク、ないじぇるトランスレーショントークと、参加型イベントを対面で開催し、オンラインではクリエイティブ会議、渡部館長の講演会6)と第9回一冊対談集7)の動画配信を行いました。
イベントを行ってまず感じたのが、イベントを通してクリエーターと研究者の生の声を伝える大切さです。例えば、渡部館長の講演会「源実朝の歌はなぜ心を打つのか」はYouTubeライブ配信で開催しましたが、コメント欄で視聴者のコメントをたくさんいただきました。和歌の技法や、この和歌はどのような心境で詠まれたのかなど、大変細かな質問や感想があり、また、「大河ドラマの時、この話を聞いたらもっと楽しめるのではないか」など、和歌研究の手法と成果に触れることで古典の楽しみ方が広がる可能性を示唆するようなコメントもあり、多くの気づきがありました。人文知コミュニケーター企画のイベントで、参加者の生の声で印象的なものがありましたか。
2019年11月、立川商工会議所、多摩信用金庫、株式会社JTB 東京多摩支店の地域社会の企業と国文研が協力して行う地域資源発掘型実証プログラムの一つとして、「古典の森モニターツアー 江戸スウィーツお菓子教室と和本づくり体験」8)というイベントを行いました。ツアーの目玉は立川市の国際製菓専門学校で、当館所蔵の江戸時代の料理のレシピ本を使い、国際製菓専門学校の先生の監修の下、江戸のスイーツを再現するというお菓子教室です。一緒にお菓子を作ったツアー参加者の方から、自分のレシピを開発する時に、新日本古典籍総合データベース9)で公開されている古典籍を参考にしているとうかがいました。レシピ開発の資料として、古典籍の画像を閲覧している方がいるのだと初めて知り、現場に出てこそ、うかがえる意見という点で、一番印象に残っています。

古典が仕事にインスピレーションを与えることがあると、他のイベントでも聞いたことがあります。2022年9月にAIRの染谷聡さんとともに、古典籍の画像をコラージュした封筒をデザインし、それを漆でコーティングする公開ワークショップ10)を行いました。古典籍に触れることで普段使っていない感覚が呼び起され、仕事のアイデアがどんどん湧いてきたことを実感したという参加者のコメントがありました。料理やデザインを生み出す現場で古典籍が多様な形で使えることをお聞きして、古典が生きているのだと改めて知らされました。
そういう気づきは人文知コミュニケーターも大事だと言われています。自分たちが発信するだけではなく、現場の声を拾って、それをまた自分たちの研究に活かす、ということがとても大事だと言われていますので、とてもよい実例だと思いました。
●多言語化を通して日本文化の魅力を伝えること
2021年からTIRを務めてくださった翻訳家の毛丹青さんは中国語圏に向けて、『夢酔独言』という勝海舟の父・勝小吉の自伝を翻訳しています。毛さんはこの書物から当時の日本文化だけにとどまらない精神性を感じ、その越境性と現代性に着目しているところも大変興味深いですが、『夢酔独言』という書物は、アメリカで学部生向けの歴史の授業の副読本として人気があり、また、中国の方が英語版でこの本を読んで小吉の生き方に魅力を感じたことがあると知り、翻訳を通してその国の文学・文化を伝えることの大事さを実感しました。日本の古典を多言語化するという点について何かお考えがありますか。
そうですね。黄さんの母語が中国語で、日本語と中国語の架け橋となり、様々なやりとりができるので、そういう新たな表現が生まれてきたのだと思います。
人文知コミュニケーターの中にも、韓国、中国を現場にして研究活動をされている方や、両国語を話せたり、自分の国との比較で日本について研究している方もいます。やはり言語の問題だけではなく、研究方法から価値観の違いなど、色々なものに派生して広がる問題だと思っています。
他の国の文化を知る、その最初のステップ、ということですよね。
はい、そのきっかけ作りになればと思います。
●ないじぇる芸術共創ラボの今後について
ないじぇるに限らず、全ての活動についてそうですが、どういう層に向けて発信するのかはとても大事だと思います。イベントを行う時、集客で苦労していることが結構あります。どういう層に向けて発信すればよいのかという点について、人文知コミュニケーターのお仕事のなかで感じたことやご苦労など、アドバイスになるようなことがありましたら、教えていただきたいと思います。
まずは仕事の依頼があった時に、「参加者層」というのでしょうか、特に気にしています。どのような年齢層なのか、例えば共催の場合、共催先の図書館や美術館の方などが、どういう目的でどういう方に向けて実施してほしいのか、ということをうかがいますし、自分たちで集客を行う場合も、同じように気にします。なぜかと言えば、社会に向けて研究成果を届けるために行っているわけですが、その前に対象と目的、なぜそれを行うのか、その対象と、なぜそれをしたいのかという目的を明確にしておかないと、上手く届かないことが多い、というのがこれ迄の経験から学びました。それに、研究、共同利用、共同研究、教育にフィードバックをする、ということをしているのですが、ただ漠然と一般社会に還元しますというのではなく、私の場合は、当座の目標としては多摩地域という社会と連携して、当館がある立川における長期の利用者層を地域的に開拓したい、と思っています。どうしても、大学生や研究者という国文学を専門とする利用者にしか来てもらえないので、もう少し地域のなかでの学問の場として利用してもらえないかと思っています。
おっしゃるとおりですね。ないじぇるでも感じていることですが、やはり国文研の存在や、古典籍の魅力を広く一般社会に向けて発信する時、最初に反応してくださるのが、もともと国文研を知っている方、あるいは、もともと古典に興味を持っている方が多いです。どうすればより多様な参加者を開拓できるのか、ということを考えますと、ないじぇるではクリエーターの方々のファンの方にはまず届いていることを実感しています。片渕さんのイベント13)でお越しいただいた方から、国文研はこういうことをやっているのだ、などのフィードバックがあったりします。また、谷原さんは江戸時代の小説『西山物語』を踏まえて絵画作品を創作されています14)が、「ハロウィーンに『西山物語』を読みたい」とtwitterに投稿したところ、「『西山物語』ってなんだ?」と興味を持ってくださり、本を購入して読んだという方もいらっしゃいました。さらに、日本の若い人は古典に興味がない、「古典離れ」、「古典嫌い」などと言われていますが、実際にお話をうかがいますと、古典は難しくて読まない、まではあるのですが、古典が嫌いという方はあまりいらっしゃらないのではないか、と感じています。古典の魅力をいかにして届けられるのかが、今後の課題となると思います
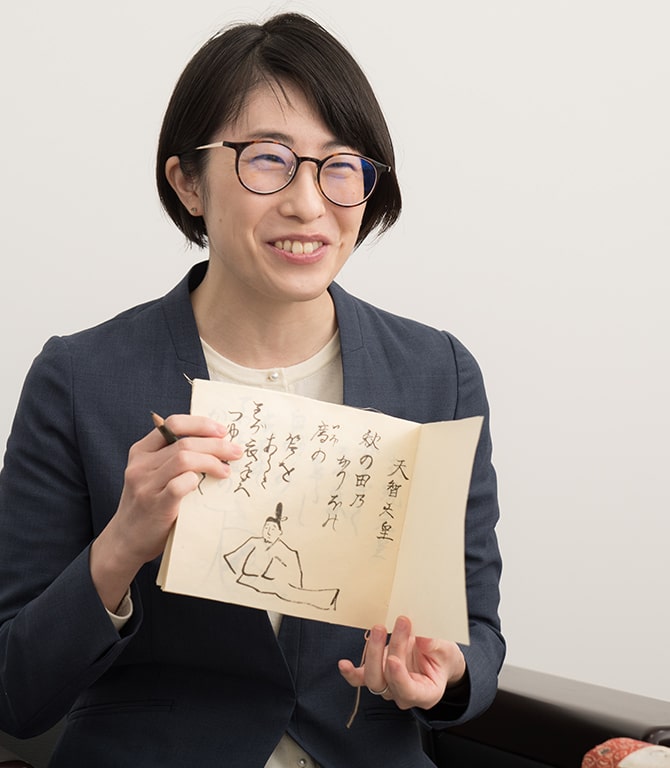
古典が嫌いな人にどうアプローチするのかについて、私は古典や国文学というのは、世界を見渡すための一つの窓だと思ってこの仕事をしています。その窓から色々な世界が見えてきて、そのきっかけを一つ提供するだけでよいのではないか、その上で一人ひとりの生活に、少しでも潤いが提供できたり、視野が広がればよいと思っています。私自身もそうやって、この世界に飛び込んだ一人です。小学生の時に絵巻の謎めいた形に惹かれ、夏休みの宿題を絵巻の形にして提出したことがあります。そんな小学生の私のように、和書の表紙の美しい模様とか、和書の内容ではなく、そういうものに魅了される人がいてもよいですし、それぞれの入口、窓があってもよいと思います。そこから、やがて奥深い古典の森に踏み込んで、意外な形で熱中する人が出てくるかもしれないと思いますので、人文知コミュニケーターとしては、古典に興味を抱く人たちに対して興味、関心の種を蒔くような仕事をしていきたいと思っています。
●古典インタプリタとして感じたこと
これまで古典インタプリタとして活動をされて、ご自身にとってどういうところがよかったなど、感想がありますか。
クリエイティブ会議でも議論になっていたのですが、一般的に古典といえば『源氏物語』のような、いわば「大古典」のイメージが強いですが、粂さんのお話のように、研究者自身も最初は小さな入り口から入った人もいますね。
研究者が持っていない視点、あるいは想像もつかないような観点で古典を見直すことの大切さと楽しさは、私にとってクリエーターたちとの交流で得たものの一つです。谷原さんとのワークショップで国文研創立50周年の記念展示を解説しましたが、谷原さんは「今年記念を迎える本」のコーナーで『方丈記』15)をご覧になって、「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という水のイメージが、美女が水になって流れ去っていくという『長谷雄草紙』の名場面につながっていると感じられ、「無常」という作品で人間が水になる場面を描きました。私が全く思いつかない発想で古典籍が創作のインスピレーションになることに大変驚きましたし、感動しました。
研究者としてどんどん固くなってきた脳みそを、柔らかくしてくれますね。

染谷さんが、「(ワークショップでは)研究者から言葉をもらっていく」と仰っていました。曖昧だった概念が、研究者との対話でクリアになっていくということですが、逆に私はクリエーターの方から感性をもらって、自分の研究に対する熱意がよみがえったような気がします。
私が定時制高校で教えていて思ったのが、人に分かりやすく教えようとすると、自分もどんどん常識にとらわれなくなっていくという感覚があります。不思議なのですが、その時に自分のなかで満足の行く論文が書けたのです。その時の感覚がなぜなのか分からないままですが、人に分かりやすく話そうとすると、自分も根底のところから、なんでだろうと一緒に考えなくてはいけないので、そこから新しいテーマができて、取り組んでいるうちに、普段気づかないことに気づいたり、思いつかない発想ができたりします。
一つ私自身の反省点でもありますが、実はワークショップで自分の研究について余り話しませんでした。その一方、専門以外の古典籍をたくさん選んで、クリエーターの方々の関心に合わせて館内・館外の多くの先生方にご協力を仰いでワークショップでお話しいただきました。できるだけ広く古典と出会う可能性を提供したい、という気持ちがありますね。クリエーターの方々が見たいものだけでなく、その周辺のものとか、一見関係のないものも提供して、思いがけないところで面白い発見が生まれればと思って「実験」しています。
ないじぇるでは、クリエーターと研究者との双方向のコミュニケーションを通して、互いの知見や感性が交差する良い循環を作っていくことがとても大事だと考えています。研究者からクリエーターの方々に、創作のインスピレーションとして、「大古典」はもちろんのこと、知られざる「小古典」を含めてご案内し、研究者もクリエーターの方々から、豊かな感性や普段気づかない古典の魅力、楽しみ方の示唆を得るというように、良い循環をどんどん作っていきたいと思います。
- 1) 人文知コミュニケーターは、社会とのコミュニケーションを通じて、研究成果をわかりやすく発信し、そこから研究課題を発見し、研究を活性化する新しいタイプの研究者です。
https://www.nihu.jp/ja/training/jinbunchi/about - 2) 「国文学研究資料館×日本科学未来館 和書からさぐる!お江戸のサイエンスとライブラリー」の詳細はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/news/2020/07/post-130.html - 3) 当館企画展示「戦国武将たちの愛した文学―幸若舞曲―」の詳細はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2020/11/2020-kikakutenji.html - 4) 当館特別展示「創立50周年記念展示 こくぶんけん〈推し〉の一冊」の詳細はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/kokubunken_50th/exhibition.html - 5) 「ないじぇるクリエイティブ会議」の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/creative_mtg/index.html - 6) 渡部館長の講演会の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/sanetomo/index.html - 7) 第9回一冊対談集の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/kyosei/index.html - 8) 「古典の森モニターツアー」の詳細はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/activity/plat/koten-no-mori.html - 9) 新日本古典籍総合データベースは当館で構築している唯一の日本古典籍ポータルサイト。
https://kotenseki.nijl.ac.jp/ - 10) 公開ワークショップ「ものがたりを保存する~漆でつくる時間封筒(タイムカプセル)~」の詳細はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/urushi_ws/index.html - 11)鼎談「「徳川の平和」が生み出した奇想天外な武士・勝小吉―なぜ今、『夢酔独言』なのか?―」の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/musuidokugen/index.html
ないじぇるトランスレーショントーク 鼎談「江戸の境界を生きた人と書物の力──勝小吉『夢酔独言』から扉をひらく」の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/musuidokugen2/index.html - 12) トークイベント「鉢中の天 ―五十三次とジオラマの景―」の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/hacchu-no-ten/index.html - 13) ないじぇるアートトーク「『枕草子』に書かれた以上に清少納言や中宮定子を知りたいあなたに」の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/art_talk_katabuchi/index.html
ないじぇるアートトーク2「清少納言たちがそこにいた「空間」を探る」の動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/art_talk_katabuchi2/index.html - 14) 谷原さんと当館木越俊介准教授が『西山物語』について対談した動画はこちらから
https://www.nijl.ac.jp/pages/nijl/event/monogatari/index.html - 15) 谷原さんがインスピレーションを受けた、当館蔵古活字版(嵯峨本)『方丈記』の冒頭部分
https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200016993/viewer/7




今日は、粂さんが人文知コミュニケーターとして、ないじぇる芸術共創ラボ(以下、ないじぇる)のワークショップやイベントなどさまざまな活動に関わられている中で気づいたことについて、色々とお話をおうかがいしたいと思います。