パブリケーション
目次
Online Journal “Studies in Japanese Literature and Culture”
英文オンライン・ジャーナル『Studies in Japanese Literature and Culture(SJLC)』は、歴史的典籍NW事業国際共同研究「境界をめぐる文学―知のプラットフォーム構築をめざして―」の研究成果発信の一環として2018年7月に創刊し、Volume 1からVolume 5にかけて古典籍共同研究事業センターより刊行しました。
Volume 6以降は、担当部署を情報事業センター国際連携部に移し、日本文学及び日本語の歴史的典籍に関連する幅広い分野の論文を掲載しています。
-

Studies in Japanese Literature and Culture
Volume 1: BORDERS
-

Studies in Japanese Literature and Culture
Volume 2: BORDERS
-

Studies in Japanese Literature and Culture
Volume 3: INTERACTION OF KNOWLEDGE
-
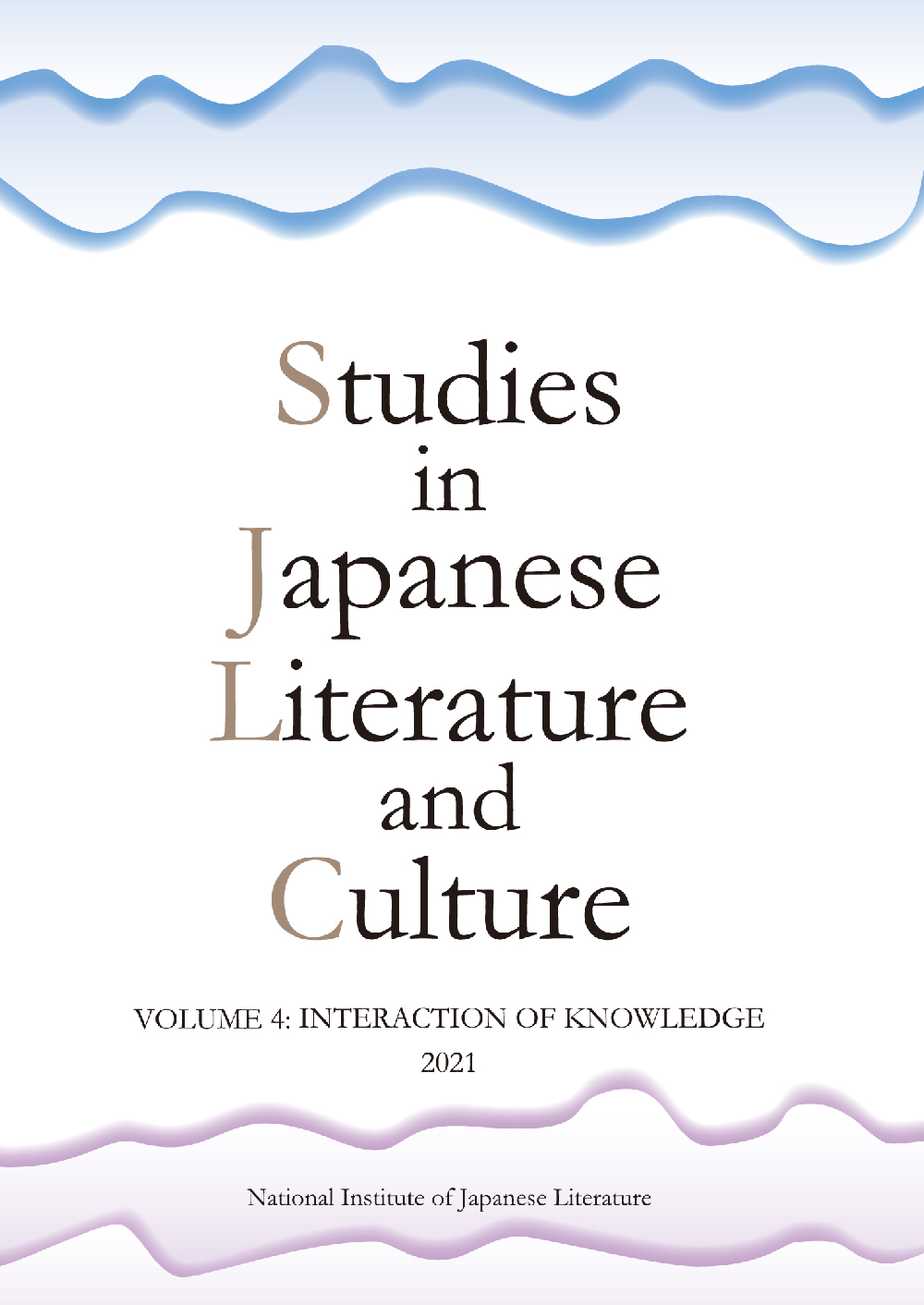
Studies in Japanese Literature and Culture
Volume 4: INTERACTION OF KNOWLEDGE 2021
-

Studies in Japanese Literature and Culture
Volume 5 (2022)
論文
NW構築計画において実施された共同研究成果等を用いて執筆された論文のリストを公開しています。下記リンク先から一覧データをご覧いただけます。
| 論文標題 | 著者名 | 出版社名 | 署名/雑誌名 | 巻 | 発行年 | 査読 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大英博物館特別展「Shunga: sex and pleasure in Japanese art(春画―日本美術における性とたのしみ)」開催と国際シンポジウムの報告 | 石上阿希 | 国際浮世絵学会 | 『浮世絵芸術』 | 167号 | 2014 | |
| 明治の科学啓蒙家の苦心 : 「―力」、「―性」の接辞化へ向けて | 陳力衛 | 明治書院 | 『日本語学』 | 第421号 33-3 | 2014 | |
| 十九世紀の絵入メディア : 錦絵の〈填詞〉をめぐって | 髙木元 | 明治書院 | 『國語と國文學』 | 第1095号 92-2 | 2015 | ○ |
| Takebe Katahiro --- a Man of his Times: A Survey of his Life and Mathematical Thought | Tsukane Ogawa | the Mathematical Society of Japan (MSJ) | M. Morimoto and T. Ogawa eds. Proceedings of Takebe Confernece 2014 (in preparation) | 2018 | ||
| 三人の徳川将軍に仕えた暦算家建部賢弘 | 小林龍彦 | 和算研究所 | 『和算研究所紀要』 | No.15 | 2015 | |
| 表白論の射程 | 牧野淳司 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』中世寺社の空間・テクスト・技芸 | 174 | 2014 | |
| 智積院蔵『醍醐祖師聞書』について―意教上人頼賢とその周辺を巡って― | 宇都宮啓吾 | 智山勧学会 | 『智山学報』 | 64 | 2015 | |
| 書評 細川涼一『日本中世の社会と寺社』 | 海津一朗 | 吉川弘文館 | 『日本歴史』 | 792号 | 2014 | ○ |
| 『平家物語』は「軍記」か | 佐伯眞一 | 岩波書店 | 『文学』 | 16-2 | 2015 | |
| 『扶桑略記』陽成天皇紀の方法─〈不戦の軍記〉と漢文伝記と | 大橋直義 | 岩波書店 | 『文学』 | 16-2 | 2015 | |
| 「不磨の大典」としての憲法 | 河島 真 | 京都民科歴史部会 | 『新しい歴史学のために』 | 285号 | 2014 | ○ |
| 読書としての戦争体験―井上光晴「ガダルカナル戦詩集」と戦中派の思想 | 梶尾文武 | 神戸大学文学部国語国文学会 | 『国文論叢』 | 49号 | 2015 | |
| 磐城三春の書肆とその江戸仕入れ | 鈴木俊幸 | 中央大学文学部 | 『紀要 言語・文学・文化』 | 113 | 2014 | |
| 草紙類の流通と広告―甲府二文字屋藤右衛門引札― | 鈴木俊幸 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 2 | 2014 | |
| 『幼学便覧』考―幕末の詩作熱とその行方― | 鈴木俊幸 | 明治書院 | 『國語と國文學』 | 第1088号 91-7 | 2014 | |
| 宮本周安『采真謾筆』-馬場佐十郎、吉雄忠次郎、青地林宗、岩崎灌園らが語る文政7~9年の江戸の蘭学事情 | 吉田忠 | 津山洋学資料館 | 『一滴 : 洋学研究誌』 | 22号 | 2015 | |
| 『夢梅華館日記』翻刻(第二十八~二十九巻) | 陳捷 | 国文学研究資料館 | 『調査研究報告』 | 第35号 | 2015 | |
| 大坂書肆北田清左衛門覚書 付、大江文坡との関わり | 福田安典 | 日本女子大学 | 『日本女子大学大学院文学研究科紀要』 | 21号 | 2015 | |
| 信州松本の貸本商売―穀屋儀七貸本広告と貸本印― | 鈴木俊幸 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 4 | 2015 | |
| 日本古代の火葬―文献史料から見た | 稲田奈津子 | 平凡社 | 『歴史と民俗』 | 31 | 2015 | |
| 宮内庁書陵部所蔵壬生家旧蔵本目録(稿) | 小倉慈司 | 思文閣出版 | 『禁裏・公家文庫研究』田島公編 | 5 | 2015 | |
| 陽明文庫所蔵『勘例 御薬・朝賀・小朝拝』所引弘仁宮内式逸文 | 小倉慈司 | 思文閣出版 | 『禁裏・公家文庫研究』田島公編 | 5 | 2015 | |
| 「弘仁格」からみた返要国規定 | 仁藤敦史 | 塙書房 | 『日本古代の国家と王権・社会』吉村武彦編 | 2014 | ||
| 古記録の裏書について―特に『御堂関白記』自筆本について― | 倉本一宏 | 思文閣出版 | 『日記・古記録の世界』 | 2015 | ||
| 延喜式に見える大炊寮からの食料支給 | 相曽貴志 | 延喜式研究会 | 『延喜式研究』 | 30号 | 2015 | ○ |
| 中世鋳造遺跡からみた鉄鍋生産 | 村木二郎 | 高志書院 | 『考古学と中世史研究』 | 11巻 | 2014 | |
| 信太郡の駅路と伝路 | 堀部 猛 | 茨城県教育委員会 | 『古代東海道と古代の道』茨城県歴史の道調査事業報告書古代編 | 2015 | ||
| 文献史料にみえる古代の道 | 堀部 猛 | 茨城県教育委員会 | 『古代東海道と古代の道』茨城県歴史の道調査事業報告書古代編 | 2015 | ||
| 仏教文献のための構造的なデジタルテクストの記述と活用 | 永崎研宣 | 日本印度学仏教学会 | 『印度學佛教學研究』 | 第63巻 第2号 | 2015 | ○ |
| 大蔵経刊行を通じて考える学術情報流通の将来 | 永崎研宣 | 日本出版学会 | 『日本出版学会会報』 | 138 | 2014 | ○ |
| 人文学にとっての「リンク」の意義 SAT大蔵経データベースを手がかりとして | 永崎 研宣、Paul Hackett、苫米地 等流、A.チャールズ・ミュラー、下田 正弘 | 情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会 | 『じんもんこん2014論文集』 | 2014 | ○ | |
| 大正新脩大藏經とデジタル時代の学術情報流通 | 永崎研宣 | 勉誠出版 | 『DHjp』 | No.3 | 2014 | |
| 「オープン」とDH | 永崎研宣 | 勉誠出版 | 『DHjp』 | No.4 | 2014 | |
| デジタル技術を活用した人文学研究の現在 | 永崎研宣 | 明治書院 | 『日本語学』 | 第432号 33-14(2014年11月臨時増刊号) | 2014 | |
| 日本語クラウドソーシング翻刻に向けて | 永崎研宣 | 情報科学技術協会 | 『情報の科学と技術』 | Vol.64(2014), No.11 | 2014 | |
| クラウドソーシングによるテクスト翻刻の実践に向けて | 永崎研宣 | 情報処理学会 | 『情報処理学会研究報告』2014-CH-102 (2014-05-24) | 6 | 2014 | |
| Bridging the Local and the Global in DH: A Case Study in Japan | Kiyonori Nagasaki A. Charles Muller Toru Tomabechi and Masahiro Shimoda | Lausanne (Switzerland) | Digital Humanities 2014 | 2014 | ○ | |
| The Development of The Dickens Lexicon Digital and its Practical Use for the Study of Late Modern English | Masahiro Hori Osamu Imahayashi Tomoji Tabata Keisuke Koguchi Miyuki Nishio and Kiyonori Nagasaki | Lausanne (Switzerland) | Digital Humanities 2014 | 2014 | ○ | |
| 古典籍原本画像と翻字テキストの対照ビュアーの作成と教育利用事例 | 高田智和・小助川貞次 | 国立国語研究所 | 『国立国語研究所論集』 | 第8号 | 2014 | ○ |
| ヲコト点の座標表現 | 高田智和 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 第192集 | 2014 | ○ |
| 近世後期上方における待遇表現化のコロケーション | 村上 謙 | 明治書院 | 『日本語学』 | 第432号 33-14(2014年11月臨時増刊号) | 2014 | |
| Educazione nel Seminario: il Compendium di Pedro Gómez | Aldo Tollini | Bulzoni Editore | L’Educazione nella società asiatica | 【図書論文】 | 2014 | |
| Il pensiero di Dōgen al di là di affermazione e negazione (Dōgen thought beyond affirmation and negation) | Aldo Tollini | Aracne editrice, Ariccia | Mastrangelo Matilde et al. (a cura di), Riflessioni sul Giappone antico e moderno | 【図書論文】 | 2014 | |
| Commento a: La religione senza Dio (Comment to: A Religion without God) | Aldo Tollini | Carocci | La società degli individui | n. 50, anno XVII | 2014 | |
| An Ancient Writing System for Modern Japan | Aldo TOLLINI | Edizioni Ca" Foscari | Contemporary Japan Challenges for a World Economic Power in Transition | 2015 | ○ | |
| 古代歌謡と和歌に見える漢文の影響 | Aldo Tollini | JSL漢字学習研究会 | JSL漢字学習研究会誌 | 7号 | 2015 | |
| World Cartography in the Jesuit Mission in China. Cosmography Theology Pedagogy | Angelo Cattaneo | Macau Ricci Institute | Artur K. Wardega S.J. (ed.) Education for New Times: Revisiting Pedagogical Models in the Jesuit Tradition | 【図書論文】 | 2014 | |
| Cartografie Poliane | Angelo Cattaneo | Edizioni Ca" Foscari | Giovanni Battista Ramusio, Dei viaggi di Messer Marco Polo | 【図書論文】 | 2015 | |
| Geographical Curiosities and Transformative Exchange in the Nanban Century (c.1549-c.1647) | Angelo Cattaneo | INST MONDE ANGLOPHONE | Etudes Epistémè | 26 | 2014 | ○ |
| The Silence Which has Woven My Life Together | Eduardo Fernández | University of Guam | Micronesian Educator Journal | 19 | 2014 | |
| La Misión a la luz de Francisco: el Mundo Latino en los Estados Unidos y la Espiritualidad Popular | Eduardo Fernández | Cochabamba Universidad Católica Bolivariana, Cochabamba. Instituto de Estudios Teológicos | Yachay | 30 (61) | 2014 | ○ |
| Hiroshima Rages, Nagasaki Prays: Nagai Takashi"s Catholic Response to the Atomic Bombing | Kevin Doak | Brill Academic Publishers | When the Tsunami Came to Shore: Culture and Disaster in Japan | 2014 | ||
| Before Silence: Stumbling Along with Rodrigues and Kichijiro | Kevin M Doak | Bloomsbury Academic | Mark W. Dennis, Darren J.N. Middleton, eds. Approaching Silence: New Perspectives on Shusaku Endo"s Classic Novel | 【図書論文】 | 2015 | |
| Abe at the Crossroads: ISIS Yoshida and Japan"s Foreign Policy Future | Kevin M Doak | Edmund A. Walsh School of Foreign Service at Georgetown University | Georgetown Journal of International Affairs | 2014 | ||
| Kiku"s Prayer for Religious Freedom | Kevin M Doak | Cornerstone: A Conversation on Religious Freedom and Its Social Implications | 2014 | |||
| Sacred High City, Sacred Low City: A Tale of Religious Sites in Two Tokyo Neighbourhoods, by Steven Heine. | Carla TRONU | International Research Center for Japanese Studies | Japan review : Journal of the International Research Center for Japanese Studies | 27 | 2014 | |
| 近世日本におけるカトリック「小教区制度」と「キリシタン町」の長崎 | トロヌ・カルラ | 「アジア・キリスト教・多元主義」研究会 | 『アジア・キリスト教・多元性』 | 第13号 | 2015 | |
| The Rivalry between the Society of Jesus and the Mendicant Orders in Early Modern Nagasaki | Carla TRONU | 天理大学地域文化研究センター | 『アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)』 | 第12号 | 2015 | ○ |
| Violence against Catholics in East Asia: Japan, China, and Korea from the Late Sixteenth Century to the Early Twentieth | Franklin Rausch | Oxford University Press | Oxford Handbooks Online | 2014 | ||
| Dying for Heaven: Persecution, Martyrdom, and Family in the Early Korean Catholic Church | Franklin Rausch | University of Hawaii Press | Death, Mourning, and the Afterlife in Korea | 【図書論文】 | 2014 | |
| Kagawa Toyohiko and the Japanese Christian Impact on American Society | Mark R. Mullins | University of Hawaii Press. | Encountering Modernity: Christianity in East Asia and Asian America | 【図書論文】 | 2014 | |
| Japanese Responses to Imperialist Secularization: The Postwar Movement to Restore Shintō in the Public Sphere | Mark R. Mullins | De Gruyter | Multiple Secularities Beyond the West: Religion and Modernity in the Global Age. | 【図書論文】 | 2015 | |
| The Diaspora of a Jesuit Press: Mimetic Imitation on the World Stage | Mia Mochizuki | Ashgate | Feike Dietz, Adam Morton, Lien Roggen, Els Stronks and Marc van Vaeck, eds, Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 | 【図書論文】 | 2014 | |
| Shock Value: The Jesuit Martyrs of Japan and the Ethics of Sight | Mia Mochizuki | Yale University Press | Sensational Religion: Sensory Cultures in Material Practice | 【図書論文】 | 2014 | |
| The Luso-Baroque Republic of Things and the Contingency of Contact | Mia Mochizuki | American Portuguese Studies Association | Journal of Lusophone Studies | 12 | 2014 | ○ |
| 大正博覧会の「台湾館」の観方-志賀直哉を中心に- | 郭南燕 | 中央研究院人文社會科學研究中心 | 『日本文学における台湾』張季琳編 | 【図書論文】 | 2014 | |
| 上海語話者の「言文不一致」舌を肥やし、耳を養う | 郭南燕 | 昭和堂 | 『五感/五環 文化が生まれるとき』阿部健一監修 | 【図書論文】 | 2015 | |
| 「バイリンガルな日本語文学」の将来性 | 郭南燕 | 国際日本文化研究センター | 『日文研』 | 53 | 2014 | |
| 外国人の日本語文学ー国際語への歩みー | 郭南燕 | お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター | 『比較日本学教育研究センター研究年報』 | 11号 | 2015 | |
| Ockham, Almain, and the Idea of Heresy | Takashi Shogimen | Palgrave Macmillan | Karen Bollermann, Thomas M. Izbicki, and Cary J. Nederman, eds. Religion, Power and Resistance from the Eleventh to the Sixteenth Centuries: Playing the Heresy Card | 【図書論文】 | 2014 | |
| トマス・アクィナス | 将基面貴巳 | 法政大学出版局 | 『西洋政治思想資料集』 | 【図書論文】 | 2014 | |
| Patriotism and Republicanism in Japan: A Century Ago and Today | Takashi Shogimen | Routledge | Republicanism in Northeast Asia | 【図書論文】 | 2014 | |
| Censorship Academic Factionalism and University Autonomy in Wartime Japan: The Yanaihara Incident Reconsidered | Takashi Shogimen | Society for Japanese Studies | The Journal of Japanese Studies | 40(1) | 2014 | ○ |
| Theological Education of Not Yet | Fumitaka Matsuoka | Cascade Books | Eleazar S. Fernandez, ed. Teaching for a Culturally and Racially Just World | 【図書論文】 | 2014 | |
| 日本の春画・艶本にみる「和合」 | 石上阿希 | 笠間書院 | 『日本人は日本をどうみてきたか』 | 2015 | ||
| 図録解説『東洋文庫コレクションにみる浮世絵としての春画』 | 石上阿希 | 東洋文庫 | 『岩崎コレクション~孔子から浮世絵まで』 | 2014 | ||
| 黒いカーテンの向こう側‐大英博物館春画展と日本 | 石上阿希 | 日本博物館協会 | 『博物館研究』 | 49(8) | 2014 | |
| 古典文学と艶本 | 石上阿希 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 2 | 2014 | |
| 地中海から日本へ | 川村信三 | 東京大学出版会 | 『ヨーロッパ中近世の兄弟会』河原温、池上俊一編 | 2014 | ||
| 日本近代におけるカトリック・アイデンティティーとカトリック教育 | 川村信三 | キリシタン文化研究会 | 『キリシタン文化研究会誌』 | 144 | 2014 | ○ |
| キリシタン大名 黒田官兵衛の消されたアイデンティティ | 川村信三 | 都市出版 | 『東京人』 | 29 (8) | 2014 | |
| 近代中国語辞書の苦悩――波寄せてくる日本新語にいかに対処すべきか | 陳力衛 | 関西大学アジア文化研究センター | 『環流する東アジアの近代新語訳語』沈国威、内田慶市編 | 【図書論文】 | 2014 | |
| 明治初年日本僧の中国語体験 | 陳力衛 | 成城大学 | 『成城大学経済研究』 | 206 | 2014 | |
| 「國語」、「漢語」、以及「日本語」──近代日本的語言論述 | 陳 瑋芬 | 學生書局 | 鄭宗義主編『全球化與本土之間的哲學探索──劉述先教授八秩壽慶論文集』 | 2014 | ||
| 金永鍵之日本與東南亞交流史論──『印度支那と日本との関係』 | 陳瑋芬 | 中央研究院中國文哲研究所 | 『東亞視域中的越南』鍾彩鈞主編 | 2015 | ○ | |
| 山本達郎之中越交流史論──『安南史研究』述評 | 陳瑋芬 | 中央研究院中國文哲研究所 | 『東亞視域中的越南』鍾彩鈞主編 | 2015 | ○ | |
| 「宗教」一語的成立與服部宇之及的孔教論 | 陳瑋芬 | 臺灣大學出版社 | 『東亞視域中的孔子形象與思想』 | 2015 | ○ | |
| 東奥義塾の設立とその背景-旧藩校書籍を読み解く一助として- | 北原かな子 | 弘前大学地域未来創生センター | 『東奥義塾高等学校所蔵 旧弘前藩古典籍調査集録』 | 2015 | ||
| 東奥義塾を巡るいくつかの「接続」 | 北原かな子 | 慶應義塾福沢研究センター | 『近代日本研究』 | 31巻 | 2015 | ○ |
| 近代津軽地方における藍の改良・開発をめぐる諸相-明治10年代前半の弘前藩士族の取り組みを中心に- | 北原かな子 | 青森中央学院大学経営法学部 | 『青森中央学院大学研究紀要』 | 23号 | 2015 | ○ |
| A Study on the Korean Railway Property during the South Manchuria Railway Period | Eunsun Bae、Byunghyun Chung、Yongsang Lee | The Korean Society for Railway | Journal of the Korean Society for Railway | 第17巻4號 | 2014 | ○ |
| 日本統治期の朝鮮鉄道 | 李容相 | 学習院大学東洋文化研究所 | 『東洋文化研究』 | 第16号 | 2014 | |
| 新井白石の知識世界序説 | 李梁 | 弘前大学人文学部 | 『人文社会論叢 人文科学篇』 | 第33号 | 2015 | |
| 在日本和東亜的研究交流征程中求索 | 趙建民 | 天津社会科学院東北亜研究所 | 『東北亜学刊』 | 14 | 2014 | |
| 附訓活字本『諸疾禁好集』と梅壽の出版活動―古活字版終焉の解明にむけて | ピーター・コーニツキー | 天理大学附属天理図書館 | 『ビブリア』 | 144 | 2015 | |
| 慶長前後における書物の書写と学問 | 海野圭介 | 勉誠出版 | 『形成される教養 十七世紀日本の〈知〉』鈴木健一編 | 2015 | ||
| 日本の絵入り本の歴史―絵本が出版されるまで | 佐々木孝浩 | 慶應義塾大学出版会 | 『出版文化の東西 原本を読む楽しみ』 | 2015 | ||
| 日本語の文字種と書物の関係について―写本の時代から版本の時代まで― | 佐々木孝浩 | 延世大学校人文学研究院 | 『人文科学』 | 103号 | 2015 | |
| 日本古典籍における近世初期の表紙の変化について―朝鮮本と和本を繋ぐもう一つの視座 | 佐々木孝浩 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』日韓の書誌学と古典籍 | 184 | 2015 | |
| Treasure Boxes, Fabrics, and Mirrors. On the Contents and the Classification of Popular Encyclopedias from Early Modern Japan | Michael Kinski | Brill | Listen, Copy, Read. Popular Learning in Early Modern Japan | 46 | 2014 | |
| Geschichte der Kindheit im Japan der Frühen Neuzeit. Methodische Ansätze und Themen der Forschung | Michael Kinski | Harrassowitz | Geschichte der Kindheit und der Kindheitsbilder in Japan. Eine Einführung | 2015 | ||
| Chinese Texts in pre-modern East and South-East Asia | ピーター・コーニツキー | Oxford Bibliographies | Chinese Studies | 2015 | ||
| Tsushima: Japan seen from the margins – archives, books,ginseng | ピーター・コーニツキー | The Japan Society | The Japan Society Proceedings | 151 | 2015 | |
| Korean books in Japan before Hideyoshi’s invasion | ピーター・コーニツキー | American Oriental Society | Journal of the American Oriental Society | 135(3) | 2015 | |
| 附訓活字本『諸疾禁好集』と梅壽の出版活動 : 古活字版終焉の解明にむけて | ピーター・コーニツキー | 天理大学出版部 | 『ビブリア』 | 144 | 2015 | |
| ‘The role of non-commercial editions in the diffusion of Chinese texts in East Asia’, in Michela Bussotti and Jean-Pierre Drège, eds, | ピーター・コーニツキー | EFEO | Imprimer autrement: le livre non commercial dans la Chine impériale | 2015 | ||
| Presenting the *Great Learning* to the public in Edo-period Japan’, in Ann Cheng, ed. | ピーター・コーニツキー | Collège de France | The Great Learning in East Asia | 2015 | ||
| ‘Women readers and books for women’, in Peter Burke and J. P.McDermott, eds, | ピーター・コーニツキー | Hong Kong: Hong Kong University Press | The book worlds of East Asia and Europe, 1450-1850:connections and comparisons | 2015 | ||
| Publishing and the book in the seventeenth and eighteenth centuries | P. F. Kornicki | Cambridge University Press | The Cambridge history of Japanese literature | 2016 | ||
| 幸若舞曲の絵画化と受容空間に関する一考察 : 「曽我物語図屏風」を例として | 井戸美里 | 美学会 | 『美学』 | 66 | 2015 | |
| 日本民俗の時間観―陰陽道の民俗的展開を中心として― | 小池淳一 | 名古屋大学文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター | HERITEX | Vol.1 | 2015 | |
| 尼と物語草子 | 恋田知子 | 東京大学国語国文学会 | 『國語と國文學』 | 第1098号 92-5 | 2015 | |
| 黒白争闘―『鴉鷺合戦物語』攷― | 齋藤真麻理 | 汲古書院 | 『いくさと物語の中世』鈴木彰・三澤裕子編 | 2015 | ||
| 役者評判記の戦略─八文字屋と江島屋─ | 河合眞澄 | 演劇研究会 | 『演劇研究会会報』 | 第41号 | 2015 | |
| 役者評判記の挿絵─上演実態の反映─ | 河合眞澄 | 明治書院 | 『國語と國文學』 | 第1102号 92-9 | 2015 | |
| 歌川国芳「夏けしき花の縁日」 | 佐藤悟 | 国際浮世絵学会 | 『浮世絵芸術』(国際浮世絵学会会誌) | 170号 | 2015 | ○ |
| 翻刻『忠臣規矩順従録』(一) | 山本卓 | 関西大学国文学会 | 『国文学』 | 第99号 | 2015 | |
| 赤穂義士伝もの実録の生長 ー『内侍所』から『赤穂精義内侍所』へを中心にー | 山本 卓 | 岩波書店 | 『文学』 | 第16巻第4号 | 2015 | |
| 「猫と提灯」と花鳥動物画 (小林清親 : "光線画"に描かれた郷愁の東京) -- (多彩な画業の展開) | 浅野秀剛 | 平凡社 | 『別冊 太陽:日本のこころ』 | 229 | 2015 | |
| 文化交渉から見る日本と台湾の膠彩画(日本画) : 陳進と鏑木清方の邂逅 | 中谷伸生 | 南島史学会 | 『南島史学』 | 108 | 2015 | |
| 研究ノート 八代目市川團十郎を描いた浮世絵 連載【一】ー八代目襲名ー | 服部仁 | 国際浮世絵学会 | 『浮世絵芸術』(国際浮世絵学会会誌) | 171号 | 2016 | |
| 実録『播州高砂天竺徳兵衛渡天海陸物語』から : 刊本『万国地理 天竺徳平往来噺』へ | 服部仁 | 岩波書店 | 『文学』 | 16(4) | 2015 | |
| 『大塔宮熊重篠繋』のこと | 木村八重子 | 雅俗の会 | 『雅俗』 | 14 | 2015 | |
| 算額を世界文化遺産にー取り組みの始めとして | 小林龍彦 | 日本評論社 | 『数学文化』 | 24 | 2015 | |
| 中根元圭と三角法 | 小林龍彦 | 思文閣出版 | 『徳川社会と日本の近代化』笠谷和比古編 | 2015 | ||
| 近世の暦と天文学 | 小林龍彦 | 思文閣出版 | 『角倉一族とその時代』森洋久編 | 2015 | ||
| 和算への誘い 和算が始まる前 | 上野健爾 | くまもと文化振興会 | 『Kumamoto : 総合文化雑誌』 | 10 | 2015 | |
| 和算への誘い2 和算興隆の基礎を作った『塵劫記』 | 上野健爾 | くまもと文化振興会 | 『Kumamoto : 総合文化雑誌』 | 11 | 2015 | |
| 和算への誘い3 日本独自の数学を作った関孝和 | 上野健爾 | くまもと文化振興会 | 『Kumamoto : 総合文化雑誌』 | 12 | 2015 | |
| 和算への誘い4 関孝和以降の和算 | 上野健爾 | くまもと文化振興会 | 『Kumamoto : 総合文化雑誌』 | 13 | 2015 | |
| 「飯塚正明文庫」目録-資料群の調査報告とその特徴- | 中山剛志・小林龍彦 | 群馬県立歴史博物館 | 『群馬県立歴史博物館紀要』 | 36 | 2015 | |
| 智積院新文庫聖教について―その成立と伝来を巡って― | 宇都宮啓吾 | 説話文学会 | 『説話文学研究』 | 50 | 2015 | ○ |
| 智積院聖教における「東山」関係資料について ー智積院蔵『醍醐祖師聞書』を手がかりとしてー |
宇都宮啓吾 | 智山勧学会 | 『智山学報』 | 65 | 2016 | |
| 惣国首都の空間構成とネットワーク 世界史のなかの根来寺 | 海津一朗 | 説話文学会 | 『説話文学研究』 | 50 | 2015 | ○ |
| 蓮体編『礦石集』と地蔵寺所蔵文献―地蔵関連資料を中心として― | 山崎淳 | 仏教文学会 | 『仏教文学』 | 39 | 2014 | ○ |
| 覚一本『平家物語』安徳天皇入水記事が示すもの―厳島明神を介して、竜女、そして文殊菩薩へ | 小林 加代子 | 同志社大学国文学会 | 『同志社国文学』 | 81号 | 2014 | |
| 熊楠メモランダム《8》「南方熊楠と万葉集」 | 杉山和也 | 南方熊楠顕彰会 | 『熊楠Works』 | 44 | 2014 | |
| シンポジウム「九・十世紀の熊野と王権―熊野の神像へのまなざしから―」の概要報告 | 川崎剛志 | 和歌山県立博物館 | 『和歌山県立博物館研究紀要』 | 21 | 2015 | |
| Editor’s Introduction Engi: Forging Accounts of Sacred Origins | Heather Blair and Kawasaki Tsuyoshi | 南山宗教文化研究所 | Japanese Journal of Religious Studies | 42-1 | 2015 | ○ |
| The Invention and Reception of the Mino’odera engi | Kawasaki Tsuyoshi | 南山宗教文化研究所 | Japanese Journal of Religious Studies | 42-1 | 2015 | ○ |
| 春草と秋風―「恨賦」による哀傷表現と法会の場― | 牧野淳司 | 明治大学文学部文芸研究会 | 『文芸研究』 | 126 | 2015 | ○ |
| 宮城県の自治体史に見る津波災害の記録について | 佐藤賢一 | 東北学院大学 | 『震災学』 | 7 | 2015 | |
| 明治30年の渡波におけるフカヒレ製造記録について | 佐藤賢一 | 石巻学プロジェクト | 『石巻学』 | Vol.1 | 2015 | |
| 英語圏における日本漢文学研究の現状と展望 | マシュー・フレーリ | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 日朝漢詩交流の場における古文辞派の存在―申維翰(シンユハン)の日本漢詩批評を例に― | 康盛国 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 古代日本漢文学と長安・洛陽 | 高兵兵 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 特集・研究会の今 日本漢詩文とカノン―「日本漢文学プロジェクト」活動報告 | 合山林太郎 | 笠間書院 | 『リポート笠間』 | 58 | 2015 | |
| 日本漢詩における“名詩”とは何か | 合山林太郎 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 竹枝詞の変容―詩風変遷と日本化― | 新稲法子 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 日本漢詩史中的“唐”与“宋” | 浅見洋二 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度)研究交流会(講演集)』 | 2015 | ||
| 面白かった、この三つ | 滝川幸司 | 笠間書院 | 『リポート笠間』 | 59 | 2015 | |
| 日中世漢学および五山禅林文学を捉えなおす―「日本中世文学史」の新たな構築のために― | 中本大 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 学術・教学の形成と漢学 | 町泉寿郎 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 語法から見る近世詩人たちの個性―唐調の詩人たちを中心に― | 福島理子 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| 近世後期の詩人における中唐・晩唐 | 鷲原知良 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学会第8次海外特別例会(2015年度) 和漢比較文学シンポジウム2015予稿集』 | 2015 | ||
| The Kuzushiji Project: Developing a Mobile Learning Application for Reading Early Modern Japanese Texts | Yuta Hashimoto, Yoichi Iikura, Yukio Hisada, SungKook Kang, Tomoyo Arisawa, Akihiro Okajima, Tsutomu Yada, Rintaro Goyama, Daniel Kobayashi-Better | Digital Humanities | Digital Humanities Quarterly | 2017,Volume 11,Number 1 | 2017 | ○ |
| Grave Relation---: Hamlet Jyuran Hisao’s ‘Hamuretto’ the Emperor and the War. | Kaori Ashizu | SAGE Publications | Cahiers Élisabéthains | 87 | 2015 | ○ |
| サドの読み方―遠藤・澁澤・三島 | 梶尾文武 | 青土社 | 『ユリイカ』 | 46巻 12号 | 2014 | |
| 『太平記』の明治-交差する情念と歴史- | 樋口大祐 | 響文社 | 『アナホリッシュ國文學』 | 8号 | 2015 | |
| 統一戦争の敗者と近世都市 | 樋口大祐 | 汲古書院 | 『いくさと物語の中世』鈴木彰・三澤裕子編 | 2015 | ||
| 冷泉立太子と藤壺立后 | 福長進 | 岩波書店 | 『文学』 | 16 | 2015 | |
| 古典籍資料から讀み取れるツバキの品種分化 | 岸川慎太郎、久保輝幸、田中孝幸 | 日本ツバキ協会 | 『椿』 | 第53号 | 2015 | |
| 中国科学史研究における史料文献の問題 | 久保輝幸 | 日本科学史学会生物学史分科会 | 『生物学史研究』 | 第91号 | 2014 | ○ |
| 日中文化交流中的植物要素初探 | 久保輝幸、津田量、周晨亮 | 北京对外贸易学院 | 『日語学習与研究』 | 180号(2015年第5号) | 2015 | ○ |
| Numerology and Calendrical Learning: The Stories of Yang Guangxian and Liu Xiangkui | Chu Pingyi | The Korean History of Science Society | The Korean Journal for the History of Science | 37-2 | 2015 | ○ |
| 『毛詩品物図考』より見た18世 紀における新しい「知」の形成 | 陳捷 | 岩波書店 | 『西学東漸と東アジア』川原秀城編 | 2015 | ||
| 韓国国立中央図書館所蔵琉球『選日通書』について | 陳捷 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』日韓の書誌学と古典籍 | 184 | 2015 | |
| 平野満教授 業績目録と略歴 | 平野恵 | 洋学史学会 | 『洋学』 | 22 | 2015 | ○ |
| 京都の絵草紙屋紙藤(綾喜)―引札と紙看板― | 鈴木俊幸 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 5 | 2015 | |
| 七禽食方及其出处《金匮录》《神仙服食经》 《自然科学史研究》 | 久保輝幸 | 中国医学会 | 『第14回中国医師会医療歴史学会年次総会のまとめ』 | 第34卷 | 2015 | |
| 日本における仲景医書関連年表(付・神農本草経関連年表)(3) | 真柳誠 | 東亜医学協会 | 『漢方の臨床』 | 63巻1号 | 2016 | |
| 韓國國立中央圖書館の古醫籍書誌(二) | 真柳誠 | 茨城大学人文学部 | 『茨城大学人文学部紀要 人文コミュニケーション学科論集』 | 20号 | 2016 | |
| 和歌・連歌・平家と能および早歌―諸ジャンルの交渉― | 落合博志 | 中世文学会 | 『中世文学』 | 60 | 2015 | ○ |
| 日本の主な書籍コードについて | 井黒 佳穂子 | 国文学研究資料館 | 「日本古典籍コードの国際標準化」成果報告書 | 2015 | ||
| 全国古典籍等画像公開データベース一覧 | 千葉真由美・井黒佳穂子・金田房子 | 国文学研究資料館 | 「日本古典籍コードの国際標準化」成果報告書 | 2015 | ||
| 国文学研究資料館・日本語の歴史的典籍のデータベース構築について | 増井ゆう子、山本和明 | 情報科学技術協会 | 『情報の科学と技術』 | Vol.65(4) | 2015 | ○ |
| 国文学研究資料館古典籍資料のコードについて | 増井ゆう子 | 国文学研究資料館 | 「日本古典籍コードの国際標準化」成果報告書 | 2015 | ||
| 韓国国立中央図書館(National Library of Korea)、韓国国立デジタル図書館(dibrary)への訪問調査について | 中村 美里 | 国文学研究資料館 | 「日本古典籍コードの国際標準化」成果報告書 | 2015 | ||
| Digital Object Identifier(DOI)について | 片岡 耕平 | 国文学研究資料館 | 「日本古典籍コードの国際標準化」成果報告書 | 2015 | ||
| 時の聖俗―「き」と「けり」と― | 今西 祐一郎 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』もう一つの日本文学史 | 195 | 2016 | |
| 『播磨国風土記』解題 | 小倉慈司 | 天理大学附属天理図書館編 | 『新天理図書館善本叢書 1古事記〈道果本〉播磨国風土記』 | 2016 | ||
| 藤原順子のための天皇喪服議―註釈『日本三代実録』貞観十三年九月二十八日~十月七日条― | 稲田奈津子 | 法史学研究会 | 『法史学研究会会報』 | 18 | 2015 | ○ |
| 尊経閣文庫所蔵『暇服事』解説 | 稲田奈津子 | 八木書店 | 『尊経閣善本影印集成55 消息礼事及書礼事他』前田育徳会尊経閣文庫編集 | 2015 | ||
| 古代史料に見る海路と船 | 荒井 秀規 | 八木書店 | 『日本古代の運河と水上交通』鈴木靖民、川尻秋生、鐘江宏之編 | 2015 | ||
| 離宮・頓宮・行宮 | 仁藤敦史 | 吉川弘文館 | 『古代の都市と条里』条里制・古代都市研究会編 | 2015 | ||
| 「治天下大王」の支配観 | 仁藤敦史 | 雄山閣 | 『季刊考古学・別冊』 | 22 | 2015 | |
| 留守官について | 仁藤敦史 | 勉誠出版 | 『日本古代のみやこを探る』舘野和己編 | 2015 | ||
| 外交拠点としての難波と筑紫 | 仁藤敦史 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 200 | 2016 | ○ |
| 花山院の修行説話をめぐって | 倉本 一宏 | 白山史学会 | 『白山史学』 | 51 | 2015 | |
| 尾張・熊野の氏族と記紀の構想 | 早川万年 | 大和書房 | 『日本古代の王権と地方』 | 2015 | ||
| 八重山・宮古の英雄時代と「琉球帝国」 | 村木二郎 | 国立歴史民俗博物館 | 『歴博』 | 194 | 2016 | |
| 「朝倉館モデル」とその地平-小田原城址御用米曲輪跡の調査成果が投じた問題- | 村木二郎 | 東国中世考古学研究会 | 『発掘調査成果でみる16世紀大名居館の諸相』 | 2016 | ||
| 国家を超えた中世の日朝交流 | 村木二郎 | 国立歴史民俗博物館 | 『歴博』 | 195 | 2016 | |
| 日本古代の勘籍制 | 堀部 猛 | 正倉院文書研究会 | 『正倉院文書研究』 | 14 | 2015 | |
| 土浦の醤油醸造 | 堀部 猛 | 土浦市立博物館 | 『まちのしるし-しるしが語る土浦の近代-』土浦市立博物館特別展図録 | 2016 | ||
| 漢文訓読と日本語 | 高田智和 | 専修大学図書館編 | 『日本語の風景―文字はどのように書かれてきたのか―』 | 2015 | ||
| 変体仮名のこれまでとこれから―情報交換のための標準化― | 高田智和、矢田勉、斎藤達哉 | 科学技術振興機構 | 『情報管理』 | 第58巻 第6号 | 2015 | |
| 近世語研究の学史的展開―戦前における「対立」の思想を中心に― | 村上謙 | 武蔵野書院 | 『近代語研究』 | 18 | 2015 | |
| 近世後期上方における遊里語のあり方 | 村上謙 | 埼玉大学国語教育学会 | 『埼玉大学国語教育論叢』 | 17・18(合併号) | 2015 | ○ |
| メドハースト『英和和英語彙集』(1830)の底本について | 陳力衛 | 明治書院 | 『日本語史の研究と資料』中山緑朗編 | 【図書論文】 | 2015 | |
| Cartografie Poliane | Angelo Cattaneo | Edizioni Ca’ Foscari | Dei viaggi di Messer Marco Polo | 5 | 2015 | |
| European Medieval and Renaissance Cosmography: A Story of Multiple Voices | Angelo Cattaneo | Brill | Asian Review of World Histories | 4(1) | 2016 | |
| Teaching History in the Electronic Era: Strategies for Connecting with Millennial Generation Learners | Franklin Rausch | Ryan Floyd, Sarah Miller, and Paul Thompson, eds. Proceedings of the South Carolina Historical Association | 【図書論文】 | 2015 | ||
| ‘All Man, All Priest’: Father Emil Kapaun, Religion, Masculinity, and the Korean War | Franklin Rausch | Institute for the Study of Religion, Sogang University, Korea | Journal of Korean Religions | 6 (2) | 2015 | |
| Undermining the myths: Habian’s Shinto critique | John Breen | Brill | The Myotei dialogues: a Japanese Christian critique of native traditions | 【図書論文】 | 2015 | |
| On Shinto | John Breen | Brill | The Myotei dialogues: a Japanese Christian critique of native traditions | 【図書論文】 | 2015 | |
| Sacred Art in an Age of Mechanical Reproduction: The Salus Populi Romani Madonna in the World | Mia Mochizuki | Kyoto University | Kyoto Studies in Art History | 1 | 2016 | |
| Book review: Marcia B. Hall and Tracy E. Cooper, eds, The Sensuous in the Counter-Reformation Church | Mia Mochizuki | Archivum Historicum Societatis Iesu | 83 | 2014 | ||
| 豊後キリシタンの跡をたどるマリオ・マレガ神父ーマレガ文書群の成立過程とその背景 | シルヴィオ・ヴィータ | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 アーカイブス研究篇』 | 12号(通巻47号) | 2016 | |
| Liturgies and Sacraments Latinamente | Eduardo Fernández | Wiley | Orlando Espín, ed. The Wiley-Blackwell Companion to Latino/a Theology | 【図書論文】 | 2015 | |
| Book review, J. Serra: California, Indians, and the Transformation of a Missionary | Eduardo Fernández | Norman: University of Oklahoma Press | Before Gold: California under Spain and Mexico | 3 | 2015 | |
| William of Ockham on Ecclesiastical Censorship | Takashi Shogimen | Bloomsbury | Geoff Kemp, ed. Censorship Moments (Textual Moments in the History of Political Thought series) | 【図書論文】 | 2015 | |
| John of Paris and the Idea of Peace in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries | Takashi Shogimen | Brepols | Chris Jones, ed. John of Paris: Beyond Royal and Papal Power | 【図書論文】 | 2015 | |
| 2000年代以降の春画展示 | 石上阿希 | 文化資源学会 | 『文化資源学』 | 13 | 2015 | |
| 中国養生書と艶本 | 石上阿希 | 武田科学振興財団 | 『曲直瀬道三と近世日本医療社会』武田科学振興財団杏雨書屋編 | 【図書論文】 | 2015 | |
| 摂河地域のキリシタンと戦国宗教史 | 川村信三 | 戎光祥出版 | 『飯盛山城と三好長慶』仁木宏、中井均、中西裕樹、NPO法人摂河泉地域文化研究所編 | 【図書論文】 | 2015 | |
| 日本近代社会におけるカトリック・アイデンティティとカトリック教育 | 川村信三 | 上智大学出版 | 『アジアにおけるイエズス会大学の役割』 | 【図書論文】 | 2015 | |
| 書評と紹介「末木文美士編『妙貞問答を読む-ハビアンの仏教批判』」 | 川村信三 | 日本宗教学会 | 『宗教研究』 | 89巻 382号 | 2015 | ○ |
| フロイスの宗教観 | 瀧澤修身 | 山喜房佛書林 | 『比較思想から見た日本仏教』末木文美士編 | 【図書論文】 | 2015 | |
| 宣教師が理解した日本の身分制度: 一六世紀・一七世紀を中心に | 瀧澤修身 | キリシタン文化研究会 | 『キリシタン文化研究会会報』 | 146 | 2015 | |
| 『作家の原稿料』-西鶴の三百匁から始まる〈原稿料〉の歴史- | 谷口幸代 | 日本古書通信社 | 『日本古書通信』 | 80巻5号 | 2015 | |
| W.H.メドハースト『英和和英語彙』 | 陳力衛 | おうふう | 『悠久』 | 143 | 2015 | |
| 「優勝劣敗,適者生存」――進化論の中国流布に寄与する日本漢語 | 陳力衛 | 成城大学経済学会 | 『成城大学経済研究』 | 210号 | 2015 | |
| 近代東アジアの言語交渉による漢語の意味変化 | 陳力衛 | 延世大学校言語情報研究院 | 『言語事実と観点』 | 36 | 2015 | |
| 現代中国語にどのくらいの日本借用語があるのか | 陳力衛 | 関西大学出版部 | 『東アジア言語接触の研究』 (関西大学東西学術研究所研究叢刊―文化交渉と言語接触研究・資料叢刊) 沈 国威、内田 慶市編著 | 【図書論文】 | 2016 | |
| <書評と紹介> 山下須美礼著『東方正教の地域的展開と移行期の人間像 : 北東北における時代変容意識』 | 北原かな子 | 弘前大学國史研究会 | 『弘前大学國史研究』 | 139号 | 2015 | |
| 新井白石の漢学と西学 | 李梁 | 汲古書院 | 『「心身/身心」と環境の哲学』伊東貴之編 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 模索東亜地区文化交流研究的理論和方法——略述研究交流進展中的点滴感悟 | 趙建民 | 『日本研究集刊』 | 2015上半年刊 | 2015 | ||
| 情報学研究資源としてのデータセットの共同利用 | 大山敬三、大須賀智子 | 人工知能学会 | 『人工知能』 | 31(2) | 2016 | |
| くずし字古典籍の自動認識のための特徴量の検討 | 田中 佑馬 | - | 『平成27年度公立はこだて未来大学卒業論文』 | - | 2016 | |
| 手軽に使える変体仮名自動認識システムの開発 | 鎌倉 央 | - | 『平成27年度公立はこだて未来大学卒業論文』 | - | 2016 | |
| 非文献資料のための学術資源群による サブジェクトリポジトリの構築(構想と進捗状況) | 高田良宏、林正治、堀井洋、堀井美里、山地一禎、山下俊介、古畑徹 | 大学ICT推進協議会 | 『大学ICT推進協議会2015年度年次大会(AXIES2015) 論文集』 | 2015 | ||
| 学術的動画の評価傾向とその要因 | 林正治、田中克明、長谷海平、高見澤秀幸、松村芳樹、中島康、万代勝信 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2015論文集』 | 2015 | 2015 | ○ |
| Providing Bilingual Access to Multiple Japanese Humanities Databases: Text Retrieval Using English and Japanese Queries. | Biligsaikhan Batjargal, Akira Maeda, and Ryo Akama. | National Taiwan University Press | 『數位人文:在過去、現在和未來之間(數位人文研究叢書v.6)』 | 2016 | ||
| 多言語の浮世絵データベース間における同一 作品の同定手法の提案. | 木村 泰典, Biligsaikhan Batjargal, 木村 文則, 前田 亮. | 情報処理学会 | 『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』 | 2015 | ○ | |
| An Approach to Build a Proper Noun Dictionary for Record Linkage across Humanities Databases in Different Languages. | Yuting Song, Taisuke Kimura, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda. | 日本データベース学会 | 『第8回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2016)論文集』 | 2016 | ||
| Records of sunspot and aurora during CE 960–1279 in the Chinese chronicle of the Sòng dynasty | Hayakawa H, Tamazawa H, Kawamura AD, Isobe H | SpringerOpen | Earth, Planets and Space 2015 | 2015 | ||
| 江戸時代の写本文化考 ー『慶安太平記』を中心にして | ピーター・コーニツキー | 日本学術協力財団 | 『学術の動向』 | 21/6 | 2016 | |
| キリシタン版国字本の造本について―平仮名古活字本との比較を通して | 佐々木孝浩 | 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫 | 『斯道文庫論集』 | 51 | 2017 | |
| デジタルアーカイブ時代の大学における「読書」の可能性──東京大学新図書館計画における実験と実践 | 阿部卓也、谷島貫太、生貝直人、野網摩利子 | 新曜社 | 『ハイブリッド・リーディング―新しい読書と文字学』 | 2016 | ||
| 和歌注釈と室町の学問 | 海野圭介 | 中世文学会 | 『中世文学』 | 61 | 2016 | |
| 本の妖怪、妖怪の本―東西の付喪神考― | ケラー・キンブロー | 勉誠出版 | 『東の妖怪・西のモンスター ―想像力の文化比較―』 | 【図書論文】 | 2017 | |
| Visualizing National History in Meiji Japan: The Komaba Museum Collection | 井戸美里 | The Japanese Society for Aesthetics | Aesthetics | 20 | 2016 | |
| 国文学研究資料館蔵『狂言絵』を読む | 小林健二 | 国文学研究資料館 | 『国文研ニューズ』 | 43 | 2016 | |
| 短冊手鑑「筆陳」 | 海野圭介 | 教育新社 | 『文部科学省教育通信』 | 387 | 2016 | |
| 古筆手鑑 | 海野圭介 | 教育新社 | 『文部科学省教育通信』 | 388 | 2016 | |
| 禅僧の詠んでない歌を集めて『詩経』を作る | ダヴァン・ディディエ | 教育新社 | 『文部科学省教育通信』 | 393 | 2016 | |
| 狂気の中心に立つ紅誠実 | ダヴァン・ディディエ | 教育新社 | 『文部科学省教育通信』 | 394 | 2016 | |
| 室町の“あそび”―『扇の草子』への招待― | 恋田知子 | 教育新社 | 『文部科学省教育通信』 | 385 | 2016 | |
| 同筆の奈良絵本―嫁入り道具としての物語絵― | 恋田知子 | 教育新社 | 『文部科学省教育通信』 | 386 | 2016 | |
| 骸骨の物語草子―『幻中草打画』再考 | 恋田知子 | ぺりかん社 | 『禅からみた日本中世の文化と社会』 | 2016 | ||
| お伽草子が描く海 | 恋田知子 | 三弥井書店 | 『海の文学史』鈴木健一編 | 【図書論文】 | 2016 | |
| The Current State of Research on Monogatari-sōsh: Women, Changelings, and Other Worlds in Otogi-zōshi | 恋田知子 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 43 | 2017 | |
| 『唐土訓蒙図彙』への誘い | クリストファー・リーブズ | 国文学研究資料館 | 『国文研ニューズ』 | 45 | 2016 | |
| 子ども絵・子ども絵本―破邪と予祝 | 佐藤悟 | 醍醐出版 | 『美術フォーラム21』 | 34 | 2016 | |
| 明治十年の小林清親と松本平吉 | 浅野秀剛 | 醍醐出版 | 『美術フォーラム21』 | 34 | 2016 | |
| 魯文の滑稽本 (特集 近世文学における〈続編〉) | 高木元 | 日本文学協会 | 『日本文学』 | 65(10) | 2016 | ○ |
| 早稲田大学演劇博物館所蔵からくり関連絵画資料の紹介 | 山田和人 | 演劇研究会 | 『演劇研究会会報』 | 42 | 2016 | ○ |
| D.E, Smith 宛三上義夫書簡について | 小林辰彦、森本光生 | 日本数学史学会 | 『数学史研究』 | 223 | 2015 | |
| On the Volume 12 of the Taisei Sankyou written by Seki Takakazu and Takebe Brothers --- A History of Early Calculations of pi in Pre-modern Japan --- | 小川束 | Korea Institute for Advanced Studies, The Korean Society for History of Mathematics | Proceedings of The Korean Society for History of Mathematics | 26 | 2016 | |
| Theory of Equations in the Taisei Sankei | 森本光生 | Korea Institute for Advanced Studies, The Korean Society for History of Mathematics | Proceedings of The Korean Society for History of Mathematics | 26 | 2016 | |
| 太田城水攻め研究の現在:紀州研フィールドミュージアム叢書①『中世終焉 秀吉の太田城水攻め 』刊行8年の総括 | 宇民正、海津一朗、弓倉弘年、新谷和之 | 和歌山大学紀州経済史文化史研究所 | 『紀州経済史文化史研究所紀要』 | 37 | 2016 | ○ |
| 紀州藩家老三浦家文書(二二):江戸出府日記・御用番留帳 | 上村雅洋 | 和歌山大学紀州経済史文化史研究所 | 『紀州経済史文化史研究所紀要』 | 37 | 2016 | |
| 書評 村瀬憲夫・三木雅博・金田佳弘著『和歌の浦の誕生―古典文学と玉津島社』 | 菊川恵三 | 和歌山大学紀州経済史文化史研究所 | 『紀州経済史文化史研究所紀要』 | 37 | 2016 | |
| 称名寺聖教・金沢文庫文書の国宝指定に関連して | 貫井裕恵 | 日本古文書学会 | 『第49回日本古文書学会大会(記念冊子)』 | 2016 | ||
| 東大寺本末相論関係史料の紹介―兵庫県立歴史博物館蔵喜田文庫のうち― | 貫井裕恵 | 神奈川県立金沢文庫 | 『金沢文庫研究』 | 337 | 2016 | |
| 総説 一 | 貫井裕恵 | 神奈川県立金沢文庫 | 『特別展 忍性菩薩』 | 2016 | ||
| 忘れられた秀才・立花銑三郎 | 杉山和也 | 南方熊楠顕彰会 | 『熊楠ワークス』(機関誌) | 48 | 2016 | |
| 南方熊楠と高木敏雄の説話研究―その特徴と可能性― | 杉山和也 | 南方熊楠顕彰会 | 『熊楠研究』 | 11 | 2017 | ○ |
| 古典教育と宗教思想―中世は「宗教の時代」なのか? | 藤巻和宏 | 笠間書院 | 『ともに読む古典:中世文学編』松尾葦江編 | 【図書論文】 | 2017 | |
| 室町期における三席御会 | 山本啓介 | 青山学院大学日本文学会 | 『青山語文』 | 47 | 2017 | |
| 鎌倉・南北朝期における中殿和歌御会と三席御会 | 山本啓介 | 風間書房 | 『日本詩歌への新視点 廣木一人教授退職記念論集』 | 2017 | ||
| 訓点資料を対象とした翻刻システムの構築および評価 | 田中勝、村川猛彦、宇都宮啓吾 | 情報処理学会 FIT2016第15回情報科学技術フォーラム | 『第15回情報科学技術フォーラム第4分冊』 | 2016 | ||
| 和泉国家原寺聖教の形成に関する一考察―智積院聖教・金剛寺聖教を手懸かりに― | 宇都宮啓吾 | 日本密教学会 | 『密教学研究』 | 49 | 2017 | |
| 智積院蔵『秘蔵宝鑰抄巻下』について | 宇都宮啓吾 | 智山勧学会 | 『智山学報』 | 66 | 2017 | |
| 『職原抄』訓点本の資料性について―龍谷大学本を手懸かりとして― | 宇都宮啓吾 | 和泉書院 | 藤田保幸編『言語文化の中世』 | 2018 | ||
| 天野山金剛寺一切経の来歴について | 大塚紀弘 | 寺院史研究会 | 『寺院史研究』 | 15 | 2016 | |
| 『愛宕地蔵物語』の基礎的考察 | 舩田淳一 | 名古屋大学人類文化遺産テクスト学研究センター | 『越境する絵物語』 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 〈法華経儀礼〉の世界―平安時代の法華講会を中心に― | 舩田淳一 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』日本化する法華経 | 202 | 2016 | |
| 中世「村」表記の性格と多様性―紀伊国荒川荘を事例に― | 坂本亮太 | 高志書院 | 『中世村落と地域社会―荘園制と在地の論理―』 | 2016 | ||
| 三上別所・願成寺の村立構造 | 坂本亮太 | 和歌山地方史研究会 | 『和歌山地方史研究』 | 71 | 2016 | ○ |
| 大阪湾の「咽喉」―加太・友ヶ島― | 坂本亮太 | 清文堂出版 | 『わかやまを学ぶ』: 紀州地域学 初歩の初歩 (和歌山大学フィールドミュージアム叢書 4) | 【図書論文】 | 2017 | |
| 書評 湯之上隆著『日本中世の地域社会と仏教』 | 坂本亮太 | 日本史研究会 | 『日本史研究』 | 650 | 2016 | ○ |
| 徳川頼宣と天海による東照社(宮)祭礼の創始―東照社小祥祭と和歌祭を中心として― | 吉村旭輝 | 名勝和歌の浦 玉津島保存会 | 『文化財担当者と学ぶ名勝和歌の浦』 | 【図書論文】 | 2017 | |
| 東照社祭礼の創始と芸能―和歌祭唐船・唐人を中心として― | 吉村旭輝 | 清文堂出版 | 『わかやまを学ぶ』: 紀州地域学 初歩の初歩 (和歌山大学フィールドミュージアム叢書 4) | 【図書論文】 | 2017 | |
| 「道成寺建立縁起」考 | 大橋直義 | 清文堂出版 | 『わかやまを学ぶ』: 紀州地域学 初歩の初歩 (和歌山大学フィールドミュージアム叢書 4) | 【図書論文】 | 2017 | |
| 伝記への執心─『扶桑略記』の歴史叙述、一隅 | 大橋直義 | 国文学研究資料館 | 『歴史叙述と文学』 | 2017 | ||
| 伝授資料から見る木山寺経蔵の史的一端 | 中山一麿 | 法蔵館 | 『神と仏に祈る山─美作の古刹 木山寺寺社史料のひらく世界』中山一麿編 | 2016 | ||
| 木山寺所蔵の日光院・増長院旧蔵聖教と真躰房無動 | 柏原康人、中山一麿 | 法蔵館 | 『神と仏に祈る山─美作の古刹 木山寺寺社史料のひらく世界』中山一麿編 | 2016 | ||
| 狐とお稲荷さん | 山崎淳 | 法蔵館 | 『神と仏に祈る山─美作の古刹 木山寺寺社史料のひらく世界』中山一麿編 | 2016 | ||
| 公家の学問と五山 | 堀川貴司 | 中世文学会 | 『中世文学』 | 61 | 2016 | |
| 五山文学における画賛 | 堀川貴司 | 檜書店 | 『観世』 | 平成28年8月号 | 2016 | |
| 宇田栗園と漢詩 | 新稲法子 | 和漢比較文学会 | 『和漢比較文学』 | 57 | 2016 | ○ |
| 如亭はなにを食べたのか――『詩本草』の笋と閉甕菜―― | 新稲法子 | 太平書屋 | 『太平詩文』 | 70 | 2016 | |
| 漢詩で旅する淀川――『淀川両岸一覧』の漢詩―― | 新稲法子 | 枚方市立中央図書館市史資料室 | 『枚方市史年報』 | 19 | 2017 | |
| 唐宋古文の幕末・明治 ― 林鶴梁の作文論を中心に | 山本嘉孝 | 勉誠出版 | 『幕末・明治 移行期の思想と文化』前田雅之、青山英正、上原麻有子編 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 近世漢詩に描かれた壬辰戦争 | 合山林太郎 | 勉誠出版 | 『近世日本の歴史叙述と対外意識』井上泰至編 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 中国・西安で日本漢文学研究のグローバル化について考える―第8回和漢比較文学会海外特別例会発表についての報告― | 合山林太郎 | 二松学舎大学東アジア学術総合研究所・日本漢文教育研究推進室実施委員会 | 『雙松通訊』 | 21 | 2016 | |
| 二五〇年前の奄美の自然 | 高津孝 | 北斗書房 | 『生物多様性と保全~奄美群島を例に~』 | (下)水圏・人と自然 編 | 2016 | |
| 宋以前の文人からみた南方植物とその文化 | 久保輝幸 | 北海道大学出版会 | 『「中尾佐助照葉樹林文化論」の展開 : 多角的視座からの位置づけ』山口裕文、金子務、大形徹、大野朋子編 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 伝統の古典菊 | 平野恵 | 古今書院 | 『人と植物の文化史』 | 2017 | ||
| 洋学者・柴田収蔵と江戸の本屋 | 平野恵 | 勉誠出版 | 『医学・科学・博物 東アジア古典籍の世界』 | 2020 | ||
| 薬史による語誌-薬味と料理 | 真柳誠 | 日本薬史学会 | 『薬史学雑誌』 | 51巻1号 | 2016 | |
| 医食同源の由来:古典籍にみる論理と歴史 | 真柳誠 | 世論時報社 | 『漢方と最新治療』 | 25巻3号 | 2016 | |
| 現代中国針灸学の形成に与えた日本の影響 | 真柳誠 | 新日本医師協会 | 『医学評論』 | 116号 | 2016 | |
| 韓國國立中央圖書館の古醫籍書誌(三) | 真柳誠 | 茨城大学人文学部 | 『茨城大学人文学部紀要 人文コミュニケーション学科論集』 | 21号 | 2016 | |
| 正常な舌象の歴史的な認識過程とその 問題の検討 | 梁嵘 | 国際日本文化研究センター | 『日本研究』 | 53 | 2016 | |
| Landscape-style Maps in Early Modern China: Maps and the Representation of Historical Geography | OSAWA Akihiro | 東洋文庫 | Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko | No.74 | 2017 | |
| 書評 潘光哲『晩清士人的西学閲読史(一八三三~一八九八)』 | 小野泰教 | 中国社会文化学会 | 『中国――社会と文化』 | 第31号 | 2016 | |
| 古典に見る茶の効能 | 岩間眞知子 | 静岡産業大学O-CHA学研究センター | 『O-CHA学』 | 第8号 | 2016 | |
| 日中交流から見た栄西 | 岩間眞知子 | 日中言語文化出版社 | 『一衣帯水』張驎声・大形徹編 大阪府立大学人間社会学部・張驎声研究室内 一衣帯水研究会 | 玄号(日中対訳) | 2016 | |
| 茶と医薬―神農と陸羽 | 岩間眞知子 | 斯文会 | 『斯文』 | 130号 | 2017 | |
| 日本と中国の蠟茶と香茶 | 岩間眞知子 | 茶の湯文化学会 | 『茶の湯文化学』 | 第27号 | 2017 | |
| 「主ある詞」と本歌取り | 小山順子 | 和歌文学会 | 『和歌文学研究』 | 112 | 2016 | ○ |
| 万葉集仙覚校訂本のはじまり―仙覚寛元本の復元に挑む | 田中大士 | 笠間書院 | 『萬葉写本学入門』 | 2016 | ||
| 『延喜式』」制以前の伊勢神宮―8~9世紀の内宮と外宮をめぐって― | 小倉慈司 | 思文閣出版 | John Breen編『変容する聖地 伊勢』 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 欽明期の王権と出雲 | 仁藤敦史 | 出雲古代史研究会 | 『出雲古代史研究』 | 26 | 2016 | |
| 王統譜の成立と陵墓 | 仁藤敦史 | 思文閣出版 | 『世界遺産と天皇陵古墳を問う』今尾文昭、高木博志編 | 【図書論文】 | 2017 | |
| 『延喜式』に見える古代の漬物の復元 | 土山寛子、峰村貴央、五百藏良、三舟隆之 | 東京医療保健大学 | 『東京医療保健大学紀要』 | 11 | 2016 | ○ |
| 律令制下の交易と交通 | 荒井秀規 | 吉川弘文館 | 『日本古代の交通・交流・情報 2 旅と交易』舘野和己、出田和久編 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 詔勅官符と式条文 | 早川万年 | 吉川弘文館 | 『日本歴史』 | 817 | 2016 | ○ |
| 『日本語歴史コーパス』の現状と展望 | 小木曽智信 | 明治書院 | 『國語と國文學』 | 93 (5) | 2016 | |
| 近世上方における二段活用の一段化とその後の展開 | 村上謙 | 明治書院 | 『國語と國文學』 | 93 | 2016 | |
| 近世上方語研究における研究手法について | 村上謙 | 武蔵野書院 | 『近代語研究』 | 19 | 2016 | |
| 「人情本コーパス」の表記情報アノテーション | 藤本灯、高田智和 | 勉誠出版 | 『漢字字体史研究』 | 2 | 2016 | |
| 「人情本コーパス」の設計と構築 | 藤本灯、北﨑勇帆、市村太郎、岡部嘉幸、小木曽智信、高田智和 | 国立国語研究所 | 『国立国語研究所論集』 | 12 | 2017 | ○ |
| Migrations et métamorphose des formes et savoirs dans la cartographie œcuménique. Europe - Asie, XIIIe-XVIIe siècle | Angelo Cattaneo | Actes Sud | Besse, Jean-Marc et Tiberghien, | 【図書論文】 | 2016 | |
| 『四庫全書』などの全文データから明らかになること――漢語の出典確認の可能性をめぐって―― | 陳力衛 | 明治書院 | 『日本語学』 | 第458号 35-10 | 2016 | ○ |
| Sacred Art in an Age of Mechanical Reproduction: The Salus Populi Romani Madonna inthe World | Mia Mochizuki | Kyoto University Press | Sacred and Profane in Early Modern Art | 2016 | ||
| グローバルな眼:徳川家《万国絵図屏風》における場所の認識 | Mia Mochizuki | 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部美術史研究室 | 『美術史論叢』 | 第32号 | 2016 | |
| A Global Eye: The Perception of Place in a Pair of Tokugawa World Map Screens | Mia Mochizuki | 国際日本文化研究センター | The Japan Review | 29 | 2017 | ○ |
| Colonialism and Catholicism in Asia: A Comparison of the Relationship between An Chunggŭn, José Rizal, and the Catholic Church | Franklin Rausch | Kyohoesa yŏn’gu [Research Journal of Korean Church History] | 48 | 2016 | ○ | |
| Suffering History: Comparative Christian Theodicy in Korea. | Franklin Rausch | Academia Koreana, Keimyung University | Acta Koreana | 19(1) | 2016 | ○ |
| 近代日本のカトリック史とカトリック教育 | 川村信三 | 教文館 | 『近代日本のキリスト教と女子教育』 | 【図書論文】 | 2016 | |
| 風俗史から見た現代日本のキリスト教 | 井上章一 | 国際基督教大学アジア文化研究所 | 『アジア文化研究. 別冊』 | 21 | 2016 | |
| 国立情報学研究所における研究用データセットの共同利用 | 大山敬三、大須賀智子 | 科学技術振興機構 | 『情報管理』 | 59(2) | 2016 | ○ |
| ウェブアノテーションを用いた仮想コレクション定義の試み-二つの「幸田文庫」を事例に | 林正治、夏目琢史、松田訓典、山本和明、赤木完爾 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2016論文集』 | 2016 | ○ | |
| Cross-Language Record Linkage by Exploiting Semantic Matching of Textual Metadata | Yuting Song, Taisuke Kimura, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda | データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM)2017実行委員会 | 『第9回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2016)論文集』 | 2017 | ||
| 異言語の浮世絵データベースにおける描写的作品名に対応した同一作品の同定手法の提案 | 木村泰典, Yuting Song, Biligsaikhan Batjargal, 木村文則, 前田亮 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2016論文集』 | 2016 | ||
| Proper Noun Recognition in Cross-Language Record Linkage by Exploiting Transliterated Words | Yuting Song, Taisuke Kimura, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda | Asian Language Processing (IALP)(Tainan, Taiwan) | In Proceedings of the 20th International Conference on Asian Language Processing (IALP 2016) | 2016 | ||
| Cross-Language Record Linkage using Word Embedding driven Metadata Similarity Measurement | Yuting Song, Taisuke Kimura, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda | International Semantic Web Conference (ISWC 2016)(Kobe, Japan) | In Proceedings of the 15th International Semantic Web Conference (ISWC 2016) Posters and Demonstrations Track | 2016 | ||
| Identifying the Same Ukiyo-e Prints from Databases in Dutch and Japanese | Taisuke Kimura, Yuting Song, Biligsaikhan Batjargal, Fuminori Kimura, and Akira Maeda | DIGITAL HUMANITIES 2016(Krakow, Poland) | In Conference Abstracts of Digital Humanities 2016 | 2016 | ||
| Unusual Rainbow and White Rainbow – A new auroral candidate in oriental historical sources | Hayakawa H, ISOBE H, Kawamura AD, Tamazawa H, Miyahara H, Kataoka R | Oxford University Press | Pablications of the Astronomical Society of Japan | Volume 68, Issue 3 | 2016 | ○ |
| East Asian observations of low-latitude aurora during the Carrington magnetic storm | Hayakawa, H., K. Iwahashi, H. Tamazawa, H. Isobe, R. Kataoka, Y. Ebihara, H. Miyahara, A. D. Kawamura, and K. Shibata | Oxford University Press | Pablications of the Astronomical Society of Japan | Volume 68, Issue 6 | 2016 | ○ |
| The earliest drawings of datable auroras and a two-tail comet from the Syriac Chronicle of Zuqnin | Hayakawa, H., Y. Mitsuma, Y. Fujiwara, A. D. Kawamura, R. Kataoka, Y. Ebihara, S. Kosaka, K. Iwahashi, H. Tamazawa, and H. Isobe | Oxford University Press | Pablications of the Astronomical Society of Japan | Volume 69, Issue 2 | 2017 | ○ |
| Historical space weather monitoring of prolonged aurora activities in Japan and in China | Kataoka, R., H. Isobe, H. Hayakawa, H. Tamazawa, A. D. Kawamura, H. Miyahara, K. Iwasaki, K. Yamamoto, M. Takei, T. Terashima, H. Suzuki, Y. Fujiwara, and T. Nakamura | AGU | Space Weather | 15(2) | 2017 | ○ |
| 林羅山と江戸初期の出版文化 | ピーター・コーニツキー | 勉誠出版 | 『書物学』 | 第12巻 | 2018 | |
| 「烏丸本徒然草」序説 | 佐々木孝浩 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 第12巻 | 2018 | |
| 不思議な装訂の古活字版 | 高木浩明 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 第12巻 | 2018 | |
| 東アジア印刷史上にみる「活字印刷」の意義 | 入口敦志 | 勉誠出版 | 『書物学』 | 第12巻 | 2018 | |
| 江戸時代の「占(うら)」を垣間見る―占術書の二五〇年 | マティアス・ハイエク | 勉誠出版 | 『書物学』 | 第12巻 | 2018 | |
| 境界の鳥―ニワトリをめぐる信仰と伝説― | 小池淳一 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 44号 | 2018 | |
| 明治41年盛岡巡啓における南部家別邸の空間構成としつらい | 赤澤真理・千葉映穂・宮彩香 | 日本建築学会 | 『建築歴史・意匠』 | 2017 | ||
| 建築空間の境界と打出の装束 ――附・宮内庁書陵部蔵『女房装束打出押出事』翻刻―― | 赤澤真理 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 44号 | 2018 | |
| 建築史の中の『源氏物語』―同時代の住宅像と考証学のあいだ― | 赤澤真理 | お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 | 『比較日本学教育研究部門研究年報』 | 14 | 2018 | |
| 渡海の絵巻―いけのや文庫蔵『御曹司島渡り』― | 齋藤真麻理 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 44号 | 2018 | |
| 近世文学と大津絵 | 佐藤悟 | きょうと視覚文化振興財団 | 『美術フォーラム 21』 | 36 | 2017 | ○ |
| 十九世紀江戸文学における作者と絵師、版元の関係 | 佐藤悟 | 勉誠出版 | 『古典文学の常識を疑う』 | 2017 | ○ | |
| 会田安明の数学思想 | 小川束 | 日本評論社 | 『数学文化』 | 28号 | 2017 | |
| 道成寺建立縁起の展開と来歴 | 大橋直義 | 和歌山県立博物館編 | 『特別展図録 道成寺と日高川―道成寺縁起と流域の宗教文化―』 | 2017 | ||
| 紀州地域学というパースペクティヴ―根来寺と延慶本、平維盛粉河寺巡礼記事について | 大橋直義 | 勉誠出版 | アジア遊学211『根来寺と延慶本『平家物語』―紀州地域の寺院空間と書物・言説』大橋直義編 | 2017 | ||
| 中世文学研究と「歴史学」の交錯 | 大橋直義 | 勉誠出版 | 『古典文学の常識を疑う』松田浩・上原作和・佐谷眞木人・佐伯孝弘編 | 2017 | ||
| 道成寺文書概観―特に「縁起」をめぐる資料について― | 大橋直義 | 国文学研究資料館 | 『国文研ニューズ』 | 49 | 2017 | |
| 建部賢弘『研幾算法』による弓形の弧長導出式の復元について | 佐藤賢一 | 電気通信大学 | 『電気通信大学紀要』 | 30巻1号 | 2018 | |
| 上方文藝への招待(6) 第二回日本漢文学総合討論「“漢文学”は東アジアにおいてどう語られてきたか?」報告 | 山本嘉孝 | 上方文藝研究の会 | 『上方文藝研究』 | 14号 | 2017 | |
| 松下忠先生の『江戸時代の詩風詩論』と江戸時代の漢文学研究の現在 | 合山林太郎 | 近役韓文学会 | 『漢文学論集』 | 48 | 2017 | |
| 正岡子規が読んだ江戸漢詩詞華集―『才子必誦 崑山片玉』及び『日本名家詩選』について― | 合山林太郎 | 慶應義塾大学藝文学会 | 『藝文研究』 | 113号 | 2017 | |
| The Local and the Global in Early Modern Japanese Kanshi | マシュー・フレーリ、山本嘉孝、合山林太郎 | American Association of Teachers of Japanese | Japanese Language and Literature | 2018 | ||
| 官人紀百継について | 中村光一 | 史聚会 | 『史聚』 | 50 | 2017 | |
| 古代東アジアにおける「神」信仰 | 小倉慈司 | 勉誠出版 | 『日本古代交流史入門』 | 2017 | ||
| 倭国における政治空間の成立-都市と王権儀礼- | 仁藤敦史 | 唐代史研究会 | 『唐代史研究』 | 20 | 2017 | |
| 律令官衙財政の基本構造―民部省・主計寮の職掌を中心に― | 神戸航介 | 史学会 | 『史学雑誌』 | 第126編第11号 | 2017 | |
| 『延喜式』写本系統の基礎的研究―巻五を中心に― | 小倉慈司 | 勉誠出版 | 新川登亀男編『日本古代史の方法と意義』 | 2018 | ||
| 文献にみる須恵器 | 荒井秀規 | 雄山閣出版 | 『季刊考古』 | 142 | 2018 | |
| 九世紀の仕丁制と日功 | 堀部猛 | 勉誠出版 | 新川登亀男編『日本古代史の方法と意義』 | 2018 | ||
| 勢多章甫と勢多家関係図書 | 相曽貴志 | 宮内庁書陵部 | 『書陵部紀要』 | 69 | 2018 | |
| 平安中後期の民部省勘会―正税帳を中心に― | 神戸航介 | 東京大学日本史学研究室・古代史研究会 | 『史学論叢』佐藤信先生退職記念号 | 2018 | ||
| 『延喜式』土御門本と近衛本の検討―巻五を中心に― | 小倉慈司 | 吉川弘文館 | 佐藤信編『史料・史跡と古代社会』 | 2018 | ||
| 『延喜式』にみえるアワビに関する復元資料-一人分の長鰒貢納量- | 清武雄二 | 国立歴史民俗博物館 | 『歴博』 | 204 | 2017 | |
| 古代の美濃・飛騨と壬申の乱 | 早川万年 | 岐阜県博物館 | 岐阜県立博物館特別展図録『壬申の乱の時代』 | 2017 | ||
| 古代における長鰒(熨斗鰒)製造法の研究 : 加工実験・成分分析による実態的考察 | 清武雄二 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 209 | 2018 | ○ |
| 古代における「糖(飴)」の復元 | 三舟隆之、橋本梓 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 209 | 2018 | ○ |
| 訓点資料の加点情報計量のためのデータ構造―国立国語研究所蔵「尚書(古活字版)」を対象として― | 林昌哉・田島孝治・堤智昭・高田智和・小助川貞次 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2017論文集』 | 2017 | ||
| ヲコト点データベースと検索システムの試作 | 堤智昭・土井裕絵・田島孝治・高田智和・小助川貞次 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2017論文集』 | 2017 | ||
| Internationalization of the Japanese Language in Interwar Period Japan (1920-1940) by Foreign Missionaries and Writers | 郭 南燕 | 国際日本文化研究センター | 『世界の日本研究2017:国際的視野からの日本研究』 | 2017 | ||
| Shores of Vespucci: A historical research of Amerigo Vespucci’s life and contexts in collaboration with Francisco Contente Domingues | Cattaneo, Angelo | Peter Lang | History & Political Science | 12 | 2017 | |
| Becoming a Multicultural Church in the Context of Neo-Nationalism: The New Challenges Facing Catholics in Japan, | Mark R. Mullins | Wipf and Stock | “Scattered & Gathered”: Catholics in Diaspora. Edited by William Cavanaugh and Michael Budde | 2017 | ||
| ジョルジュ結城弥平次 | 滝澤修身 | 宮帯出版 | 五野井隆史編『キリシタン大名』 | 2017 | ||
| The Society of Jesus and Korea: A Historiographical Essay. | Jieun Han and Franklin Rausch | BrillOnline Reference Works | In Jesuit Historiography Online | 2017 | ||
| Recognition and Transliteration of Proper Nouns in Cross-Language Record Linkage by Constructing Transliterated Word Pairs | Yuting Song, Biligsaikhan Batjargal, and Akira Maeda | Chinese & Oriental Languages Information Processing Society | “International Journal of Asian Language Processing” | Vol. 27, No. 2 | 2017 | ○ |
| 在外日本美術品のデジタル画像共有化をめぐって 絵本に注目して | 赤間 亮 | 醍醐書房 | 『美術フォーラム21』 | 35 | 2017 | |
| Searching for the 27-day solar rotational cycle in lightning events recorded in old diaries in Kyoto from the 17th to 18th century | Hiroko Miyahara, Yasuyuki Aono, Ryuho Kataoka | IST NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | Ann. Geophys. | 35 | 2017 | ○ |
| Inclined zenith aurora over Kyoto on 17 September 1770: Graphical evidence of extreme magnetic storm | Kataoka, R., and K. Iwahashi | AGU | Space Weather | Volume15,Issue10 | 2017 | ○ |
| Solar 27-day rotational period detected in a wide-area lightning activity in Japan | Miyahara H., Higuchi C., Terasawa T., Kataoka R., Sato M., Takahashi Y. | ANGEO Communicates | 35 | 2017 | ○ | |
| 古代甘味料あまつらの復原 | 神松幸弘/入口敦志 | 雄山閣 | 『環太平洋文明研究』 | 2 | 2017 | ○ |
| 縄文人の資源利用と土地利用に関する 生態学的研究 | 神松幸弘 | 雄山閣出版 | 『環太平洋文明研究』 | 第2号 | 2018 | |
| 寛政・享和期における知と奇の位相─諸国奇談と戯作の虚実─ | 木越俊介 | 古典ライブラリー | 『日本文学研究ジャーナル』 | 7 | 2018 | |
| 霊元院の古今和歌集講釈とその聞書―正徳四年の相伝を中心に | 海野圭介 | 勉誠出版 | 『文化史のなかの光格天皇 朝儀復興を支えた文芸ネットワーク』 | 2018 | ||
| 寛政期新造内裏における南殿の桜―光格天皇と皇后欣子内親王 | 盛田帝子 | 勉誠出版 | 『文化史のなかの光格天皇 朝儀復興を支えた文芸ネットワーク』 | 2018 | ||
| 海を渡った禅-欧米「ZEN」の誕生 | ダヴァン・ディディエ | サンガジャパン | 『別冊サンガジャパン、「Zen」』 | 5 | 2019 | |
| Between the Mountain and the City – Ikkyū Sōjun and the Blurred Border of Awakening | ダヴァン・ディディエ | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 2 | 2019 | ○ |
| 禅と俳句 | ダヴァン・ディディエ | 総合研究大学院大学 | 『特別講義』 | 38 | 2019 | |
| 『兼修禅』から『純粋禅』を再考する ― 中世禅の再考≪10≫ | ダヴァン・ディディエ | 中外日報社 | 『中外日報』 | 2018 | ||
| 「日本の演劇は甚だ不完全」―演劇改良の発想― | 矢内賢二 | 新典社 | 『明治、このフシギな時代』 | 3 | 2019 | |
| 「仁王の物真似と見得」再説・補説 | 武井協三 | 芸能史研究 | 『芸能史研究』 | 223 | 2018 | ○ |
| デジタル化時代の歌舞伎研究―歌舞伎・浄瑠璃と出版物― | 高橋則子 | 歌舞伎学会 | 『歌舞伎 研究と批評』 | 62 | 2019 | |
| 「日伊国交150周年のためにイタリアの劇場で上演された能公演について」 Caleidoscopio del nō. Gli spettacoli delle celebrazioni per i 150 anni dei rapporti diplomatici Giappone-Italia in Bi no michi. La via della Bellezza. Esplorazioni nella cultura giapponese per i 150 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, Venezia, |
Ruperti, Bonaventura | Articolo su libro | Polo Museale del Veneto | 1 | 2018 | |
| Guerrieri sulle scene del teatro giapponese | Ruperti, Bonaventura | Silvana editoriale | Il samurai. Da guerriero a icona La Collezione Morigi e altre recenti acquisizioni del MUSEC |
2018 | ||
| Riflessioni sulla scrittura in Izumi Kyōka tra ispirazione, artificio e fascinazione | Ruperti, Bonaventura | Orizzonti giapponesi: ricerche, idee, prospettive | 2018 | |||
| Solar rotational cycle in lightning activity in Japan during the 18–19th Centuries | Hiroko Miyahara, Ryuho Kataoka, Takehiko Mikami, Masumi Zaiki, Junpei Hirano, Minoru Yoshimura, Yasuyuki Aono, and Kiyomi Iwahashi | ANGEO Communicates | 36 | 2018 | ○ | |
| 異分野連携研究における研究基盤データ構築への市民参加の可能性 ー市民参加型ワークショップ「古典オーロラハンター」を事例としてー | 岩橋清美・玉澤春史 | 兵庫県立大学自然・環境科学研究所天文科学センター | 『stars and Galaxies』 | 1巻 | 2018 | |
| Image Processing Scheme for Archiving Epigraph | Hideyuki Uesugi, Masayuki Uesugi | 2018 International Conference on Digital Heritage 2018 | 3 | 2018 | ○ | |
| 歴史資料を活用した減災・気候変動適応に向けた新たな研究分野の創成 | 田村誠 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 11 | 2019 | |
| 国文学研究資料館蔵歴史資料のデータベースと資料の所在情報 | 西村慎太郎 | 吉川弘文館 | 『日本歴史』 | 848 | 2019 | |
| 常陸国の調布墨書銘 | 堀部 猛 | 筑波大学日本史談話会 | 『日本史学集録』 | 39 | 2018 | |
| 古代文献史料本文研究の課題―『延喜式』を中心に― | 小倉慈司 | 九州史学研究会 | 『九州史学』 | 181 | 2018 | |
| 構造化記述されたテクストの基盤整備に向けて:延喜式のTEIマークアップを事例に | 後藤 真、小風 尚樹、橋本 雄太、小風 綾乃、永崎 研宣 | 『じんもんこん2018論文集』 | 2018 | 2018 | ||
| 『延喜式』に見える古代の酢の製法 | 小嶋 莉乃、小牧 佳代、峰村貴央、五百藏良、三舟隆之 | 東京医療保健大学 | 『東京医療保健大学紀要』 | 13(1) | 2019 | |
| 古代における「豉」の復元 | 小松本里菜、今野里咲、峰村貴央、西念幸江、三舟隆之 | 東京医療保健大学 | 『東京医療保健大学紀要』 | 13(1) | 2019 | |
| 加点情報の再構成 | 高田智和・田島孝治・堤智昭 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2018-CH-117(2) | 2018 | |
| 資料画像公開・利用の国際化と高度化の取り組み : 「日本語史研究資料[国立国語研究所蔵]の事例 | 高田智和・福山雅深・堤智昭・小助川貞次 | 国立国語研究所論集編集委員会 | 『国立国語研究所論集』 | 15 | 2018 | |
| 尚書(古活字版)の訓点データの基礎計量 | 林昌哉・田島孝治・高田智和 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2018-CH-118(7) | 2018 | |
| 文字情報と図版情報を有する近世版本コーパスの構築とその応用 | 間淵洋子 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2018論文集』 | 2018 | ||
| 訓点資料の移点ツールとデータ構成への応用 | 田島孝治・林昌哉 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2018論文集』 | 2018 | ||
| ヲコト点データベースの改良と書誌情報の追加 | 堤智昭・山田貴弘・萩原泰地・田島孝治・小助川貞次 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2018論文集』 | 2018 | ||
| 「宣教師の日本語文学」という新しい分野の開拓 | 郭南燕 | 「書物・出版と社会変容」研究会 | 『書物・出版と社会変容』 | 22 | 2019 | |
| 延喜式(平安時代篇) | 小倉慈司(佐藤信 他) | 同成社 | 『古代史料を読む 下 平安王朝篇』 | 2018 | ||
| 死亡報告と弔使派遣の展開 | 稲田奈津子(古瀬奈津子 他) | 竹林舎 | 古瀬奈津子編『古代文学と隣接諸学5 律令国家の理想と現実』 | 2018 | ||
| 官社制度の展開 | 早川万年 | 竹林舎 | 岡田莊司編『古代文学と隣接諸学7 古代の信仰・祭祀』 | 2018 | ||
| 神戸の存在形態と神社経済 | 小倉慈司 | 竹林舎 | 岡田莊司編『古代文学と隣接諸学7 古代の信仰・祭祀』 | 2018 | ||
| 延喜式 | 小倉慈司(藤尾慎一郎 他) | 吉川弘文館 | 『ここが変わる!日本の考古学―先史・古代史研究の最前線』 | 2019 | ||
| 宣教師ホイヴェルスの日本語文学―「世界文学」の精神を考える | 郭南燕 | 勉誠出版 | 伊藤守幸、岩淵令治編『グローバル・ヒストリーと世界文学 日本研究の軌跡と展望』 | 2018 | ||
| 身体の苦しみから魂の救済へ:遠藤周作の『海と毒薬』と『悲しみの歌』 | 郭南燕 | 臨川書店 | 牛村圭編『文明と身体』 | 2018 | ||
| Dōgen’s Religious Discourse and Hieroglossia | ジャン=ノエル・ロベール | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 3 | 2020 | ○ |
| A Forgotten Aesop: Shiba Kōkan, European Emblems, and Aesopian Fable Reception in Late Edo Japan | イフォ・スミッツ | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 3 | 2020 | ○ |
| From “Pointing Straight to the Human Mind” to “Pointing Round to the Human Mind” | 芳澤勝弘 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 3 | 2020 | ○ |
| The kōan in Japanese Society at the Beginning of the Early Modern Period: Kana hōgo and kanna-zen | ディディエ・ダヴァン | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 3 | 2020 | ○ |
| Language and Representation with ōgi and uchiwa Fans: Considering “Applied Knowledge” in the Early Modern Period | 鈴木健一 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 3 | 2020 | ○ |
| Medieval Buddhism and Music: Musical Notation and the Recordability of the Voice | 猪瀬千尋 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 3 | 2020 | ○ |
| 歴史と物語の交点―『太平記』の射程― | 兵藤裕己 | 響文社 | 『アナホリッシュ国文学』 | 8 | 2019 | ○ |
| 恋歌のポストモダンー『万葉集』から『源氏物語』へ | 兵藤裕己 | 青土社 | 『現代思想』 | 47 | 2019 | ○ |
| 中世歴史学と「物語」史観について | 兵藤裕己 | 古典ライブラリー | 『日本文学研究ジャーナル』 | 11 | 2019 | ○ |
| Corps et paroles chez Mishims,in Corps et Message | マチルデ・マストランジェロ | Philippe Picquier | Corps et message,De la structure de la traduction et de l"adaptation | 2019 | ○ | |
| Variations of the yamauba Figure in Murakumo no mura no monogatari (1987) by Saegusa Kazuko | ダニエラ・モーロ | Kervan | International Journal of Afro-Asiatic Studies | 23 | 2019 | ○ |
| La danza giapponese dalle origini al teatro nõ, Estetica nell"intreccio tra parola,musica e gesto | ボナベンツゥーラ・ルペルティ | Bellezza in fiore, Colori e parole nell"estetica asiatica, Beauty in flower, Colors and words in the Asian aesthetic | 2020 | ○ | ||
| 平安朝文人における過去と現在の意識—漢詩集序をテクスト遺産言説の一例として | エドアルド・ジェルリーニ | 国文学研究資料館 | 『第43回国際日本文学研究集会会議録』 | 2020 | ○ | |
| マリオ・マレガ文庫蔵黒本『眉間尺』 | 山下則子 | 三弥井書店 | 『在外絵入り本 研究と目録』 | 2019 | ○ | |
| Cultura letteraria del periodo Kamakura: transizione e impermanenza | 鷺山郁子 | Bio Guida edizioni | Lo Zen nella cultura giapponese il maestro Dogeneil suo tempo | 2019 | ○ | |
| Enlightened and Enlightening Plants in No Theatre | クラウディア・イアツェッタ | Firenze University Press | Trajectories. Selected papers in East Asian studies | 2019 | ○ | |
| Extraction of Distinctive Keywords and Articles from Untranscribed Historical Newspaper Images | Sora Ito and Kengo Terasawa | Proceedings Volume 11515, International Workshop on Advanced Imaging Technology (IWAIT) 2020 | 2020 | ○ | ||
| Recognition of Historical Japanese Characters Based on Subcharacter Components | Takehiro Nakano and Kengo Terasawa | The 26th International Workshop on Frontiers of Computer Vision (IW-FCV 2020) | ○ | |||
| 雉尾攷―日本書紀にみる赤気に関する一考察 | 片岡龍峰、山本 和明、藤原 康徳、塩見 こずえ、國分 亙彦 | 総合研究大学院大学文化科学研究科 | 『総研大文化科学研究』 | 16 | 2020 | ○ |
| Fan-shaped aurora as seen from Japan during a great magnetic storm on 11 February 1958 | 片岡龍峰 | EDP Sciences | J. Space Weather Space Clim. | 9 | 2019 | ○ |
| A watercolor painting of northern lights seen above Japan on 11 February 1958 | 片岡龍峰 | EDP Sciences | J. Space Weather Space Clim. | 9 | 2019 | ○ |
| 原子力災害地域の歴史を未来へ紡ぐ -大字誌という方法- | 西村慎太郎 | 跡見学園女子大学 | 『跡見学園女子大学地域交流センターブックレット』 | 1 | 2020 | |
| 古代の甘味「甘葛」の原料に関する考察 | 神松幸弘、入口敦志 | 雄山閣 | 『環太平洋文明研究』 | 4 | 2020 | ○ |
| 遺稿集の季節-二十世紀前半の日本の言説編制 | 谷川惠一 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』 | 255 | 2021 | |
| 律令官制の成立 | 相曽 貴志 | 吉川弘文館 | 『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』 | 2020 | ||
| 左近衛権少将藤原房雄の九州下向 | 中村 光一 | 岩田書院 | 『古代史論聚』 | 2020 | ||
| 古代王権の成立 | 仁藤 敦史 | 吉川弘文館 | 『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』 | 2020 | ||
| 王宮と古代王権・官僚制 | 仁藤 敦史 | 雄山閣出版 | 『王宮と王都 講座・畿内の考古学Ⅲ』 | 2020 | ||
| 複都制と難波宮官人 | 仁藤 敦史 | 同成社 | 『難波宮と古代都城』 | 2020 | ||
| 壬申の乱と天皇制の成立 | 早川 万年 | 吉川弘文館 | 『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』 | 2020 | ||
| 津田左右吉の記紀研究の始まり | 早川 万年 | 岩田書院 | 『古代史論聚』 | 2020 | ||
| 日本営繕令と律令軍制 | 古田 一史 | 山川出版社 | 『日本古代律令制と中国文明』 | 2020 | ||
| 古代「山ノ荘」の景観-山と川と神仏- | 堀部 猛 | 土浦市立博物館 | 『第42回特別展図録 東城寺と「山ノ荘」』 | |||
| 東城寺経塚出土経筒の再検討 | 萩谷 良太、堀部 猛 | 土浦市立博物館 | 『第42回特別展図録 東城寺と「山ノ荘」』 | ○ | ||
| 古代史はLGBTを語れるか | 三上 喜孝 | 吉川弘文館 | 『恋する日本史』 | 2021 | ||
| 日本古代の陰陽道と神祇信仰・仏教 | 山口 えり | 名著出版 | 『新陰陽道叢書 第一巻 古代』 | 2020 | ||
| 『延喜式』 | 小倉 慈司 | 吉川弘文館 | 『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』 | 2020 | ||
| 『延喜式』巻九・一〇の写本系統 | 小倉 慈司 | 同成社 | 『古代東アジア史料論』 | 2020 | ||
| 改元はいつ行われるのか? | 小倉 慈司 | 国立歴史民俗博物館 | REKIHAKU | 2 | 2021 | |
| ジェンダー史研究事始 | 三上 喜孝 | 国立歴史民俗博物館 | REKIHAKU | 1 | 2020 | |
| 米国陸海軍日本語学校の漢字教材“Kanji book” | 高田智和 | 勉誠出版 | 『日本語文字論の挑戦―表記・文字・文献を考えるための17章』 | 2021 | ||
| 漢字 | 高田智和 | 三省堂 | 『明解日本語学辞典』 | 2021 | ||
| 訓点資料 | 高田智和 | 三省堂 | 『明解日本語学辞典』 | 2021 | ||
| 訓読 | 高田智和 | 三省堂 | 『明解日本語学辞典』 | 2021 | ||
| 重箱読み・湯桶読み | 高田智和 | 三省堂 | 『明解日本語学辞典』 | 2021 | ||
| 福澤諭吉における図入りテキストに関する調査研究 ――『世界国尽』を中心に―― | ハサン・カマル・ハルブ | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 図と言葉による意匠―「武具訓蒙図彙」と「女用訓蒙図彙」 | 加茂 瑞穂 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 『仮名本朝孝子伝』翻刻 | 勝又 基 | 東京堂出版 | 『仮名草子集成』 | 64 | 2020 | |
| 『仮名本朝孝子伝』解題 | 勝又 基 | 東京堂出版 | 『仮名草子集成』 | 64 | 2020 | |
| 『訓蒙図彙』の言葉と図像 | 勝又 基 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 日本正教会刊行『教会初学読本』挿絵にみる東と西の出会い | 山崎 佳代子 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 中村正直の語彙 | 木村 一 | 朝倉書店 | 『シリーズ日本語の語彙5 近代の語彙(1)一四民平等の時代一』 | 2020 | ||
| 『訓蒙図彙』寛文六年初版本から元禄版本へ――大衆化の位相をめぐって―― | 楊 世瑾 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 日中近代の翻訳語——西洋文明受容をめぐって | 陳 力衛 | 文学通信 | 金文京編『漢字を使った文化はどう広がっていたのか 東アジアの漢字漢文文化圏』東アジア文化講座2 | 2021 | ||
| はじめに ことばとイメージの文化圏 | 山田 奨治 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ||
| 『訓蒙図彙』諸本再考 | 石上 阿希 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 可視化する日本史―絵入年代記を素材に― | 木場 貴俊 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| 戦間期東アジアにおける森永製菓の新聞広告と広告戦略 | 前川 志織 | 晃洋書房 | 『文化・情報の結節点としての図像 絵と言葉でひろがる近世・近代の文化圏』 | 2021 | ○ | |
| カリフォルニア大学バークレー校所蔵 光格上皇御点『実勲詠草』解説と三条西実勲文政期和歌年表 | 盛田 帝子 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館調査研究報告』 | 41号 | 2021 | |
| A Genealogy of Saikaku’s ukiyo-zōshi | ダニエル・ストリューヴ | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| Kyokutei Bakin’s Philological Research and the Writing of Historical Narrative: Study of the Izu Islands in the Marvelous Story of the Drawn-Bow Moon | ニコラ・モラール | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| Variations on yatsushi in the ukiyo-zōshi genre: Expansion of the Classical World and Transworld Identification | 高橋明彦 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| A Japanese Commentary History of Jianghu fengyue ji: From Medieval to Early-Modern | 堀川貴司 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| On the Reception and Uses of Li Shizhen’s Classified Materia Medica (Bencao gangmu) in 17th-century Japan: Text, Categories, Pictures | マティアス・ハイエク | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| Naturalizing Li Shizhen’s Bencao gangmu in Early-modern Japan: The Cases of Honchō shokkan, Yamato honzō, and Wakan sansai zue | アニック・堀内 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| Tsukumogami emaki and Urban Spaces | 齋藤真麻理 | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | |
| 太陽黒点観測に見る近世後期の天文認識 | 岩橋清美 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 46 | 2020 | |
| 異分野融合で切り拓く歴史的オーロラ研究―オーロラ4Dプロジェクトの経験から | 岩橋清美 | 勉誠出版 | 『デジタルアーカイブ・ベーシックス3 自然史・理工系研究データの活用』 | 2020 | ||
| 文理融合で切り拓く歴史地震研究の現在;一八三〇年の京都地震を事例にしてー | 岩橋清美・大邑潤三・加納靖之 | 地方史研究協議会 | 『地方史研究』 | 405 | 2020 | |
| 近世史料にみるオーロラと人々の認識 : 文理協働による研究の成果と課題 | 磯部洋明・岩橋清美・玉澤春史 | 「書物・出版と社会変容」研究会 | 『書物出版と社会変容』 | 25 | 2020 | |
| 茨城県下の地域資料の保存をめぐる現状と課題 | 添田仁 | 地方史研究協議会 | 『地方史研究』 | 407 | 2020 | |
| 水戸藩の流行り病-文久2年(1862)の麻疹とコレラを中心にー | 添田仁 | 常陸大宮市教育委員会 | 『常陸大宮市史研究』第4号 | 2021 | ||
| 地域に遺る歴史資料の行方 -「ウィズ・コロナ」社会における歴史資料保全 | 西村慎太郎 | 績文堂出版 | 『歴史学研究』 | 1002 | 2020 | |
| 複合災害地における歴史的実践 福島県浜通りの大字誌 | 西村慎太郎 | ブックエンド | 『BIOCITY』 | 85 | 2021 | |
| 水戸市史料「大高氏記録」を用いた「やませ」の研究への活用の提案 | 宮崎将 | 『茨城大学大学院理工学研究科理学専攻 令和2年度修士論文』 | 2021 | |||
| A Study of Kawanabe Tōiku (Kyōsai)’s Ehon Taka Kagami(An Illustrated Mirror of Falconry) | 藤實久美子 | 九州大学基幹教育院 | The Journal of Hawks, Hawking Grounds, and Environment Studies | 5 | 2021 | |
| 〈私〉の言説戦略-アイロニーの日本近代- | 谷川惠一 | 総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学研究専攻 | SOKENDAI 特別講義 | 43 | 2021 | |
| 「辻󠄀」の墨書土器 − 点の数を巡って | 荒井 秀規 | 湘南考古学同好会 | 『湘南考古学同好会々報』 | 160 | 2021 | |
| 公式令の「出雲以北」と延喜主税式の「伯耆以西」 | 荒井 秀規 | 出雲古代史研究会 | 『出雲古代史研究』 | 30 | 2020 | ○ |
| 入殓・下葬仪礼复原的考察―以吐鲁番出土随葬衣物疏为中心 | 稲田 奈津子(羅亮訳、劉安志校) | 武漢大学中国三至九世紀研究所 | 『魏晋南北朝隋唐史资料』 | 41 | 2020 | ○ |
| 廃朝・廃務からみた諸司と伊勢神宮 | 井上 正望 | 吉川弘文館 | 『日本歴史』 | 865 | 2020 | ○ |
| 古代の苞苴-アラマキ・ツトの機能 | 小川 宏和 | 神奈川大学日本常民文化研究所 | 『民具マンスリー』 | 第53巻10号 | 2021 | ○ |
| 建長二年十月宣陽門院領六条殿分公事注進状の成立 : 「建久二年十月日長講堂領目録」の再検討 | 河合 佐知子、遠藤 基郎 | 鎌倉遺文研究会 | 『鎌倉遺文研究』 | 45 | 2020 | ○ |
| 『延喜式』第39巻「正親司」の史料的価値を英語圏に伝えるために : ジェンダー的視点を取り入れて | 河合 佐知子 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 228 | 2021 | ○ |
| 押小路本『即位式』と『儀式』の写本系統 | 神戸 航介 | 宮内庁書陵部 | 『書陵部紀要』 | 72 | 2021 | ○ |
| 唐賦役令継受の歴史的意義 | 神戸 航介 | 績文堂出版 | 『歴史学研究』 | 1007 | 2021 | ○ |
| 『延喜式』巻十一「太政官」校訂(稿) | 神戸 航介 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 228 | 2021 | ○ |
| 『延喜式』巻十一「太政官」現代語訳(稿) | 神戸 航介 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 228 | 2021 | ○ |
| Application of the Methodology for Structuring Historical Financial Records to a Japanese Historical Source along with Financial Information | Naoki Kokaze(National Museum of Japanese History, ed.) | The National Museum of Japanese History | Japanese and Asian Historical Resources in the Digital Age | 2021 | ○ | |
| 古代須恵器窯跡の発掘 | 酒井 清治 | ニューサイエンス社 | 『考古学ジャーナル』 | 746 | 2020 | ○ |
| 埼玉県滑川町寺谷廃寺・平谷窯跡の出土瓦について | 酒井 清治、生野 一志、鈴木 崇司 | 駒澤大学考古学研究室 | 『駒澤考古』 | 45 | 2020 | |
| 埼玉県道仏遺跡出土軟質系土器の胎土分析と出土意義 | 酒井 清治、藤根 久、鈴木 正章 | 駒沢史学会 | 『駒沢史学』 | 95 | 2021 | |
| 「弘仁式」・「貞観式」逸文集成の補訂とその考察 : 附「『本朝月令』所引「弘仁式」・「貞観式」逸文一覧」・「「弘仁式」・「貞観式」新出逸文一覧(稿)」・「弘仁式貞観式逸文集成目録(稿) | 高橋 人夢 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 228 | 2021 | ○ |
| 貼り込み形式の資料に対するフォント画像を用いたテキスト検索手法の検討 - 東京大学総合図書館所蔵『捃拾帖』を対象として | 高橋 大成、中村 覚 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2020-CH-123-1 | 2020 | |
| 歴史学と情報学のより良い協働を目指して―オープンな DH 支援ツールを用いたオスマン・トルコ語文書群のデータ整理の一事例― | 佐治 奈通子、中村 覚 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2019-CH-120-11 | 2019 | |
| 源氏物語本文研究支援システム「デジタル源氏物語」の開発におけるIIIF・TEIの活用 | 中村 覚、田村 隆、永崎 研宣 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2020-CH-124-2 | 2020 | |
| Cultural Japanの構築におけるジャパンサーチ利活用スキーマの活用 | 中村 覚 | デジタルアーカイブ学会 | 『デジタルアーカイブ学会誌』 | 4-4 | 2020 | |
| 法帖画像アーカイブを研究資源として活用するために | 成田 健太郎、中村 覚、水野 遊大 | 書学書道史学会 | 『書学書道史研究』 | 30 | 2020 | ○ |
| 持続性と利活用性を考慮したデジタルアーカイブ構築手法の提案 | 中村 覚, 高嶋 朋子 | デジタルアーカイブ学会 | 『デジタルアーカイブ学会誌』 | 5-1 | 2021 | ○ |
| 日本史学者の要求分析に基づく歴史資料のトピック推定システムの開発 | 鳥居 克哉、中村 覚、山田 太造、稗方 和夫 | 情報処理学会 | 『第83回全国大会講演論文集』 | 2021(1) | 2021 | |
| コメント─古代王権論からみた天皇の位置づけ─ | 仁藤 敦史 | 民衆史研究会 | 『民衆史研究』 | 99 | 2020 | ○ |
| 古代の郡と郷をさぐる-下総国印旛の事例を中心に- | 仁藤 敦史 | 千葉歴史学会 | 『千葉史学』 | 76 | 2020 | |
| 五世紀史解釈の方法論をめぐって | 仁藤 敦史 | 歴史科学 | 『歴史科学』 | 242 | 2020 | ○ |
| 白村江敗戦後の倭国と新羅・唐関係-『日本書紀』対外関係記事の批判的検討- | 仁藤 敦史 | 慶北大学人文学術院 | 『東西人文』 | 14 | 2020 | ○ |
| 「万世一系」論と女帝・皇太子 : 皇統意識の転換を中心に | 仁藤 敦史 | 歴史学研究会 | 『歴史学研究』 | 1004 | 2021 | ○ |
| 古代公文書の成立前史-漢字・暦・印・文書様式- | 仁藤 敦史 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 224 | 2021 | ○ |
| 『延喜式』巻三九「正親司」現代語訳(稿) | 古田 一史 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 228 | 2021 | ○ |
| 常陸国棚島駅と「棚藻駅子」 | 堀部 猛 | 吉川弘文館 | 『日本歴史』 | 868 | 2020 | ○ |
| 日本出土の古代木簡―古代地域社会における農業経営と仏教活動― | 三上 喜孝 | 韓国木簡学会 | 『木簡と文字』 | 24 | 2020 | ○ |
| 韓国出土木簡にみえる海産物とその加工品 | 三上 喜孝 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 221 | 2020 | ○ |
| 古代日本論語木簡の特質―韓半島出土論語木簡の比較を通して― | 三上 喜孝 | 韓国木簡学会 | 『木簡と文字』 | 25 | 2021 | ○ |
| 韓国出土の文書木簡~「牒」木簡と「前白」木簡を中心に~ | 三上 喜孝 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 224 | 2021 | ○ |
| 平泉出土文字資料へのアプローチ(1)饗宴と文字 | 三上 喜孝 | 「世界遺産平泉」保存活用推進実行委員会 | 『平泉学研究年報』 | 1 | 2021 | |
| 「片節会」に関する覚書 | 三輪 仁美 | 宮内庁書陵部 | 『書陵部紀要』 | 72 | 2021 | ○ |
| 『延喜式』巻十四校訂(稿) | 三輪 仁美 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 228 | 2021 | ○ |
| 前近代の年号―決定方法とその出典、意味 | 小倉 慈司 | 明治書院 | 『日本語学』 | 39・4通巻503 | 2020 | |
| On the Reception and Uses of Li Shizhen’s Classified Materia Medica (Bencao gangmu) in 17th-century Japan: Text, Categories, Pictures | HAYEK Matthias | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 4 | 2021 | ○ |
| 友禅協会「伊達模様」の募集とその周辺―明治後期・京都における流行創出との関わり | 加茂 瑞穂 | 意匠学会 | 『デザイン理論』 | 77 | 2021 | ○ |
| 常用語の分水嶺―『漢英対照いろは辞典』の同一見出し内の複数漢字表記― | 木村 一 | 武蔵野書院 | 『近代語研究』 | 22 | 2021 | |
| 『訓蒙図彙』寛文六年初版本の下位分類の図像化―『三才図会』の引用手法をめぐって― | 楊 世瑾 | 東アジア比較文化国際会議日本支部 | 『東アジア比較文化研究』 | 19 | 2020 | ○ |
| 『訓蒙図彙』寛政版本の増補改訂――寛文六年初版本への回帰―― | 楊 世瑾 | 大東文化大学大学院外国語学研究科 | 『外国語学研究』 | 22巻 | 2020 | ○ |
| 近代科学词汇的生成及中日间往来——以词缀“-力”“-性”为主 | 陳 力衛 | 浙江工商大学出版社 | 『汉日语言对比研究论丛』 | 11 | 2020 | |
| 「農奴」概念の成立と展開 | 陳 力衛 | 成城大学 経済学会 | 『成城大学 経済研究』 | 230 | 2020 | |
| テクスト、パラテクスト、秘儀伝受―テクストを所有するとはどのような行為なのか? | 海野圭介 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』古典は遺産か? 日本文学におけるテクスト遺産の利用と再創造 | 261 | 2021 | ○ |
| Auroral zone over the last 3000 years | 片岡龍峰、中野慎也 | J. Space Weather Space Clim. | 2021(11) | 2021 | ○ | |
| Intertextuality and Corporality in Chikamatsu Monzaemon’s Shutendōji makurakotoba | Bonaventura RUPERTI | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| The Water Mirror Motif in the Noh Play Izutsu : Continuation and Variation of a Classical Theme | SAGIYAMA Ikuko | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| Physical Imitations of the Deva King Statue: Performances of Kabuki in the Seventeenth Century | TAKEI Kyōzō | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| Textual Heritage Embodied: Entanglements of Tangible and Intangible in the Aoi no ue utaibon of the Hōshō School of Noh | Edoardo GERLINI | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| Sakura Sōgorō between Kabuki and Kōdan : A Cross-Genre Genealogy | Stefano ROMAGNOLI | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| The Sound, the Body, the Classics: Nagai Kafū and Traditional Theater | Gala Maria FOLLACO | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| Sōgi’s Problem Passages : Exegetical Method and the Idea of the Text | Jeffrey KNOTT | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| The Reception and Reworking of Empress Renxiao’s Book of Exhortations : Chinese Works in Japan as Mediated through Printed Buddhist Texts | KIMURA Michiko | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 5 | 2022 | ○ |
| 日本古典籍くずし字データセットとAIによるくずし字認識 | 北本朝展 | 日本図書館協会 | 『現代の図書館』 | 59(2) | 2021 | ○ |
| 資料調査のためのAIくずし字認識スマホアプリ「みを」 | カラーヌワット タリン, 北本 朝展 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2021論文集』 | 2021 | ○ | |
| Understanding IIIF image usage based on server log analysis | Chifumi Nishioka, Kiyonori Nagasaki | Oxford University Press | Digital Scholarship in the Humanities | Volume 36,Issue Supplement_2 | 2021 | ○ |
| 『續一切經音義』からみる漢文文献の TEI マークアップの課題 | 王一凡, 渡邉要一郎, 永崎研宣, 下田正弘 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2021論文集』 | 2021 | ○ | |
| 仏教思想の概念体系の記述手法としてのTEI マークアップの現状と課題 | 左藤仁宏, 渡邉要一郎,下田正弘 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2021論文集』 | 2021 | ○ | |
| 相互運用性を高めた日本歴史資料データ実装:『延喜式』TEI とIIIF を事例として | 小風尚樹, 中村覚, 永崎研宣, 渡辺美紗子, 戸村美月, 小風綾乃, 清武雄二, 後藤真, 小倉慈司 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2021論文集』 | 2021 | ○ | |
| デジタル時代における多様な資料継承の仕組みを包括する議論モデルの提案 | 大月希望, 大向一輝, 永崎研宣, 佐倉統 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2021-CH-126 | 2021 | |
| デジタル源氏物語(AI画像検索版):くずし字OCRと編集距離を用いた写本・版本の比較支援システムの開発 | 中村覚, 田村隆, 永崎研宣 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2022-CH-128 | 2022 | |
| 人文系学部向け人文情報学/デジタル・ヒューマニティーズ教育のためのカリキュラムについて | 永崎研宣, 長野壮一, 小風尚樹 | 情報処理学会 | 『研究報告人文科学とコンピュータ(CH)』 | 2022-CH-128 | 2022 | |
| 東アジア人文情報学の可能性についての試論 : デジタルテキスト構造化の動向を中心として | 永崎研宣 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター | KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究 | 2022 | ||
| Longing for the Refinement of the Heian Court during the Edo Period: Development of Printed Books with Kasen-e | 神作研一 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 48 | 2022 | |
| 能における宗教関係語句一斑―《放下僧・春日龍神・楊貴妃・草子洗・三輪》について | 落合博志 | 勉誠出版 | 『アジア遊学265 宗教芸能としての能楽』 | 2022 | ||
| 十七世紀狩野派の「戯画図巻」―諸本と点描― | 齋藤真麻理 | 国文学研究資料館 | 『調査研究報告』 | 42 | 2022 | |
| 《円山派粉本資料》(東洋画真蹟5226) | 古田亮 | 東京藝術大学大学美術館 | 東京藝術大学大学美術館『年報・紀要』令和2年度 | 2022 | ||
| 近代日本画の青春期 紫紅と靫彦を中心に | 古田亮 | 岡山県立美術館 | 『伊豆市所蔵近代日本画展 修善寺物語―大観と靫彦、紫紅たち』展図録 | 2022 | ||
| 小杉放菴:近代の風に吹かれて | 古田亮 | エイアンドエフ | 『ひらく』 | 6 | 2021 | |
| 欧米を魅了した花鳥画 渡辺省亭 写生をめぐる明治の美術と文学 | 古田亮 | エイアンドエフ | 『ひらく』 | 5 | 2021 | |
| 若冲画賛の研究―竹図・海老図・鯉図― | 門脇むつみ、國井星太、池田泉 | 大阪大学大学院文学研究科 | 『大阪大学大学院文学研究科紀要』 | 62 | 2022 | |
| 公家物として見る『玉水物語』 | 井黒佳穂子 | 国文学研究資料館 | 『国文学研究資料館紀要 文学研究篇』 | 48 | 2022 | |
| ODSと武鑑研究 | 藤實久美子 | 史学会 | 『日本歴史』 | 876 | 2021 | |
| ブックバーコーディング法:版本の差読に基づく「武鑑全集」の網羅的な解析に向けて | 北本 朝展, 藤實 久美子, 本間 淳 | 『じんもんこん2021論文集』 | 2021 | |||
| 동아시아 의례연구의 새로운 시각- ‘물품 목록’의 검토에서-(東アジア儀礼研究の新視角―「物品目録」の検討から―) | 稲田 奈津子 | 慶北大学校人文学術院 | 『東西人文』 | 16 | 2021 | ○ |
| 古代・中世移行期における天皇の変質-「隠蔽」される天皇 | 井上 正望 | 史学会 | 『史学雑誌』 | 130-4 | 2021 | ○ |
| 『延喜式』巻三九の写本系統と「内膳司」本文校訂(稿) | 小川 宏和 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 234 | 2022 | ○ |
| Empowering through the mundane: royal women’s households in twelfth and thirteenth century Japan | 河合 佐知子 | Routledge, Taylor & Francis Group | Japan Forum | 34 | 2022 | ○ |
| 資料紹介 九条本『諒闇部類記』翻刻(一) 付解題 | 神戸 航介、三輪 仁美 | 宮内庁書陵部 | 『書陵部紀要』 | 73 | 2022 | ○ |
| 相互運用性を高めた日本歴史資料データ実装:『延喜式』TEI と IIIF を事例として | 小風 尚樹、中村 覚、永崎 研宣、渡辺 美紗子、戸村 美月、小風 綾乃、清武 雄二、後藤 真、小倉、慈司 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2021論文集』 | 2021 | ○ | |
| 上野三碑は語る | 中村 光一 | 筑波大学日本史談話会 | 『日本史学集録』 | 42 | ||
| 天平期の疾病と風損-国家による対策と地域- | 仁藤 敦史 | 静岡県地域史研究会 | 『静岡県地域史研究』 | 11 | 2021 | |
| トネリの勘籍-徳島県観音寺遺跡出土の木簡をめぐって- | 堀部 猛 | 史学会 | 『史学雑誌』 | 130-7 | 2021 | ○ |
| 岡部洞水筆「古画模本画巻」について | 堀部 猛 | 土浦市立博物館 | 『土浦市立博物館紀要』 | 32 | 2021 | |
| 古代日本における人面墨書土器と祭祀 | 三上 喜孝 | 慶北大学校人文学術院 | 『東西人文』 | 16 | 2021 | ○ |
| 日本出土の古代木簡―戸籍と木簡― | 三上 喜孝 | 韓国木簡学会 | 『木簡と文字』 | 26 | 2022 | ○ |
| 出土文字資料から見た払田柵の機能 | 三上 喜孝 | 国立歴史民俗博物館 | 『国立歴史民俗博物館研究報告』 | 232 | 2022 | ○ |
| 出土文字資料の集成的研究 平泉出土文字資料へのアプローチ(2)片仮名木簡 | 三上 喜孝 | 「世界遺産平泉」保存活用推進実行委員会 | 『平泉学研究年報』 | 2 | 2022 | |
| 日本感霊録の史料性 | 三舟 隆之 | 日本歴史学会 | 『日本歴史』 | 881 | 2021 | ○ |
| 『日本三代実録』にみえる「告文」について | 山口 えり | 神道宗教学会 | 『神道宗教』 | 264265 | 2022 | |
| 古辞書の構造化記述の試み―『和名類聚抄』を例に― | 藤本灯、韓一、高田智和 | 国立国語研究所 | 『国立国語研究所論集』 | 21 | 2021 | ○ |
| 訓点データベースと点図の自動判別 | 堤智昭、田島孝治、小助川貞次、高田智和 | 情報処理学会 | 『情報処理学会論文誌』 | 63巻2号 | 2022 | ○ |
| 和食と魚 | 石川 智士 | 勉誠出版 | 『知っておきたい和食の文化』 | 2022 | ||
| 東アジアの律令制 | 稲田 奈津子、西本哲也 | 八木書店 | 『古代日本対外交流史事典』 | 2021 | ||
| 『延喜式』にみえる食品とその特徴 | 小倉 慈司 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する』 | 2021 | ||
| 讃岐国司解端書(いわゆる「藤原有年申文」)の再検討 | 小倉 慈司 | 思文閣出版 | 『禁裏・公家文庫研究』 | 8 | 2022 | |
| 東山御文庫本マイクロフィルム内容目録(稿)(3) | 小倉 慈司 | 思文閣出版 | 『禁裏・公家文庫研究』 | 8 | 2022 | |
| 修復された史料-国立歴史民俗博物館所蔵史料から | 小倉 慈司 | 東京大学史料編纂所 | 『古文書を科学する 料紙分析 はじめの一歩』 | 2021 | ||
| 第8章総括 第2節 南比企窯跡群における須恵器生産 | 酒井 清治 | 鳩山町教育委員会 | 『南比企窯跡群総括報告書Ⅰ』 | 2022 | ||
| 国衙工房と手工業生産 | 堀部 猛 | 雄山閣 | 『別冊季刊考古学』 | 37 | 2022 | |
| 由緒を求めて-小田氏治百五十回忌- | 堀部 猛 | 土浦市立博物館 | 第43回特別展図録『八田知家と名門常陸小田氏』 | 2022 | ||
| 東アジアの木簡 | 三上 喜孝 | 八木書店 | 『古代日本対外交流史事典』 | 2021 | ||
| 漢字文化の東アジア的展開と列島世界 | 三上 喜孝 | KADOKAWA | 『地域の古代日本 東アジアと日本』 | 2022 | ||
| むかしの落書きにはどんなことが書かれているのですか | 三上 喜孝 | 幻冬舎 | 『日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白いことばの世界』 | 2021 | ||
| 総論 古代食研究の歩みと課題 | 三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 写経生への給食の再現の諸問題 | 三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 木簡にみえる鮎の加工法 | 三舟 隆之・大平 知未 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 『延喜式』にみえる古代の漬物の復元 | 土山 寛子・峰村 貴央・五百藏 良・三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 古代における「糖(飴)」の復元 | 三舟 隆之・橋本 梓 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 古代の堅魚製品の復元ー堅魚煎汁を中心として | 三舟 隆之・中村 絢子 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 古代における猪肉の加工と保存法 | 高橋 由夏莉・内藤 千尋・西念幸江・五百藏良・三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 古代における鰒の加工・保存法の復元とその成分 | 三舟 隆之・及川 夏菜 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 古代における「豉」の復元(再録) | 小松本 里菜・今野 里咲・峰村 貴央・西念 幸江・三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 『延喜式』にみえる古代の漬物の復元古代の酢の製法(再録) | 小嶋 莉乃・小牧 佳代・峰村 貴央・五百藏 良・三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 西大寺食堂院跡出土木簡にみえる漬物の復元 | 佐藤 清香・佐藤 彩乃・五百藏良・三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 古代における「大豆餅」「小豆餅」の復元 | 高橋 奈瑠海・三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病』 | 2021 | ||
| 地方寺院の成立と国分寺建立 | 三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』 | 2020 | ||
| 古代の神仏習合 | 三舟 隆之 | 吉川弘文館 | 『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』 | 2020 | ||
| 古活字版『帝鑑図説』再考 : 『帝鑑図説』は本当に〈秀頼版〉か | 高木浩明 | 勉誠出版 | 『アジア遊学』資料論がひらく軍記・合戦図の世界 | 262 | 2021 | |
| 『黄帝内経』解題 | 真柳誠 | 日本医史学会 | 『日本医史学雑誌』 | 67(4) | 2021 | |
| 朝窒コンツェルンの評価に関する研究史的考察 : 書籍を中心にして | 任正爀 | 日本科学史学会 | 『科学史研究』 | 60(300) | 2022 | |
| 文一平の生涯と業績 (리병수《외손자가 보고 들은 호암 문일평》) | 任正爀 | 朝鮮大学校 | 『朝鮮大学校学報』 | |||
| 唐代の下第詩 : 他者への慰めという観点から | 高津孝 | 九州中國學會 | 『九州中國學會報』 | 59 | ||
| The Clustering Occurrence of “Red Sign” Auroral Events in Japanese History | RYUHO KATAOKA | 国文学研究資料館 | Studies in Japanese Literature and Culture | 6 | 2023 | ○ |
| Present status of the YU-AMS system and its operation over the past 10 years | M. Takeyama, H. Miyahara(4番目)他 | North-Holland | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms | 538 | 2023 | |
| Reconstruction of April temperatures in Kyoto, Japan, since the fifteenth century using the floral phenology of herbaceous peony and rabbit-ear iris. | Yasuyuki AONO and Ayaka NISHITANI | Springer | International Journal of Biometeorology | 66 | 2022 | |
| ICT教育における古典文学の可能性ー国文学研究資料館共同研究を紹介しながら | 宮本祐規子 | 白百合女子大学言語・文学研究センター | 『言語・文学研究論集』 | 23 | 2023 | |
| 近世における旅行情報誌と現代との接続--“楽しむ教材化”を視野に―― | 速水香織 | 信州大学教職支援センター | 『教職研究』 | 14 | 2023 | ○ |
| 古典教育の題材としての日本近世文学の可能性―ICT活用教育プログラム開発の研究報告より― | 中村綾 | 愛知学院大学教養部 | 『愛知学院大学教養部紀要』第70巻第3号 | 70 | 2023 | |
| 草双紙の本文料紙の紙質―高精細デジタル顕微鏡の観察結果を手掛かりに― | 松原 哲子 | 日本近世文学会 | 『近世文藝』 | 117 | 2023 | |
| Study of Paper used for Pictorial Books and Ukiyo-e Pictures Published during the 17th to 19th Centuries in Japan | 江南 和幸 岡田 至弘 佐藤 悟 |
IPH2022、36thCongressでの発表がKrems Bookから刊行予定。 | ||||
| 近代日本画の一側面 大正期のコンテンポラリーアート | 古田亮 | 徳島城博物館 | 『特別展 阿波藍商の〈たからもの〉』図録 | 2022 | ||
| 近代日本美術の歴史と思想 | 古田亮 | エイアンドエフ | 『ひらく』 | 7 | 2022 | |
| 朋誠堂喜三二と狩野周信―幕末明治期における「戯画図巻」受容― | 齋藤真麻理 | 国文学研究資料館 | 『調査研究報告』 | 43 | 2023 | ○ |
| 江戸狩野派による雪舟「山水長巻(四季山水図)」(毛利博物館)の学習 | 野田麻美 | 山口県立美術館 | 『雪舟と狩野派』展図録 | 2022 | ||
| 《蝦蟇帖》(大阪大学総合学術博物館蔵)とその周辺 : 江戸時代中後期の蛙図ブーム | 門脇むつみ | 大阪大学大学院文学研究科 | 『大阪大学大学院文学研究科紀要』 | 63 | 2023 | |
| 黒田長政公と縁の什物 | 門脇むつみ | 龍光院 | 『南游行』 | 8 | 2022 | |
| 「つまりたるがわろき」美意識 | 門脇むつみ | 青幻舎 | Living History in 京都・二条城協議会編『京都二条城と寛永文化』 | 2022 | ||
| 150年後の国宝を考えることの意味 | 松嶋雅人 | 東京国立博物館 | 『150年後の国宝展』 | 2022 | ||
| 大阪の佇まい―大阪風流礼賛 | 井田太郎 | 京都国立近代美術館 | 『視る』 | 521 | 2022 | |
| 仁左衛門の富樫 | 井田太郎 | 木挽堂書店 | 『劇評』 | 9 | 2022 | |
| 『花吹雪』と文化圏の転生―覚書 | 井田太郎 | 大東急記念文庫 | 『かがみ』 | 53 | 2023 | |
| 悪の華の構造 | 井田太郎 | 木挽堂書店 | 『劇評』 | 13 | 2023 | |
| 共同研究「アジアの中の日本古典籍―医学・理学・農学書を中心として―」ワークショップ報告 | 陳捷 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 2 | 2014 | |
| 「草双紙を中心とした近世挿絵史の再構築」経過報告 | 佐藤悟 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 3 | 2015 | |
| 日本漢詩文における古典形成の研究ならびに研究環境のグローバル化に対応した日本漢文学の通史の検討 | 合山林太郎 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 3 | 2015 | |
| 近世日本を中心とする東アジアの理学典籍に関する国際共同研究 | 小川束 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 4 | 2015 | |
| 文書画像の認識と理解 | 寺沢憲吾 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 4 | 2015 | |
| 国際共同研究「江戸時代初期出版と学問の綜合的研究」 | 海野圭介 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 4 | 2015 | |
| 国際共同研究「境界をめぐる文学―知のプラットフォーム構築をめざして―」 | 齋藤真麻理 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 4 | 2015 | |
| 『紀州地域に存する古典籍およびその関連資料・文化資源の基礎的研究」経過報告 | 大橋直義 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 5 | 2016 | |
| オーロラと人間社会の過去・現在・未来—古典籍・古文書が伝える江戸時代のオーロラ— | 岩橋清美 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 5 | 2016 | |
| 古典籍の若年層への普及活動 | 田中大士 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 5 | 2016 | |
| 歴史的典籍の検索機能の高度化、そしてスクリプトーム解析に向けて | 北本朝展 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 6 | 2016 | |
| 表記の位相─『延寿撮要』を例に─ | 入口敦志 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 6 | 2016 | |
| 古典オーロラハンター~新しい市民参加型研究の可能性~ | 片岡龍峰、藤原康徳 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 6 | 2016 | |
| デジタル・データの乱読時代へ | 佐藤賢一 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 7 | 2017 | |
| 古典籍を活用した和漢薬に関する総合研究の進捗状況 | 伏見裕利 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 7 | 2017 | |
| 共同研究「日本古典籍の書誌概念と書誌用語の国際化」について | 落合博志 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 8 | 2017 | |
| 「新日本古典籍総合データベース」のマルチリンガル化対応のための基礎研究 | 赤間亮、前田亮 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 9 | 2018 | |
| 「津軽デジタル風土記の構築」に向けて | 瀧本壽史 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 9 | 2018 | |
| 「古代の甘味料"あまつら"の復元」-文と理の知恵の蔓を綯い交ぜて- | 神松幸弘 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 9 | 2018 | |
| スケッチによる古典籍画像検索 | 松井勇佑、松田訓典 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 10 | 2018 | |
| 江戸時代初期出版と学問の綜合的研究 | 海野圭介 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 10 | 2018 | |
| 境界をめぐる文学―知のプラットフォーム構築をめざして― | 齋藤真麻理 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 10 | 2018 | |
| 古典籍を活用した和漢薬に関する総合研究―民族薬物データベースから『広恵済急方』情報を発信― | 小松かつ子 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 10 | 2018 | |
| 光のふるまいの解析―古典籍の光学解析に向けた基礎的研究― | 舩冨卓哉 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 11 | 2019 | |
| 「古典芸能における身体-ことばと絵画から立ち上がるもの-」について | ボナベントゥーラ・ルペルティ、山下則子 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 12 | 2019 | |
| 「くずし字OCR」技術の開発-実用的な翻刻システムの実現を見据えて- | 大澤留次郎 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 12 | 2019 | |
| 試練~文理融合研究に挑む~ | 宮﨑将 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 12 | 2019 | |
| 古代の甘味「あまつら」の復元とその試食 | 神松幸弘 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 13 | 2020 | |
| 碑文のデジタル復元に関する手法研究と実践ひかり拓本の開発 | 上椙英之 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 13 | 2020 | |
| 「津軽デジタル風土記 ねぷた見送り絵リブート!~デジタルアーカイブからよみがえる北斎の女たち~」展レポート | 木越俊介 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 13 | 2020 | |
| AIによるくずし字認識「KuroNet」 | カラーヌワット タリン | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 14 | 2020 | |
| 「偶然記録」の探究へ向けて──総合書物論の開設にあたって── | 谷川惠一 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 14 | 2020 | |
| 文学の空間を表示する「日本のデジタル文学地図」 | ユディット アロカイ | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 15 | 2021 | |
| 大英図書館ケンペル旧蔵日本古典籍コレクション | ヘイミッシュ トッド | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 16 | 2021 | |
| 史的文字データベース連携検索システムの理念と未来 | 馬場基 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 16 | 2021 | |
| 共同研究「歴史資料を活用した減災・気候変動適応に向けた文理融合研究の深化」について | 西村慎太郎、小荒井衛 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 17 | 2022 | |
| TEIから広げる古典籍デジタルテキスト基盤の未来 | 岡田一祐 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 17 | 2022 | |
| 料紙分析に期待すること | 松原哲子 | 国文学研究資料館 | 『ふみ』 | 18 | 2022 | |
| くずし字認識のためのKaggle機械学習コンペティションの経過と成果 | 北本朝展、カラーヌワット タリン、Alex Lamb、Mikel Bober-Irizar | 情報処理学会 | 『じんもんこん2019論文集』 | 2019 | 〇 | |
| くずし字認識の進化とサービス化の展開 | カラーヌワット, タリン、北本朝展 | 情報処理学会 | 『じんもんこん2020論文集』 | 2020 | 〇 | |
| 日本の古典籍を用いたオーロラ研究から考える古文・漢文の学習 | 片岡龍峰 | 成蹊学園・成蹊大学サステナビリティ教育研究センター | 『サステナビリティ教育研究』 | 5 | 2023 |
著書
| 『書名』 | 著者名 | 出版社名 | 発行年 | ISBN番号 |
|---|---|---|---|---|
| 古代の東国3「覚醒する〈関東〉」 | 荒井秀規 | 吉川弘文館 | 2017 | 9784642068208 |
| 訳注日本史料 延喜式 下巻 | 虎尾俊哉編、相曽貴志・荒井秀規・小倉慈司・中村光一・早川万年・堀部猛・三上喜孝 | 集英社 | 2017 | 9784081970100 |
| 都霊聖殮布 | 共訳 林潔、郭南燕(解説) | 良友之声出版社 | 2017 | 9789881472755 |
| キリシタンが拓いた日本語文学 多言語多文化交流の淵源 | 郭南燕(編著) | 明石書店 | 2017 | 9784750345574 |
| ザビエルの夢を紡ぐ : 近代宣教師たちの日本語文学 | 郭南燕(著) | 平凡社 | 2018 | 9784582703580 |
| NHKカルチャーラジオ『科学と人間「太陽フレアと宇宙災害」』 | 片岡龍峰 | NHK出版 | 2017 | 9784149109749 |
| 自然と人間の関係の地理学 | 安田喜憲・高橋学編 | 古今書院 | 2017 | 9784772241854 |
| 後醍醐天皇 | 兵藤裕己 | 岩波書店 | 2018 | 9784004317159 |
| 初中等学校における古典教育 | 小山順子編 | 国文学研究資料館 | 2019 | 9784875921967 |
| ミッションスクールになぜ美人が多いのか 日本女子とキリスト教 | 井上章一、郭南燕、川村信三 | 朝日新聞出版 | 2018 | 9784022737953 |
| ブックレット〈書物をひらく〉18「オーロラの日本史: 古典籍・古文書にみる記録」 | 岩橋清美、片岡 龍峰 | 平凡社 | 2019 | 9784582364583 |
| 山梨県南アルプス市上宮地横小路家文書目録 | 南アルプス市 | 南アルプス市教育委員会 | 2018 | |
| ブックレット〈書物をひらく〉23「『無門関』の出世双六: 帰化した禅の聖典」 | ディディエ・ダヴァン | 平凡社 | 2020 | 9784582364637 |
| L"Intendente Sansho di Mori Ogai | マチルデ・マストランジェロ | Marietti | 2019 | 9788821110146 |
| 在外絵入り本 研究と目録 | 山下 則子 | 三弥井書店 | 2019 | 9784838233557 |
| 医学・科学・博物 東アジア古典籍の世界 | 陳捷 | 勉誠出版 | 2020 | 9784585200727 |
| 津軽デジタル風土記資料集-弘前大学・国文学研究資料館共同研究成果報告書- | 瀧本壽史 渡辺麻里子 木越俊介 谷川惠一 |
国立大学法人弘前大学 人間文化研究機構国文学研究資料館 |
2020 | |
| ブックレット〈書物をひらく〉21「江戸水没 : 寛政改革の水害対策」 | 渡辺浩一 | 平凡社 | 2019 | 9784582364613 |
| ブックレット〈書物をひらく〉24「アワビと古代国家 『延喜式』にみる食材の生産と管理」 | 清武 雄二 | 平凡社 | 2021 | 9784582364644 |
| 古代氏族と地方寺院 | 三舟 隆之 | 同成社 | 2020 | 9784886218438 |
| 絵入巻子本 伊曽保物語 | ローレンス マルソー編・校注 | 臨川書店 | 2021 | 9784653044673 |
| ニッポンの型紙図鑑 | 加茂 瑞穂 | 青幻舎 | 2020 | 9784861527753 |
| 江戸のことば絵事典―『訓蒙図彙』の世界 | 石上 阿希 | KADOKAWA | 2021 | 9784047036017 |
| 寺院文献資料学の新展開5ー中四国諸寺院Ⅰー | 中山一麿(監修)、落合博志(編) | 臨川書店 | 2020 | 9784653045458 |
| 古代日本と渡来系移民 百済郡と高麗郡の成立 | 須田 勉、荒井 秀規 | 高志書院 | 2021 | 9784862152169 |
| 儀礼・象徴・意思決定 | 小口 雅史 | 思文閣 | 2021 | 9784784219919 |
| 自然史・理工系研究データの活用 | 中村 覚責任編集 | 勉誠出版 | 2020 | 9784585202837 |
| 新釈全訳 日本書紀 上巻(巻第一~巻第七) | 神野志 隆光、金沢 英之、福田 武史、三上 喜孝 | 講談社 | 2021 | 9784065153598 |
| 仮名草子集成 | 勝又 基 | 東京堂出版 | 2021 | 9784490307924 |
| 文化・情報の結節点としての図像――絵と言葉がつがぐ近世・近代の文化圏 | 山田 奨治、石上 阿希(編著) | 晃洋書房 | 2021 | 9784771034440 |
| 源氏物語(九)蜻蛉-夢浮橋/索引 | 柳井滋、室伏信助、大朝雄二、鈴木日出男、藤井貞和、今西祐一郎 校注 | 岩波書店 | 2021 | 9784003510230 |
| 玄奘三蔵 新たなる玄奘像をもとめて | 桑山正進、佐久間秀範、吉村誠、橘川智昭、師茂樹、ステフェン・デル、蓑輪顕量、阿部龍一、肥田路 美、荒見泰史、李銘敬、本井牧子、谷口耕生、落合博志、レイチェル・サンダーズ、近本謙介 |
勉誠出版 | 2021 | 9784585310051 |
| ブックレット〈書物をひらく〉27「妖怪たちの秘密基地―つくもがみの時空―」 | 齋藤真麻理 | 平凡社 | 2022 | 9784582364675 |
| 日本古代天皇の変質-中世的天皇の形成過程- | 井上 正望 | 塙書房 | 2022 | 9784827313307 |
| 古代律令国家と神祇行政 | 小倉 慈司 | 同成社 | 2021 | 9784886218667 |
| Uncertain Powers: Sen’yōmon-in and Landownership by Royal Women in Early Medieval Japan | 河合 佐知子 | Harvard University Asia Center | 2021 | 9780674260160 |
| 藤原仲麻呂 | 仁藤 敦史 | 中央公論新社 | 2021 | 9784121026484 |
| 近世日記の世界 | 福田千鶴・藤實久美子 | ミネルヴァ書房 | 2022 | 9784623093694 |
| 運ぶ―文化とかたち | 小川 宏和・松本 美虹 | 武蔵野美術大学 美術館・図書館 | ||
| 新書版 性差の日本史 | 国立歴史民俗博物館監修・「性差の日本史」展示プロジェクト編 | 集英社 | 2021 | 9784797680836 |
| 古代の食を再現する―みえてきた食と生活習慣病 | 三舟 隆之・馬場 基編 | 吉川弘文館 | 2021 | 9784642046619 |
| テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編 | 佐藤 信監修・新古代史の会(三舟 隆之ほか)編 | 吉川弘文館 | 2020 | 9784642083843 |
| 印刷博物館講演録「印刷博物館20周年記念トークイベント 第1回印刷文化会議 テキストと版画―印刷による知の循環」 | 樺山浩一、小秋元段、入口敦志 | 印刷博物館 | 2022 | |
| EXTREME SPACE WEATHER | RYUHO KATAOKA | Elsevier | 2022 | 9780128225370 |
| Solar-Terrestrial Environmental Prediction | K. Kusano編集(H. Miyahara 分担執筆) | SpringerLink | 2023 | 9789811977657 |
| 幕末・明治期の巷談と俗文芸 | 神林 尚子 | 花鳥社 | 2023 | 9784909832733 |
| 近世後期江戸小説論攷 | 山本 和明 | 勉誠社、2023年2月 | 2023 | 9784585390220 |
| 新訳 東洋の理想 | 古田亮 | 平凡社 | 2022 | 9784582288162 |
ブックレット
| 『書名』 | 著者名 | 出版社名 | 発行年 | ISBN番号 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 死を想え『九相詩』と『一休骸骨』 | 今西 祐一郎 | 2016/12 | 9784582364415 |
| 第2号 | 漢字・カタカナ・ひらがな | 入口 敦志 | 2016/12 | 9784582364422 |
| 第3号 | 漱石の読みかた 『明暗』と漢籍 | 野網 摩利子 | 2016/12 | 9784582364439 |
| 第4号 | 和歌のアルバム | 小山 順子 | 2017/4 | 9784582364446 |
| 第5号 | 異界へいざなう女 | 恋田 知子 | 2017/4 | 9784582364453 |
| 第6号 | 江戸の博物学 | 高津 孝 | 2017/7 | 9784582364460 |
| 第7号 | 園芸の達人 本草学者・岩崎灌園 | 平野 恵 | 2017/7 | 9784582364484 |
| 第8号 | 和算への誘い | 上野 健爾 | 2017/7 | 9784582364477 |
| 第9号 | 南方熊楠と説話学 | 杉山 和也 | 2017/11 | 9784582364491 |
| 第10号 | 聖なる珠の物語 | 藤巻 和宏 | 2017/11 | 9784582364507 |
| 第11号 | 天皇陵と近代 | 宮間 純一 | 2018/5 | 9784582364514 |
| 第12号 | 熊野と神楽 | 鈴木 正崇 | 2018/5 | 9784582364521 |
| 第13号 | 神代文字の思想 | 吉田 唯 | 2018/5 | 9784582364538 |
| 第14号 | 海を渡った日本書籍 | ピーター・コーニツキー | 2018/8 | 9784582364545 |
| 第15号 | 伊勢物語 流転と変転 | 山本 登朗 | 2018/8 | 9784582364552 |
| 第16号 | 百人一首に絵はあったか | 寺島 恒世 | 2018/11 | 9784582364569 |
| 第17号 | 歌枕の聖地 | 山本 啓介 | 2018/11 | 9784582364576 |
| 第18号 | オーロラの日本史 | 岩橋 清美・片岡 龍峰 | 2019/03 | 9784582364583 |
| 第19号 | 御簾の下からこぼれ出る装束 | 赤澤 真理 | 2019/03 | 9784582364590 |
| 第20号 | 源氏物語といけばな | 岩坪 健 | 2019/03 | 9784582364606 |
| 第21号 | 江戸水没 | 渡辺 浩一 | 2019/03 | 9784582364613 |
| 第22号 | 時空を翔ける中将姫 | 日沖 敦子 | 2020/03 | 9784582364620 |
| 第23号 | 『無門関』の出世双六 | ディディエ・ダヴァン | 2020/03 | 9784582364637 |
| 第24号 | アワビと古代国家 | 清武 雄二 | 2021/03 | 9784582364644 |
| 第25号 | 春日懐紙の書誌学 | 田中 大士 | 2021/03 | 9784582364651 |
| 第26号 | 「いろは」の十九世紀 | 岡田 一祐 | 2022/03 | 9784582364668 |
| 第27号 | 妖怪たちの秘密基地 | 齋藤 真麻理 | 2022/03 | 9784582364675 |
| 第28号 | 知と奇でめぐる近世地誌 | 木越 俊介 | 2023/03 | 9784582364682 |
| 第29号 | 雲は美しいか | 渡部 泰明 | 2023/03 | 9784582364699 |
| 第30号 | 八王子に隕ちた星 | 森 融 | 2023/11 | 9784582364705 |
| 第31号 | 雨森芳洲の朝鮮語教科書 | 金子 祐樹 | 2023/11 | 9784582364712 |
プレスリリース
NW構築計画において実施された共同研究成果等を用いて行われた学会発表等のリストを公開しています。下記リンク先から一覧データをご覧になれます。
