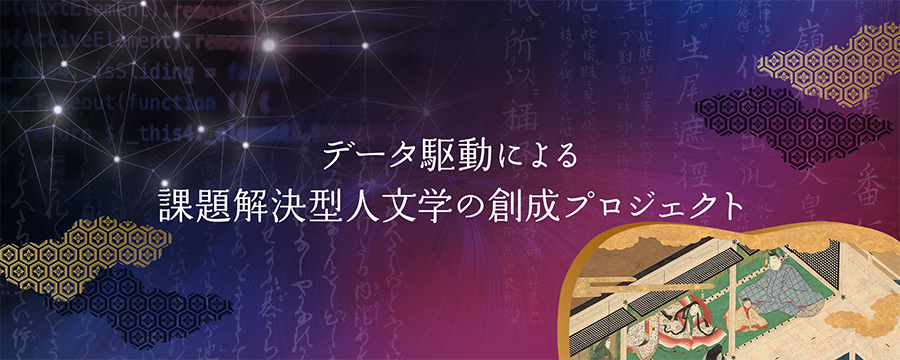本事業の概要
目次
本事業について
文部科学省の大規模学術フロンティア促進事業に人文・社会系ではじめて採択された歴史的典籍NW事業は、国文学研究資料館が中心となり、国内外の大学等の研究機関・図書館と連携して日本語の歴史的典籍約30万点全冊のデジタル画像化を行い、国文学研究資料館が従前より構築してきた歴史的典籍の書誌情報データベースと統合し、諸分野の研究利用に資する大規模データベースとしてWeb上で公開し、その画像を用いた国際的な共同研究のネットワークを構築した事業です。
事業ポスター(2023年4月改訂版)PDF拠点大学について
歴史的典籍NW事業は、国外12機関、国内20機関を拠点として開始し、国外拠点は19機関に拡充しました。
国外拠点(19機関)
コレージュ・ド・フランス日本学高等研究所、コロンビア大学、高麗大学校、フィレンツェ大学、北京外国語大学、ライデン大学、ヴェネツィア カ・フォスカリ大学、ナポリ大学オリエンターレ、サピエンツァ ローマ大学、バチカン市国図書館、ブリティッシュ・コロンビア大学、ケンブリッジ大学、カリフォルニア大学バークレー校東アジア図書館、ベルリン国立図書館、ハワイ大学マノア校、ハイデルベルク大学、ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン、大英図書館、フリーア美術館/アーサー・M・サックラー・ギャラリー(スミソニアン協会)
国内拠点(20機関)
北海道大学、広島大学、東北大学、九州大学筑波大学、慶應義塾大学東京大学、國學院大学お茶の水女子大学、立教大学名古屋大学、早稲田大学京都大学、大谷大学大阪大学、同志社大学神戸大学、立命館大学奈良女子大学、関西大学
実施体制
平成25(2013)年度予算として準備経費が措置され、平成25(2013)年4月に、国文研に、古典籍データベース研究事業センターを設置し、事業開始に向けて準備を進めました。
事業を開始した平成26(2014)年4月に、NW構築計画を推進する中心的部署として、古典籍データベース研究事業センターを改組した古典籍共同研究事業センターを設置し、事業を推進しました。
古典籍データベース研究事業センター
平成25(2013)年10月現在
| センター長 | 今西 祐一郎 | 副センター長 | 山本 和明 | 准教授 | 北村 啓子 |
古典籍共同研究事業センター
平成26(2014)年4月現在
| センター長 | 今西 祐一郎 | 副センター長 | 山本 和明 | 特任教授 | 中村 康夫 |
| 准教授 | 北村 啓子 | 特任准教授 | 金田 房子 |
平成27(2015)年4月現在
| センター長 | 今西 祐一郎 | 副センター長 | 山本 和明 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 特任准教授 | 岩橋 清美 | 特任准教授 | 金田 房子 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 |
平成28(2016)年4月現在
| センター長 | 今西 祐一郎 | 副センター長 | 山本 和明 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 特任准教授 | 岩橋 清美 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 | 特任助教 | 松田 訓典 |
平成29(2017)年4月現在
| センター長 | 谷川 惠一 | 副センター長 | 山本 和明 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 特任准教授 | 岩橋 清美 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 | 特任助教 | 松田 訓典 |
平成30(2018)年4月現在
| センター長 | 谷川 惠一 | 副センター長 | 山本 和明 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 特任准教授 | 岩橋 清美 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 | 特任助教 | 岡田 一祐 |
| 特任助教 | 松田 訓典 |
平成31/令和元(2019)年4月現在
| センター長 | 谷川 惠一 | 准教授 | 北村 啓子 | 特任准教授 | 岩橋 清美 |
| 特任准教授 | 宮本 祐規子 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 | 特任助教 | 岡田 一祐 |
| 特任助教 | 松田 訓典 |
令和2(2020)年4月現在
| センター長 | 山本 和明 | 副センター長 | 神作 研一 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 特任准教授 | 宮本 祐規子 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 | 特任助教 | 松田 訓典 |
令和3(2021)年4月現在
| センター長 | 山本 和明 | 副センター長 | 神作 研一 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 准教授 | 松田 訓典 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 |
令和4(2022)年4月現在
| センター長 | 山本 和明 | 副センター長 | 神作 研一 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 准教授 | 松田 訓典 | 特任助教 | 井黒 佳穂子 | 特任助教 | 幾浦 裕之 |
令和5(2023)年4月現在
| センター長 | 山本 和明 | 副センター長 | 神作 研一 | 准教授 | 北村 啓子 |
| 准教授 | 松田 訓典 | 特任助教 | 幾浦 裕之 |
事業の成果
世界でも有数な質及び量を有し、千年にわたる事象の記録が確認されている日本語の歴史的典籍を、各図書館等の書庫内に留めず、Web上で利活用可能な研究資源とすることにより、所蔵機関や国文研に訪問し、研究資料情報を得るしかなかった従来の研究環境を大幅に改善し、その情報入手難による研究推進の障壁を取り除くとともに、自然科学系を含む国内外の幅広い分野の研究者が、埋もれた知の宝庫である日本の歴史的典籍を、研究資源として自在に活用できる研究基盤として、「新日本古典籍総合データベース」(令和5(2023)年3月に「国書データベース」として発展的に統合)を構築しました。
これと併行して、歴史的典籍を利活用していくための国際共同研究ネットワークを国内外の大学・研究機関の参画により構築し、歴史的典籍から新たな知見を導き出す共同研究を実施しました。
歴史的典籍に集積されてきた膨大な「日本の知」を、現代社会に活きたものとして自在に活用する環境整備により、歴史的典籍が多くの研究者、市民に開かれ、新たな発想や文化形成に繋げていくものであるとともに、文化財危機(原本資料の破損・劣化、自然災害による消失等)への対応として、日本の文化財の後世への継承にも貢献しています。
日本古典籍研究国際コンソーシアムの設立
令和2(2020)年11月に、これまでに構築した国内外の研究機関とのネットワークを基盤として、
①若手人材(学生、研究者、司書・学芸員・アーキビスト等の専門職員)の育成、
②先端的研究と研究成果発信等に関する情報・資源の共有と活用、
③データベースの活用等に関する情報・意見の交換を目的とする「日本古典籍研究国際コンソーシアム」を、
国文研が幹事機関となり、国内外の機関と共同して設立しました。
当初目標は令和3(2021)年度までに50機関でしたが、実績はこれを大きく上回り、令和5(2023)年度末現在で、国外42機関、国内41機関の計83機関の参加を得ました。
各種委員会・委員名簿
国文学研究資料館に設置した古典籍共同研究事業センターでは、各種委員会を設置し、運営の円滑化を図っています。
- 日本語歴史的典籍ネットワーク委員会PDF 事業計画に関するモニタリング、事業の評価に関すること等を行います。
- センター運営委員会PDF センターの管理運営に関する重要事項を審議します。
- 国際共同研究ネットワーク委員会PDF 国際共同研究ネットワークの構築や、国際共同研究の企画立案及び統括に関することを審議します。
- 拠点連携委員会PDF センターと国内拠点との連絡調整等を行います。
- データベース高度化専門員PDF 専門的で高度な知見を踏まえ、新日本古典籍総合データベースの検索機能の高度化に関することを行います。
- タグ付けワーキンググループPDF データベースの汎用性を高める上で重要な「タグ付け」の今後の方針を検討しました。(平成26年度~平成29年度終了)
- 資料活用連絡協議会PDF 各分野の研究者コミュニティとの連絡協力体制を築き、各分野の専門家による高度な知見に基づきデータベースの高度化を図りました。 (平成30年度~令和 2年度終了)