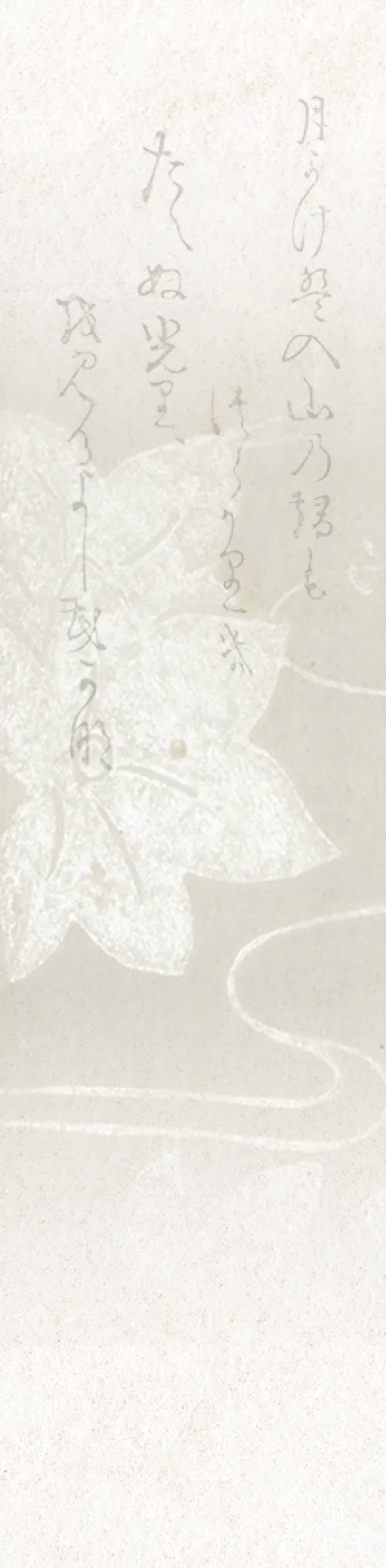在学生・修了生の声
日本文学研究コースの在学生・修了生の声を、コース案内より一部抜粋してご紹介します。
全文は以下のコース案内よりご覧ください。
在学生の声
坂井 彪さん(2023年4月入学)
私は中世の様々なテキストで見られる宝剣(草薙剣)叙述に関する研究を行っています。その上で、多くのテキストを扱うことが肝要になりますが、日本文学研究コースの基盤機関である国文学研究資料館には、原本資料、紙焼き写真本、マイクロフィルム、その他図書や雑誌等、膨大な資料があるので、これらを活用して日々研究を進めています。本コースの院生は、書庫に立ち入って資料(貴重書や特別コレクション等を除く)を直接手に取ることができ、貸出の手続きを行えば、資料を院生室で閲覧することも可能です。国文研の豊富な資料を思う存分利用できる点こそが、本コースの最大の魅力と言えるでしょう。
水嶋 彩乃さん(2023年4月入学)
私は日本文学研究コースにて、「鎌倉~南北朝期の公家社会と芸能」というテーマで研究を進めています。当該期の公家社会の構成員がどのような人的・社会的関係を結んでいたかと、その諸関係を前提に芸能、特に管絃がどのように担われてきたかを分析しています。
充実した研究指導と研究支援を受けられた初年度を終え、本コースへの進学を決心して本当に良かったと実感しております。
講義では、研究テーマと密接に関係する、近世朝廷と公家の家業について学ぶことができました。受講前は、自身のテーマの最終的な到達点が近世の家業との接続になるだろうと漠然と考えていましたが、講義の中で家業という概念が想定以上に流動的だったことに気づき、研究の方向性を定めることができました。
修了生の声
伊藤 美幸さん(2025年3月修了)
充実した国文学研究資料館の環境
私は切附本(きりつけぼん)(幕末明治期に出版された中本書型の読み物で、題材は一代記・軍談・敵討等)を研究していますが、自身の研究対象だけではなく、同時期に制作された出版物を多く見ることが研究を進める上で非常に重要となってきます。膨大な資料を所蔵する国文学研究資料館の環境で、江戸後期から明治二十年頃に制作された版本や写本などを多数閲覧することができ、資料に対する洞察力や感性が着実に養われました。また、誠実に資料に向き合うことで、研究の一歩を踏み出すべき方向性や手応えを得られたことは、国文研に在籍していなければ得られないものでした。
学位取得までに苦労した点
これまでの投稿論文を単純に並べただけでは博士論文にはなりません。博士論文全体の一貫性を意識しながら、各章の研究目的・意義・方法・主張などが適切かどうかを見極めるのが難しかったです。また、表記揺れの修正をはじめ、図版や表の調整といった細かい作業も多く、手間と時間がかかりました。
学位取得を目指す方へ
時間はあっという間に過ぎていくので、学位取得に向けて早めに執筆を始め、計画的に進められるとよいと思います。また、国文学研究資料館が所蔵する膨大な資料や研究データを大いに活用してください。
小野 光絵さん(2022年9月修了)
本専攻の院生としては私の研究内容は少し異質だったため、進学を考えている方々にはあまり参考にならないかもしれませんが、主な研究対象は尾崎翠、倉橋由美子、中井英夫などの、幻想性の強い日本近現代文学です。人が生身の人間として生きる上で自分自身の中からこぼれ落ちてしまう理想の在り方が、いかに語られているかという具体的ありように強い関心を向けてきました。博士論文は、「日本近現代文学に於ける〈精神の両性具有〉表象研究」という題目のもと執筆しました。
本専攻を志す決め手となったのは、時には講義がマンツーマンになることも珍しくない、ごく少人数での指導環境です。単に学生の数が少ないだけでなく、学生数に対して先生が大勢在籍されているという点が本専攻の大きな特色の一つです。
学位取得までに苦労した点は少なくありませんが、一番の悩みは研究対象の絞り込みと研究テーマの設定でした。私が強い関心を向ける作家のテクストはどれも観念性が高く、だからこそ、具体的なテクスト分析と、それを背後で支える実証的なアプローチとのバランスにも苦戦しました。豊かな資料に基づいた丹念な研究に重きを置く本専攻の風土から、私に欠けていた多くを学びました。また、ここまで研究を続けてこられたのは、指導教員の先生方の忍耐強いご指導のおかげに他なりません。本専攻が気になられている方は是非、入学説明会への参加をお勧めします。